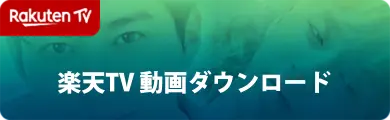StreamFab 動画 ダウンローダー
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次>
パワー・オブ・ザ・ドッグ(2021)
| 監督 | ジェーン・カンピオン |
| 評価 | 4.10 |
解説
[Netflix作品]『ブライト・スター ~いちばん美しい恋の詩(うた)~』などのジェーン・カンピオンが監督を務めたドラマ。冷酷な牧場主が、ある女性をめぐって弟に激しい憎しみを抱く。『クーリエ:最高機密の運び屋』などのベネディクト・カンバーバッチ、『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』などのキルステン・ダンスト、ジェシー・プレモンス、コディ・スミット=マクフィーらが出演する。
あらすじ
1920年代のアメリカ・モンタナ州。周囲の人々に畏怖されている大牧場主のフィル(ベネディクト・カンバーバッチ)は、夫を亡くしたローズ(キルステン・ダンスト)とその息子ピーター(コディ・スミット=マクフィー)と出会う。ローズに心を奪われるフィルだったが、弟のジョージ(ジェシー・プレモンス)が彼女と心を通わせるようになって結婚してしまう。二人の結婚に納得できないフィルは弟夫婦に対して残忍な仕打ちを執拗(しつよう)に続けるが、ある事件を機に彼の胸中に変化が訪れる。
羅生門(1950)
| 監督 | 黒澤明 |
| 評価 | 3.91 |
解説
芥川龍之介の小説「藪の中」を故・黒澤明監督が映画化した時代劇。ある侍の死に立ち会った、男女4人それぞれの視点から見た事件の内幕を生々しく再現する。本作の成功で黒澤監督とともに海外で高い評価を受けた三船敏郎や、『七人の侍』などの名優志村喬、大映の看板女優だった京マチ子ら豪華キャストが共演。1951年のヴェネチア国際映画祭でグランプリを受賞した、モノクロームの斬新で美しい映像や、俳優たちの鬼気迫る熱演に魅了される。
あらすじ
平安時代、羅生門の下で雨宿りをする下男(上田吉二郎)相手に、旅法師(千秋実)と杣売り(志村喬)が奇妙な話を語り始める。京の都で悪名高き盗賊多襄丸(三船敏郎)が山中で侍夫婦の妻(京マチ子)を襲い、夫(森雅之)を殺害したという。だが、検非違使による調査が始まると、盗賊と妻の証言はまったく異なっており……。
映画レポート
※ここは「新作映画評論」のページですが、新型コロナウイルスの影響で新作映画の公開が激減してしまったため、「映画.com ALLTIME BEST」に選ばれた作品の映画評論を掲載しております。
韓国のポン・ジュノ監督「パラサイト 半地下の家族」が、第92回アカデミー賞で作品賞はじめ4冠に輝くという歴史的な快挙を成し遂げたのが今年2月。ポン・ジュノという名前、韓国映画のクオリティの高さを世界に、そしてハリウッドの映画人に知らしめた。アジア映画として初の快挙であり、アジア映画史の新しい局面を切り開いた。
しかし今から約70年前。世界にクロサワの名前を、日本映画の存在を知らしめた歴史的作品がある。日本映画として初めて第12回ベネチア国際映画祭でグランプリの金獅子賞を受賞し、第24回アカデミー賞名誉賞を受賞した黒澤明監督の「羅生門」(1950)だ。この受賞から吉村公三郎監督「源氏物語」(1951)、溝口健二監督「雨月物語」(1953)、衣笠貞之助監督「地獄門」(1953)など、日本映画が次々と海外映画祭で評価されていった。
映画ファンであれば、黒澤明、「羅生門」のことは知っていると思うが、もしかしたら10代、20代の世代は未見の方が多いのではないか。モノクロの時代劇というだけで、これまで見ることを先送りにしてきた方は、この機会に是非確認して欲しい。「パラサイト」の70年も前に、アジアの映画が世界から評価されるきっかけとなった一本で、その後の世界の映画人に影響を与えた。
原作は芥川龍之介の短編「藪の中」。時は平安時代の乱世、都にほど近い山中で侍夫婦が盗賊に襲われ、夫の侍が殺される。やがて盗賊は捕われるが、盗賊と侍の妻、目撃者らの食い違う証言がそれぞれの視点から描かれる。見栄や虚栄のための嘘により、人間のエゴイズムがあぶり出され、黒澤監督と橋本忍による脚本がこの世の真実とは何かを追求している。
さらに、この映画の見所は物語構造とともに、その映像美と役者たちの演技にある。豪雨の中に浮き立つ荒廃した羅生門の造形美から始まり、盗賊、侍とその妻の森の中での立ち回りシーンの迫力、語り部となる杣(そま)売りと旅法師らの羅生門下でのやり取りなどすべてが印象深い。夏の森の中の光と影のコントラストの中で、盗賊を演じた三船敏郎の力強くも滑稽な野性味が繰り返される証言シーンを牽引し、侍の妻を演じた京マチ子が女性の内なる強さや妖艶さを見事に表現。木漏れ日の光に照らし出される表情が美しさを増し、モノクロの映画でありながら色彩を感じさせる。自然光を生かし、静と動を使い分けたカメラワークにより、風、雨、太陽の熱を捉えた宮川一夫の画期的な撮影も必見だ。
また森雅之が演じる侍の高貴さが対比となり、美しい妻の前で追いやられた男の無念さ、自我を浮き立たせ、志村喬が演じる杣売りらをこの世の藪の中へと引きずり込んでいく。役者たちの目の表情に圧倒されるに違いない。そしてラストの解釈は、この映画を見た者のエゴイズムが問われることになるだろう。
田舎司祭の日記(1950)
| 監督 | ロベール・ブレッソン |
| 評価 | 4.00 |
解説
北フランスの寒村に赴任した、若い司祭と村人たちとの関係を描いた人間ドラマ。ジョルジュ・ベルナノスの小説を原作に、布教と善行に務める司祭と、村人たちの間に生まれるずれを映し出す。監督と脚本を手掛けるのは、『抵抗(レジスタンス)-死刑囚の手記より-』などのロベール・ブレッソン。職業俳優ではなく素人を起用し、音楽やカメラの動きなどの演出をできる限り廃したスタイルで撮り上げた。
あらすじ
北フランスの村に赴任した若い司祭(クロード・レデュ)は、村人たちの悩みに真摯(しんし)に耳を傾け、日々の出来事を日記につづっていく。自身の体調不良を抱えながら布教と善行に務めるものの、真面目すぎる司祭の行動は村人たちの反感を買い、やがて孤立していく。司祭と村人たちのギクシャクした関係はやがて、思いがけない事態を招く。
ノクターナル・アニマルズ(2016)
| 監督 | トム・フォード |
| 評価 | 3.54 |
解説
『シングルマン』で監督デビューしたファッションデザイナー、トム・フォードがメガホンを取って放つサスペンスドラマ。オースティン・ライトの小説「ミステリ原稿」を基に、リッチな生活を送る主人公と彼女の元夫が書いた過激な小説の世界がリンクしていく様子を描く。『アメリカン・ハッスル』などのエイミー・アダムスが主人公を演じる。共演は『ナイトクローラー』などのジェイク・ギレンホールや『ドリーム ホーム 99%を操る男たち』などのマイケル・シャノンら。
あらすじ
アートギャラリーの経営者スーザン(エイミー・アダムス)は、夫ハットン(アーミー・ハマー)と裕福な生活をしていたが、心は空っぽだった。ある日彼女のもとに、20年前に離婚した元夫エドワード(ジェイク・ギレンホール)から、彼が書いた「夜の獣たち(ノクターナル・アニマルズ)」という小説が届く。
映画レポート
「セットではスーツを着て撮影にあたった。スーツが僕の制服だから。ニットを身につけると自分が弱々しく、脆くなった気がする」
二本目の監督作「ノクターナル・アニマルズ」を放ったトム・フォードのそんな発言を、ガーディアン紙のインタビューでみつけて大いに興味をかきたてられた。同じ記事で「スーツは僕の鎧」とも語っているフォードは、その監督デビュー作「シングルマン」の主人公をまさに鎧のように身を守る優雅なスーツ姿で登場させていた。新たな快作でも彼は、一部の隙もないドレスとメイクでヒロイン、スーザンの初登場場面を印象づける。
LAの現代アート界でしのぎをけずるギャラリー・オーナー、スーザンの居場所は、モード界の先端をゆくデザイナー、フォードのそれとも無縁ではないだろう。そこで闘いぬくために内面の葛藤を封印する鎧/服装術を必要とするような存在。その戦闘モードがふっとほころびを見せる時を2本の映画で監督フォードが素材にしているのはやはり見逃せない。完璧で強い戦士としての自分に絶大な自信をもち、そのイメージを迷いなく世界に発信するクリエイターが、内にある弱さや脆さや傷つき易さと対峙するために映画というもうひとつの創造の場を耕しているようにも思えるからだ。
20年前に別れた夫が送ってきた小説を読むスーザンが、小説内で展開される陰惨な事件の向こうに裏切った自分への前夫の復讐の思いを重ね、若き日を回想しつつ壊れた関係の再生に淡い期待を抱く――。そんなプロットを現実と小説、現在と過去とを交錯させる多重構造の中で緻密に制御する監督フォードは、読書するヒロインをメイクなしの素顔とセーター姿で差し出してみせる。鎧を脱いだ、脆く弱々しい状態のひとり。現実の自分には許容し難いそんな状態もここでなら解き放てるというように、封印してきた罪悪感や後悔や取り戻し難い夢と向き合うスーザンをフォードの映画は残酷に、真摯に、みごとに率直にみつめ切る。ヒロインの内なる自分との対話の時は精密な色彩設計を味方につけ、やがて繊細な心理メロドラマとしてスリリングに紡ぎ直される。そうしてそこに現出される映画の完璧なルック。監督フォードのしたたかな強さを思い知る。
ジョーカー(2019)
| 監督 | トッド・フィリップス |
| 評価 | 4.11 |
解説
『ザ・マスター』『ビューティフル・デイ』などのホアキン・フェニックスが、DCコミックスの悪役ジョーカーを演じたドラマ。大道芸人だった男が、さまざまな要因から巨悪に変貌する。『ハングオーバー』シリーズなどのトッド・フィリップスがメガホンを取り、オスカー俳優ロバート・デ・ニーロらが共演。『ザ・ファイター』などのスコット・シルヴァーがフィリップス監督と共に脚本を担当した。
あらすじ
孤独で心の優しいアーサー(ホアキン・フェニックス)は、母の「どんなときも笑顔で人々を楽しませなさい」という言葉を心に刻みコメディアンを目指す。ピエロのメイクをして大道芸を披露しながら母を助ける彼は、同じアパートの住人ソフィーにひそかに思いを寄せていた。そして、笑いのある人生は素晴らしいと信じ、底辺からの脱出を試みる。
映画レポート
ダース・ベイダーに悪感情も恨みもないが、自分はヒール(悪役)の起源を描いた映画を、あまり好ましいものとは思っていない。かつては優しく純粋だった人物が、自己犠牲のすえにやまれず暗黒面へと身を寄せる。そんな綺麗ごとによって正当化される悪に、はたして説得力などあるのだろうか?
ヒーローコミックス「バットマン」の宿敵として登場するジョーカーは、廃液の満ちたタンクに落下し、異貌となった形相が本性を肥大化させ、世界で最も知られるヴィランの一人となった。だが彼の出自を再定義する本作は、そんな固定されたジョーカー伝説とは異質のコースをたどる。心を病み、それでも人々に笑いを提供する貧しい大道芸人が、社会からの孤立や資本主義がもたらす貧富格差といった膿汁で肺を満たされ、呼吸困難からあえぐように悪の水面へと浮かび上がっていく。苦しいのか、それとも開放感から出る笑みなのか分からぬ表情で。
このようにジョーカーこと主人公アーサー(ホアキン・フェニックス)は、自ら道を選んで悪の轍を踏んだわけではない。そこにはダークヒーローなどといった気取ったワードとは無縁の、逃れられない運命の帰結として悪が存在する。人生に選択の余地を与えぬ、容赦ない哀しみの腐臭を放ちながら。
監督のトッド・フィリップスは「ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(09)を代表作とするコメディ一辺倒の手練れだが、「全身ハードコア GGアリン」(93)などキャリア初期のドキュメンタリーで得た人間観察の慧眼を助力に、“喜劇”のコントラストとしてそこにある“悲劇”へと踏み込んでいく。なので想定外の人選では決してない。コメディ作家だからこそ到達が可能な、そんな不可触領域にジョーカーは潜在していたのだから。
加えて過去、映像化されたジョーカーの歴任俳優は、それぞれが最高のパフォーマンスをもって役に臨んできた。ホアキン・フェニックスもその例に漏れず、自らをとことんまで追い込みパラノイアを体現することで、狂気の塊のようなキャラクターからつかみどころを見つけ、握った感触を確実にわがものにしている。
“狂っているのは僕か? それとも世間か???“ ドーランを血に代えた、悲哀を極める悪の誕生を見た後では、ジョーカーへの同情が意識を遮断し、もはやバットマンに肩入れすることなどできない。なんと恐ろしい作品だろう。
シェイプ・オブ・ウォーター(2017)
| 監督 | ギレルモ・デル・トロ |
| 評価 | 3.62 |
解説
『パンズ・ラビリンス』などのギレルモ・デル・トロ監督が異種間の愛を描き、第74回ベネチア国際映画祭で金獅子賞に輝いたファンタジー。米ソ冷戦下のアメリカを舞台に、声を出せない女性が不思議な生き物と心を通わせる。『ハッピー・ゴー・ラッキー』などのサリー・ホーキンスが主演し、『ヘルプ ~心がつなぐストーリー~』などのオクタヴィア・スペンサー、『扉をたたく人』などのリチャード・ジェンキンス、『ドリーム ホーム 99%を操る男たち』などのマイケル・シャノンらが共演。
あらすじ
1962年、米ソ冷戦時代のアメリカで、政府の極秘研究所の清掃員として働く孤独なイライザ(サリー・ホーキンス)は、同僚のゼルダ(オクタヴィア・スペンサー)と共に秘密の実験を目撃する。アマゾンで崇められていたという、人間ではない“彼”の特異な姿に心惹(ひ)かれた彼女は、こっそり“彼”に会いにいくようになる。ところが“彼”は、もうすぐ実験の犠牲になることが決まっており……。
映画レポート
「うつし世は夢 よるの夢こそまこと」とは人外への憧憬を生涯抱えていた江戸川乱歩の箴言だが、その甘美で倒錯的なヴィジョンは映画でいえばジョルジュ・フランジュからティム・バートンに至る幻視者が血脈を受け継いでいるといえよう。そして今、その系譜の最先端にいるのがギレルモ・デル・トロであることは間違いない。
今年のオスカー最有力候補である「シェイプ・オブ・ウォーター」は、フランコ独裁政権下で孤独な少女の非合理な夢想を紡いだ傑作「パンズ・ラビリンス」の寓話世界を1962年、冷戦下のアメリカに置き換え、スケールアップしたような趣きがある。
政府の極秘研究所に務めるイライザ(サリー・ホーキンス)は、アマゾンの奥地から運ばれた“クリーチャー”に惹かれ、恋に落ちる。しかし、冷酷な軍人ストリックランド(マイケル・シャノン)は容赦なく“彼”を虐待し、果ては生体解剖を提案する。一方で、背後では熾烈な宇宙開発競争でしのぎをけずるソ連が暗躍し、イライザは無謀にも“彼”を救出する計画を思いつく――。
口のきけないイライザ、ゲイである隣室の画家ジャイルズ(リチャード・ジェンキンス)、黒人の同僚ゼルダ(オクタヴィア・スペンサー)に象徴される肉体的・精神的な外傷、疎外感を抱えたマイノリティたち、さらに醜貌、畸形的でグロテスクな存在への真情あふれる偏愛は、これまでのデル・トロ作品同様、一貫している。
この映画の霊感源は、デル・トロが幼少期に深く魅せられた「大アマゾンの半魚人」(54)である。奇怪でユーモラスなギルマンの形姿、“美女と野獣”のテーマの変奏と、殆どあからさまなオマージュと言ってもよいが、「大アマゾンの半魚人」がカルト化した最大の理由は水面を泳ぐ美女ジュリー・アダムスの下方を、半魚人が、あたかも性行為のように向き合いながら平行して泳いでゆく妖しくもティックなシーンゆえである。
“水の形態”という原題に即していえば、この映画の際立った魅力もいくつかの水中撮影にある。とくにイライザが、浴槽のある部屋全体を密閉して水で満たし、“彼”と愛の行為にふけるシーンは幻想的でこよなく美しい。
しかし、映画を観終わってもっとも印象に残るのは、残忍きわまりない軍人を演じたマイケル・シャノンである。マチズモの典型のようなこの男の抱える空虚さ、屈辱感、狂気は名状しがたい味わいがある。デル・トロの描くファンタスティックな寓話がつねに童話的な残酷さに満ちているのは、この類いまれな〈悪〉の造型ゆえなのである。
ノマドランド(2020)
| 監督 | クロエ・ジャオ |
| 評価 | 3.80 |
解説
ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション小説を原作に、「ノマド(遊牧民)」と呼ばれる車上生活者の生きざまを描いたロードムービー。金融危機により全てを失いノマドになった女性が、生きる希望を求めて放浪の旅を続ける。オスカー女優フランシス・マクドーマンドが主人公を演じ、『グッドナイト&グッドラック』などのデヴィッド・ストラザーンをはじめ、実際にノマドとして生活する人たちが出演。『ザ・ライダー』などのクロエ・ジャオがメガホンを取り、第77回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で金獅子賞を獲得した。
あらすじ
アメリカ・ネバダ州に暮らす60代の女性ファーン(フランシス・マクドーマンド)は、リーマンショックによる企業の倒産で住み慣れた家を失ってしまう。彼女はキャンピングカーに荷物を積み込み、車上生活をしながら過酷な季節労働の現場を渡り歩くことを余儀なくされる。現代の「ノマド(遊牧民)」として一日一日を必死に乗り越え、その過程で出会うノマドたちと苦楽を共にし、ファーンは広大な西部をさすらう。
映画レポート
放浪生活への憧れは、アメリカの西部開拓時代からの伝統と言えるかもしれない。古くは「野性の呼び声」「マーティン・イーデン」で知られる作家ジャック・ロンドン、50年代には、「路上」でビート・ジェネレーションを代表したジャック・ケルアック、最近では映画「イントゥ・ザ・ワイルド」のモデルで、アラスカで命を落とした青年、クリス・マッキャンドレスがいた。
前作「ザ・ライダー」で、中西部に生きる現代のカウボーイの姿を描いたクロエ・ジャオ監督も、そんな憧れを持つひとりである。
だが、ジェシカ・ブルーダー原作の映画化である「ノマドランド」は、ロマンチックな放浪の夢とは趣を異にする。主人公のファーンは会社の倒産で職を失い、病で夫も亡くした61歳の女性。彼女は致し方なく、愛着のあるぽんこつキャラバンに夫との思い出の品を積み、当てのない旅に出る。生活のため、ところどころで季節労働をするうちに、自分の意志でノマド生活をする「ホームレスではなくハウスレス」な人々と出会い、新しい世界を発見する。
ジャオ監督は前作と同じ手法で、実際のノマドたちを「起用する」というよりは、彼らの生活にとけ込み、その横顔をカメラに収めた。そのなかに混じったフランシス・マクドーマンドもまた、演技ではなく、そこにただ存在し、ノマド生活を営んでいる。その佇まいはフィクションとドキュメンタリーの境界を超え、もはや観る者の先入観も消し去るほど、真実を差し出す。役を生きるとは、こういうことなのだろう。
自分の生き方を貫くことは生易しいことではない。とくにそれが現代社会の慣習に反するようなものなら、なおさらだ。ノマドたちは、「この生活の素晴らしいところは最後の“さよなら”がないから。“また路上で会おう”と言うだけ」と語るが、それはまた、死に際に誰にも看取ってもらえない可能性もあるということだ。否、圧倒的にその確率の方が高い。
だから自ら辺境の人生を選ぶのなら、何があっても後悔しないような覚悟がいる。この映画は、そんなノマド生活の厳しさも十分に掬い取った上で、それでも、そこにある何かかけがえのないロマンを謳いあげる。
ファーンはひとり、静けさに満ちた神秘的な岩山や、激しい風雨の吹き付ける海岸に佇む。ときに神々しい美しさをたたえ、圧倒的な力に満ちた自然の前で、彼女は無力でちっぽけであり同時に、自由で、大地と繋がった存在でもある。
現代におけるノマド生活を通して、人間の生きる意味とは何なのか、といった本質的なテーマに思いを至らせる、それが本作の底知れない力だ。
スリー・ビルボード(2017)
| 監督 | マーティン・マクドナー |
| 評価 | 3.99 |
解説
娘を殺害された母親が警察を批判する看板を設置したことから、予期せぬ事件が起こるクライムサスペンス。本作はベネチア国際映画祭で脚本賞、トロント国際映画祭で観客賞に輝いた。娘を失った母をオスカー女優のフランシス・マクドーマンドが演じ、『メッセンジャー』などのウディ・ハレルソン、『コンフェッション』などのサム・ロックウェルらが共演。ウディやサムも出演した『セブン・サイコパス』などのマーティン・マクドナーがメガホンを取る。
あらすじ
ミズーリ州の田舎町。7か月ほど前に娘を殺されたミルドレッド(フランシス・マクドーマンド)は、犯人を逮捕できない警察に苛立ち、警察を批判する3枚の広告看板を設置する。彼女は、警察署長(ウディ・ハレルソン)を尊敬する彼の部下や町の人々に脅されても、決して屈しなかった。やがて事態は思わぬ方へ動き始め……。
映画レポート
一年のうちに一度か二度、ああ、この映画のことはこれからも繰り返し頭の中を駆け巡るだろうと思える作品に出会う。2018年はまだ1月だというのに「スリー・ビルボード」に出会ってしまった。年末にベスト10を選ぶ時に、早くもひと枠が埋まったようなものだ。
「スリー・ビルボード」は、ミズーリ州エビングという架空の田舎町を舞台にした群像ドラマだ。中心となるのは、娘を何者かに殺された母親ミルドレッドと、住人たちから信頼の厚い警察署長のウェルビー、そして署長の部下で粗野な巡査ディクソン。娘を殺した犯人が捕まらないことに業を煮やしたミルドレッドが、町はずれにある三枚の古い看板に署長を非難する意見広告を出したことから、町全体を揺るがせる騒動が勃発する。
悲劇に見舞われた母親の切なる訴えと、事件の解決に消極的な警察との対立――という構図だが、脚本も手がけたマーティン・マクドナー監督は「世の中はそんな風に白黒つけられるものではない」と言わんばかりに観客の早合点をひとつひとつ裏切っていく。ぶつかるべき敵役かと思われたウェルビー署長は誠実な人格者だし、ミルドレッドのゴリ押しは無責任に波風を立てているだけにも思えてくる。
途中で犯人捜しのミステリーに向かうかのように思えるが、それもスッと梯子を外されてしまう。最も憎まれ役であるはずのディクソンさえ、環境によって偏見と暴力性を育まれた弱き者でしかない。気がつけば、姿を見せない犯人以外に誰も悪人などいないのに、なぜいがみ合わなければいけないのかと不毛さばかりが浮かび上がる。
いや、この映画の凄さは、現実の世の中は、そしてわれわれ一人一人の人生など所詮不毛なのではないかという疑念を容赦なく追及しながら、そこにもまた、可笑しさや愛でるべきものがあるのではないかと思わせてくれること。正直、本作をジャンル分けすることは不可能だ。悲劇と喜劇、悲哀と笑いが常に背中合わせで、いつどちらの顔を見せるのかわからないという点で「スリー・ビルボード」は昨年の賞レースを賑わせた「マンチェスター・バイ・ザ・シー」と共通する視点を持っていると言える。
とりわけミルドレッドとディクソンは、日本人的な和を尊ぶ感性からすれば我が強すぎて空気を読まない問題人物だが、あらんかぎりの力で壁にぶつかっていく不器用で正直な生き様を見ているうちに、われわれ観客も共に全力で迷うべきだという確信さえ生まれてくるのである。
グッドフェローズ(1990)
| 監督 | マーティン・スコセッシ |
| 評価 | 3.89 |
解説
実在の人物をモデルに、少年の頃からギャングに憧れ、その仲間入りを果たした一人の男の波瀾に満ちた半生を、主人公のモノローグを織り込みながら描いた犯罪ドラマ。
桃(タオ)さんのしあわせ(2011)
| 監督 | アン・ホイ |
| 評価 | 4.13 |
解説
『女人、四十。』などで知られるアン・ホイ監督が、老いをテーマにつづる感動の人間ドラマ。いつも空気のようにそばにいた老メイドが病に倒れたことをきっかけに、やがて肉親以上の強い絆で結ばれていく主従の関係を描き切る。『サイクロンZ』などの演技派女優ディニー・イップが昔気質の使用人を演じ、介護に奔走する主人公を、香港の大スターアンディ・ラウが熱演する。ユーモアと優しさを交えて描かれる人生の転機に勇気をもらう。
あらすじ
広東省生まれの桃さん(ディニー・イップ)は、13歳から60年もの間梁家の使用人として4世代の家族の世話をしてきた。今は、生まれたときから面倒を見てきたロジャー(アンディ・ラウ)が彼女の雇い主で、彼は映画プロデューサーとして中国本土と香港を往復する多忙な日々を送っていた。そんなある日、桃さんが脳卒中を起こして倒れ……。
雨あがる(1999)
| 監督 | 小泉堯史 |
| 評価 | 3.77 |
解説
故・黒澤明監督が山本周五郎の短編をもとに書いた遺稿を、黒澤組のスタッフたちが映画化。剣の達人でありながら人の良さが災いし、思うように仕官になれない浪人をユーモラスに描く。堅苦しくなく、見終わった後に爽快な気分になれる良質の時代劇。お人好しの浪人を寺尾聰が好演。宮崎美子、三船史郎、吉岡秀隆、原田美枝子、仲代達矢共演。享保の時代。浪人の三沢伊兵衛とその妻は、長雨のため安宿に居を構えた。ある日、若侍の諍いを難なく仲裁した三沢は、通りかかった藩主・永井和泉守に見そめられ城に招かれる。三沢が剣豪であることを知った和泉守は、彼を藩の剣術指南番に迎えようとするが…。
ラ・ラ・ランド(2016)
| 監督 | デイミアン・チャゼル |
| 評価 | 4.10 |
解説
『セッション』などのデイミアン・チャゼルが監督と脚本を務めたラブストーリー。女優の卵とジャズピアニストの恋のてん末を、華麗な音楽とダンスで表現する。『ブルーバレンタイン』などのライアン・ゴズリングと『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』などのエマ・ストーンをはじめ、『セッション』でチャゼル監督とタッグを組んで鬼教師を怪演したJ・K・シモンズが出演。クラシカルかつロマンチックな物語にうっとりする。
あらすじ
何度もオーディションに落ちてすっかりへこんでいた女優志望の卵ミア(エマ・ストーン)は、ピアノの音色に導かれるようにジャズバーに入る。そこでピアニストのセバスチャン(ライアン・ゴズリング)と出会うが、そのいきさつは最悪なものだった。ある日、ミアはプールサイドで不機嫌そうに1980年代のポップスを演奏をするセバスチャンと再会し……。
映画レポート
ハイウェイの渋滞に業を煮やした人々が踊り出すプロローグのダイナミックなミュージカルシーンは、運搬橋を舞台にキャラバン隊が踊る「ロシュフォールの恋人たち」を連想させる。一方、エピローグで恋人たちの数年後に話が飛ぶところは、「シェルブールの雨傘」を思わせる。ジャック・ドゥミ監督のミュージカル映画へのオマージュがブックエンドをなす「ラ・ラ・ランド」には、他にも「バンド・ワゴン」のエレガントな公園のダンスから「世界中がアイ・ラヴ・ユー」の空中浮遊まで、新旧ミュージカル映画のエッセンスが詰め込まれている。が、デイミアン・チャゼル監督の本領はそうした引用のうまさではなく、リアルな描写からファンタジーへとミュージカルシーンをなめらかに昇華させるテクニックを心得ていることだろう。恐るべき32歳だ。
ミュージカル映画定番の「芸能界の内幕物」に属するストーリーも魅力だ。女優志望のミア(エマ・ストーン)と売れないジャズマンのセブ(ライアン・ゴズリング)が繰り広げる愛らしいラブストーリーには、2種類の悲哀が宿っている。ひとつはアーティストの悲哀。生活のために売れ線のバンドに加わるセブと、才能の限界を感じるミア。妥協を突きつけられる2人の揺れる心情が切なさをかきたてる。もうひとつは恋愛の悲哀。人生の浮き沈みのタイミングのすれ違いが恋愛の行方を微妙に左右する設定は、ハラハラさせると同時に胸をキュンとしめつける。
この2種の悲哀が絡み合ってドラマを生む構成は「ニューヨーク・ニューヨーク」と同じだが、主人公を見守りたいと思わせる共感度の高さは「ラ・ラ・ランド」が勝っている。それがラストで生きる。かなった夢とかなわなかった夢、逃した幸福とつかんだ幸福。誰もが経験するであろう人生の忘れ物が走馬燈のようにかけめぐる至福の15分間。これを見たら、インスピレーションの元になった「巴里のアメリカ人」のビンセント・ミネリ監督も誇りに思うに違いない。
オアシス(2002)
| 監督 | イ・チャンドン |
| 評価 | 4.21 |
解説
世界的に高く評価された『ペパーミント・キャンディー』のイ・チャンドン監督が、演技派のソル・ギョングと同作で見い出した女優、ムン・ソリと再び組んだ、社会から疎外された男女の愛の物語。本作で肉体的にも精神的にも辛い役を見事に演じ、ベネチア国際映画祭新人俳優賞に輝いたムンと、最優秀監督賞を受賞した監督は韓国を代表する顔になった。現実とファンタジーのバランスも絶妙な究極の愛の姿に、しばし現実を忘れる。
あらすじ
前科三犯のジョンドゥ(ソル・ギョング)は、出所後自分がひき逃げした被害者の家族に謝罪に行き、重度脳性麻痺のコンジュ(ムン・ソリ)と出会う。2人は秘かに愛を育んでいくが、周りはそれを許さない。
映画レポート
Netflixで配信中の韓国ドラマ「愛の不時着」や「梨泰院クラス」などが人気だ。2003年から日本で社会現象を巻き起こしたドラマ「冬のソナタ」から数えて、日本における“第4次”韓流ブームが来ていると言われている。韓国のドラマや映画には常に刺激を受け、そのクオリティの高さに嫉妬してきた。
1999年あたりから、特に2000年代に入ってからの韓国映画の勢いは凄まじく、パク・チャヌク、ポン・ジュノら新しい才能が、「JSA」(2000)、「殺人の追憶」(2003)といった数々の秀作、傑作を生みだした。国際的にも高く評価され、日本でもミニシアター系で公開されて熱狂的なファンを獲得してきた。
そんな流れの初期、日本では2004年に公開されたイ・チャンドン監督の「オアシス」(2002)は、恋愛映画の概念を覆すような、詩的でありながら破壊力を持った作品だ。ソル・ギョングが演じる社会に適応できない青年と、ムン・ソリが演じる脳性麻痺の女性の極限の純愛を描き、第59回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(最優秀監督賞)、ソリがマルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞した。
まず、主演ふたりの演技に驚愕することだろう。ギョングが演じる刑務所から出所したばかりの青年ジョンドゥは、落ち着きがなく、周囲をイラつかせる。29歳ながら子供のように無邪気で、家族からも煙たがられてしまう。ソリが演じる脳性麻痺のコンジュは、白いハトや蝶々が飛んでいるように見える部屋で、壁にかけられた異国の絵を眺め、ラジオを聴いてひとり夢想していた。そんな社会から厄介者扱いされていた二人が出会い、彼らなりの愛を育んでいく姿に心打たれる。ギョングもソリもこの難役を「生きている」ようにしか見えない。チャンドン監督の名作「ペパーミント・キャンディー」(1999)でも共演しているが、同じ役者だとは気づかないかもしれない。
そして、脚本も手掛けているチャンドン監督の演出には唸らされる。障がい者を扱ったデリケートな物語であるが、二人の純愛を極限まで描き切ることで、映画的なファンタジー、もしくはコメディの領域にまで高めてしまう。車椅子の上で自由に動けずにいたコンジュを映していたカメラがパンしてジョンドゥを映していると、コンジュが健常者の姿になってフレームインし、普通のカップルのようにじゃれ合うシーンなどは秀逸だ。現実と幻想の境界線を軽やかに越え、交じり合わせてしまう映画表現には胸が熱くなるし、改めて映画の力を感じる。コンジュの部屋の絵が再現されるシーンも、愛し合う二人だけが見ることができる世界なのだろう。
元教師で小説家でもあるチャンドン監督は、韓国社会の片隅でもがき苦しみながらも純粋に、必死に生きようとする人間を、独自の視点で描き続けている。「オアシス」には、実際にはあり得ない表現もあるのかもしれない。でも、もしかしたら二人の刹那で純粋な願望や幻想の世界を垣間見ただけなのかもしれないと思わせてくれる余韻が残る。韓流ドラマやK-POPのブームとはまた違った側面で、韓国映画が成し遂げてきた功績は非常に大きく、その底力を痛感することができる一本だ。
永遠の門 ゴッホの見た未来(2018)
| 監督 | ジュリアン・シュナーベル |
| 評価 | 3.34 |
解説
『潜水服は蝶の夢を見る』などのジュリアン・シュナーベル監督が、画家フィンセント・ファン・ゴッホの人生を描く伝記ドラマ。ゴッホを『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』などのウィレム・デフォーが演じ、第75回ベネチア国際映画祭最優秀男優賞を受賞。『インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌』などのオスカー・アイザックのほか、『偽りなき者』などのマッツ・ミケルセン、監督としても活動しているマチュー・アマルリックらが共演する。
あらすじ
人付き合いができないフィンセント・ファン・ゴッホ(ウィレム・デフォー)は、いつも孤独だった。唯一才能を認め合ったゴーギャンとの共同生活も、ゴッホの行動により破たんしてしまう。しかし、ゴッホは絵を描き続け、後に名画といわれる数々の作品を残す。
映画レポート
自身も現代美術のアーティストであるジュリアン・シュナーベル監督が、画家を主人公にした映画を発表するのは、デビュー作の「バスキア」に続いて二度目だ。「バスキア」は、NYアート界の商業化の波にもまれて疲弊していくバスキアの無垢な魂に光を当てていた。対して「永遠の門」は、ゴッホの目にこの世界がどう映っていたかを観客に体感させる映画になっている。
ゴーギャンのアドバイスに従って南仏へ移住したゴッホが、初めて絵筆をとる場面が印象深い。無造作に脱ぎ捨てた靴がゴッホの脳内で瞬時に構図を得て絵画のモチーフになる過程が、靴のクローズアップの画角の変化で表現される。ここから先の映像は、風景も静物も、色彩もアングルも、ゴッホの感受性というフィルターを通したものであると予告する演出だ。実際、その映像は豊かで美しい。糸杉は風をはらみ、黒い雲はうねり、麦畑はオレンジ色に輝く。ゴッホが対象物のどの部分に意識を集中させているかを表すために、映像の半分が接写、半分がノーマルに映し出されるレンズ(スプリット・ディオプター)も使われる。シュナーベル監督は、どこまでもわかりやすくゴッホの視点を解説してくれる。
それだけじゃない。シュナーベル監督は、「なぜ絵を描くのか?」という画家の命題を、ゴーギャン(オスカー・アイザック)、聖職者(マッツ・ミケルセン)、2人の医師(ウラジミール・コンシニ&マチュー・アマルリック)との対話を通してゴッホに語らせている。芸術的、宗教的、心理学的な観点から理路整然となされるゴッホの自己分析は、説明が過ぎる感じがしなくもないのだが。
ウィレム・デフォーのゴッホは、知的で繊細で孤独で、人や酒に依存しなければ生きられない弱さを抱えている。が、この映画で最も強調される性格は、伝道師としての使命感だ。神なる自然の中に宿る美を解放し、永遠の命を宿す絵画に変え、人々に知らしめる。その使命を果たすために自分は存在するのだという揺るぎない信念を、デフォーの青い瞳は湛えている。それを見て気づかされる。「バスキア」と同じく、やはりこれも画家の魂の映画なのだ、と。
スパイの妻<劇場版>(2020)
| 監督 | 黒沢清 |
| 評価 | 3.43 |
解説
『トウキョウソナタ』『岸辺の旅』などの黒沢清監督によるドラマの劇場版。太平洋戦争前夜を背景に、運命によってもてあそばれる夫婦の試練を描き出す。蒼井優と高橋一生が『ロマンスドール』に続いて夫婦にふんし、『犬鳴村』などの坂東龍汰や、『コンフィデンスマン JP』シリーズなどの東出昌大らが共演。『寝ても覚めても』などの濱口竜介監督と、濱口監督の『ハッピーアワー』などの脚本を担当した野原位が、黒沢監督と共に脚本を手掛ける。
あらすじ
1940年、神戸で貿易会社を経営する優作(高橋一生)は満州に渡り、偶然恐ろしい国家機密を知る。正義のために一連の出来事を明るみに出そうとした彼は、反逆者とみなされてしまう。優作の妻の聡子(蒼井優)は反逆者と疑いの目で見られる夫を信じ、スパイの妻とそしりを受けても、愛する夫と手に手を取って生きていこうと決意する。
映画レポート
これまで黒沢清監督の映画を見るたびに、その独特な世界の見方と映画の文体に驚きと感銘を受けてきた一人として、第77回ベネチア国際映画祭での銀獅子賞(監督賞)受賞のニュースは感慨深いものがあった。そして、コンペティション部門に出品されたその映画「スパイの妻」は、いったいどんな作品なのかとこれまで以上に期待は高まった。
「スパイの妻」は、元々は今年6月にNHK BS8Kで放送された同名ドラマを、劇場版としてスクリーンサイズや色調を新たにし、1本に再編集したもの。物語の舞台は太平洋戦争前夜、1940年の日本。相反するものに揺さぶられながら、抗えない時勢にのまれていく夫婦の愛と正義を賭けた様を描く。ロケ地、衣裳、美術、台詞まわし、すべてにこだわったというだけに一級のミステリーエンターテインメントに仕上がっている。これまで黒沢監督が手掛けてきたものとは一線を画すようなテーマ、物語とも言え、8K・スーパーハイビジョン(超高解像度のテレビ規格)撮影によるその映像表現には舌を巻いた。
振り返れば黒沢監督は、過去にもホラーやサスペンスといった要素は根底に残しながら、それまで得意としてきたジャンルとは異なる新しい映画作りに取り組んで新境地を広げてきた。例えば、1990年代末から2000年代にかけて、「CURE」や「トウキョウソナタ」などのインディペンデント作品で、刑事もの、家族や恋愛のドラマというジャンルの中で独自の死生観と黒沢節とも言える演出、映像と音で映画世界を構築し、国内外で高い評価を得た。2010年代に入ると「リアル 完全なる首長竜の日」などメジャー作品や、「ダゲレオタイプの女」など海外での撮影や国際共同製作も手掛けている。
そういったキャリアを経て取り組んだ「スパイの妻」は、黒沢監督が最新の8K・スーパーハイビジョン撮影で初めて挑んだ歴史ものである。脚本には「寝ても覚めても」の濱口竜介、「ハッピーアワー」の野原位と海外で評価された才能が参加し、音楽は「ペトロールズ」「東京事変」で活躍するミュージシャンの長岡亮介が手掛け、黒沢監督よりも若い世代との化学反応を起こしている。そして、美術の安宅紀史、衣裳の纐纈春樹が再現した昭和初期の世界観も見どころのひとつだ。
主演は、テレビドラマ「贖罪」、映画「岸辺の旅」で黒沢組に参加している蒼井優。「ロマンスドール」に続いて高橋一生が蒼井と夫婦役を演じ、ふたりの心情の変化を繊細に表現。憲兵の分隊長を演じた東出昌大とともに確かな存在感で監督の演出に応えている。
黒沢監督は最初から劇場公開も視野に入れて、映画として作り上げていることがうかがえる。スパイものというジャンルの枠組みのなか、超高解像度の撮影でどこまで登場人物の心情を表現できるのか、光と影(闇)を意識し、これまで以上にあえてクラシカルで様式的なリズムに則った演出は必見である。
ポネット(1996)
| 監督 | ジャック・ドワイヨン |
| 評価 | 3.57 |
解説
4歳の主演少女ヴィクトワール・ティヴィソルが、96年のヴェネチア映画祭で女優賞を受賞した感動作。愛する母親の死に直面した4歳の少女が、死と向かい合いながら乗り越えてゆくまでを温かい眼差しで描く。史上最年少で受賞した、ティヴィソルの純朴な演技は絶品。事故で亡くなってしまった母親を、ひとり待ち続ける少女ポネット。そんな彼女を見た周囲の大人達は、彼女に死の意味を教えるが、ポネットは逆に自分の世界に閉じこもってしまう。そんな時、彼女の前にある“奇跡”が訪れるが……。
ブラック・スワン(2010)
| 監督 | ダーレン・アロノフスキー |
| 評価 | 3.95 |
解説
『レスラー』のダーレン・アロノフスキー監督と、『スター・ウォーズ』シリーズのナタリー・ポートマンがタッグを組んだ心理スリラー。内気なバレリーナが大役に抜てきされたプレッシャーから少しずつ心のバランスを崩していく様子を描く。芸術監督を演じるのは、フランスを代表する俳優ヴァンサン・カッセル。主人公のライバルを、『マックス・ペイン』のミラ・クニスが熱演する。プロ顔負けのダンスシーン同様、緻密(ちみつ)な心理描写に驚嘆する。
あらすじ
ニューヨーク・シティ・バレエ団に所属するバレリーナ、ニナ(ナタリー・ポートマン)は、踊りは完ぺきで優等生のような女性。芸術監督のトーマス(ヴァンサン・カッセル)は、花形のベス(ウィノナ・ライダー)を降板させ、新しい振り付けで新シーズンの「白鳥の湖」公演を行うことを決定する。そしてニナが次のプリマ・バレリーナに抜てきされるが、気品あふれる白鳥は心配ないものの、狡猾(こうかつ)で官能的な黒鳥を演じることに不安があり……。
映画レポート
話の枠はバレエだ。ニナ(ナタリー・ポートマン)というダンサーが苦悩する映画だ。ただし彼女は、芸術を取るか人生を取るかという古典的命題をめぐって苦しむのではない。「赤い靴」とはそこがちがう。
私はむしろ、別の映画を連想した。「イヴの総て」と「何がジェーンに起ったか?」の2本。わけても近いのは後者だ。
「ジェーン」はサイコパスの映画だった。動けない姉と狂った妹の百年戦争。光と影の落差が激しい画面で、メロドラマとスリラーとゴシック・ホラーが入り混じる。おや、この構造は「ブラック・スワン」と似ていないか。
「ブラック・スワン」に姉妹は出てこない。が、ニナを取り巻く女たちは、彼女の天敵であるとともに彼女の分身だ。競争相手のリリー、過保護で過干渉の母親エリカ、もと花形のベス。そしてだれよりも、ニナはニナ自身に苦しめられる。白鳥は踊れても黒鳥を踊れないニナ。踊るためには、自身のデーモンを解き放ってやる必要がある。だが、そんなことが簡単にできるのか。そもそも、彼女にはデーモンが備わっているのだろうか。
監督のダーレン・アロノフスキーは、ここで一気に負荷をかける。オーバーロード、オーバードライブ、オーバー・ザ・トップ。似たような言葉が私の脳裡で一斉に明滅する。同時に映画のテンションも急激に高まる。現実と妄想の境界線は溶け合い、映画は強力な薬物のように観客の脳髄に侵入する。
ここが「ブラック・スワン」の勇敢なところだ。いや、勇敢というより無謀に近い大胆さか。「赤い靴」が追求した二元論はすでに吹き飛ばされている。ニナは、芸術と人生を串刺しにして……いや自分自身をも突き貫いて、世界の中心に迫っていく。その激痛、その覚醒は観客にも感染する。これは、映画が豪華な悪夢になりうることを証明した作品だ。
ブロークバック・マウンテン(2005)
| 監督 | アン・リー |
| 評価 | 4.02 |
解説
保守的なアメリカの西部で、20年以上にも渡って男同士の愛を貫いた2人の“普遍の愛”を描く人間ドラマ。2005年のヴェネチア国際映画祭で最高賞の金獅子賞を受賞したほか、数々の映画賞にノミネートされている話題作。主演はヒース・レジャーとジェイク・ギレンホールが20歳から40歳までの年齢も繊細に表現した演技を見せる。監督は『グリーン・ディスティニー』のアン・リー。ブロークバックの山々を美しく映し出した映像にも注目。
あらすじ
1963年の夏。ワイオミング州のブロークバック・マウンテンでイニス(ヒース・レジャー)は羊番の仕事を始める。たまたま一緒に組んで仕事をしていたジャック(ジェイク・ギレンホール)との間に友情が芽生えるが……。
映画レポート
「女性が書いたとは思えないほどタフでワイルドですが、読み終わると涙を流していました」と監督アン・リーは、この映画の原作であるE・アニー・プルーの短編について述懐する。その後、大作「グリーン・デスティニー」と「ハルク」に取り組み、精も根も尽き果てた彼が結局、立ち戻ったのがこの物語。険しい山を越えた果てに新たな地平が開けたような、驚くべきマスターピースだ。
羊番の仕事でワイオミングの山にこもった2人の青年は、自分たちにも理解できないパッション(熱情)に突き動かされ、果実を味わってしまう。その味が忘れられず、2人は互いに結婚して子供をもうけても秘かに交流を続ける。だがその代償として、もうひとつのパッション(受難)が待ち受けていた……。
「ブローク(破損)バック(背)」という名の山での、つかのまの牧歌的生活。それが2人にとっての「楽園」だったことに、失って初めて気づく痛み。その意味で、これは男2人の「失楽園」といえるのかもしれない。神話や伝説とはおよそ縁のない、武骨な西部の男を通して語られる普遍的なラブストーリー。ヒース・レジャーの寡黙さに、原罪を「背負った」人間の悲しみがある。
ヒミズ(2011)
| 監督 | 園子温 |
| 評価 | 3.39 |
解説
『恋の罪』などの鬼才園子温が監督を務め、古谷実原作の人気漫画を映画化した衝撃作。ごく平凡な15歳の少年と少女の運命が、ある事件をきっかけに激変する過程を園監督ならではの手法で描き出す。主人公に『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』の染谷将太、ヒロインに『劇場版 神聖かまってちゃん/ロックンロールは鳴り止まないっ』の二階堂ふみら若手実力派を起用。自身も原作のファンだという園監督が創造する新たなる人間の心の闇から目が離せない。
あらすじ
どこにでもいる中学3年生の祐一(染谷将太)の夢は、成長してごく当たり前のまっとうな大人になること。一方、同い年の景子(二階堂ふみ)の夢は、自分が愛する人と支え合いながら人生を歩んでいくことだった。しかしある日、2人の人生を狂わせる大事件が起き……。
映画レポート
若者の暴れる映画に、私は点が辛い。素材が手に入れやすく、調理に手間をかける必要がなく、客の味覚にも訴えやすいからだ。つまり俗耳に受け入れられやすいわけで、そんなものはおいそれと褒めるわけにいかない。
もちろん、例外はある。「仁義なき戦い」や「勝手にしやがれ」や「青春残酷物語」などは魅力的な映画だった。エネルギーにあふれているだけでなく、スタイルやデリカシーも忘れなかったからだ。逆にいえば、火入れと盛り付けに心を砕けば、乱暴な若者の映画もけっして退屈にはならない。さらに、素材が選び抜かれていれば、レベルは一段上がる。
「ヒミズ」は、このハードルに挑んでいた。
なによりも、染谷将太という素材がみずみずしい。彼の演じる住田祐一という15歳の少年はなかなか面白い動物だ。住田は「立派な大人」になろうとしている。親がクズで、愛情の注ぎ方を知らなかったからだ。彼は怒る。彼は苦しむ。彼は暴れる。彼は叫ぶ。
「俺はたまたまクズのメスとオスの間に生まれただけだ。だがな、俺はおめえらみたいなクズじゃないんだ。見てろ、俺の未来はだれにも変えられねえんだ」
こんなに単細胞な科白を口にしても、住田は観客の胸を打つ。がんばれ住田、負けるな住田という気持を湧き上がらせてくれる。これは稀有だ。監督の園子温も、開き直ったような直球をずばずばと投げ込んでくる。その球がときどきナチュラルなシュート回転をして、観客の胸もとに食い込んでくる。
ここも急所だ。くりかえし挿入されるモーツァルトの「レクイエム」とバーバーの「弦楽のためのアダージョ」の一節が、料理の盛り付けに使われて効果を上げる。惜しむらくは、絶望と自暴自棄を突き抜けた先の笑いがいまひとつ足りなかったことだが、贅沢はいうまい。「ヒミズ」はけっこうハートに来る。私も昔、少しだけ住田だった。
嘆きのピエタ(2012)
| 監督 | キム・ギドク |
| 評価 | 3.72 |
解説
独創的な作風で世界中から注目を浴びる韓国の鬼才キム・ギドク監督による、第69回ベネチア国際映画祭金獅子賞に輝いた問題作。昔ながらの町工場が並ぶソウルの清渓川周辺を舞台に、天涯孤独に生きてきた借金取りの男の前に突如母親と名乗る女性が現われ、生まれて初めて母の愛を知った男の運命を描き出す。主演はテレビドラマ「愛してる、泣かないで」のイ・ジョンジンと、ベテラン女優チョ・ミンス。二人の気迫に満ちた演技と、観る者の予想を超えたストーリー展開に圧倒される。
あらすじ
身寄りもなく、ずっと一人で生きてきたイ・ガンド(イ・ジョンジン)は、極悪非道な借金取り立て屋として債務者たちから恐れられていた。そんな彼の前に母親だと名乗る女性(チョ・ミンス)が突如現われ、当初は疑念を抱くガンドだったが、女性から注がれる愛情に次第に心を開いていく。生まれて初めて母の愛を知った彼が取り立て屋から足を洗おうとした矢先、女性の行方がわからなくなってしまい……。
映画レポート
舞台は経営難の町工場がひしめく町。主人公のガンド(イ・ジョンジン)は弱者を食い物にして生きている。孤児の彼には、それしか生きる術がなかったからだ。そんな悪業にまみれた主人公の「どうしようもなさ」を、キム・ギドク監督は見事にすくいとる。「悪い男」や「春夏秋冬そして春」で発揮された人間描写の個性は健在だ。
拝金主義の弱肉強食社会で、債務者という獲物を貪欲に狩るガンドの獣性を、キム監督は食事の儀式に象徴させる。ピエタ(キリストの亡骸を抱く聖母マリア)という題名の宗教性にならって言えば、ガンドが食事用の動物をさばく浴室にはホロコーストの匂いが充満している。床を濡らす血と肉のイメージが鮮烈だ。
そんなガンドの前に母と名乗る女が現れたことから、ドラマが動き出す。ガンドに「失うことへの恐怖」を味わわせる母の存在は、彼の中で眠っていた人間性を呼び覚ます。そして、あらわになった母の真実は、より残酷な第2のめざめへと彼を導いていく。
このシンプルな覚醒の物語は、フェリーニの「道」を想起させる。「道」が野蛮なザンパノと無垢なジェルソミーナの双方の魂の覚醒を描いたように、この映画もガンドと母の2人の覚醒をみつめているからだ。ガンドの覚醒の触媒の役目を果たす母親は、自身も「息子を愛する母」以外の何者でもないことにめざめる。が、それがガンドに伝わることはない。2人の心が永遠にすれ違ったまま放置される無情さが、胸をしめつける。
さらに、劇の最後にはこんな問いかけも放たれる。金に始まり金に終わる世の中で救いは得られるのか? と。その問いは、好景気の幻想に浮かれる我々の胸にも「覚醒」の2文字を喚起するのだ。
コメント
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です。
関連記事
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】ivfree.asiaは安全?視聴方法や代わりサイトまで一気にご紹介!
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】カリビアンコムのダウンロード廃止?今なら使えるカリビアンコム動画のダウンロード方法!
- Aoi / 2023-12-26【高品質かつ安全】Supjavからアダルト動画をダウンロードする方法
- Aoi / 2023-12-21【23年最新】Avgle ダウンロードの裏技を公開!簡単に高画質動画を入手~Android・iPhone/iPad・PC全環境対応
- Aoi / 2023-11-30av4.usが閉鎖!?代わりの無料アダルト動画サイトをまとめ
- Aoi / 2023-11-29【無料】TokyoMotionダウンロードする方法、その操作手順まで詳しくご紹介!(PC&スマホ)
最新記事 人気記事
Kira / 2024-09-24
【無料】ディズニー動画ダウンロード方法おすすめ|ディズニー+から映画を保存してオフラインで視聴しよう
Kira / 2024-09-24
SwitchでHuluは見れません!その理由と今後の動向を予想して裏技まで紹介します
Melody / 2024-09-24
【2023年】Huluを録画する方法!裏ワザ?真っ黒にならないソフトを紹介します
Kira / 2024-09-24
AbemaTVをダウンロード&録画できるツール7選!DRM解除できるものだけを厳選
HANA / 2024-09-24
【ABEMA ダウンロード】ABEMA(旧AbemaTV)動画をダウンロードする方法、ダウンロードできない原因と対策
youjinkin / 2024-09-24
U-NEXTで鑑賞できるおすすめアニメ作品TOP 20
Kira / 2024-09-24
U-NEXTがダウンロードできるツールトップ7!録画ソフトも
Melody / 2024-09-24
【完全保存版】U-NEXTのダウンロード方法!できない時の原因と解決法も
Tetsuko / 2024-09-24
StreamFab myFansダウンローダーの機能や使い方、評判をレビューして徹底解説!
Tetsuko / 2024-05-09
Missavの無料エロ動画をダウンロードするツール5選
展開 ∨ 折りたたみ ∧
ホットトピックス

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次
Copyright © 2024 entametalk.jp All Rights Reserved.
年齢認証

あなたは18歳以上ですか?
エンタメTALKはアダルトコンテンツを含みますので、18歳未満の方の閲覧を固くお断りいたします。
いいえ はい