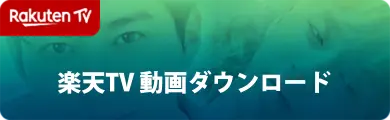StreamFab 動画 ダウンローダー
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次>
プライベート・ライアン(1998)
| 監督 | スティーヴン・スピルバーグ |
| 評価 | 4.18 |
解説
1944年6月。ノルマンディ上陸作戦は成功に終わったものの、激戦に次ぐ激戦は多くの死傷者を出していた。そんな中、オマハビーチでの攻防を生き延びたミラー大尉に、落下傘兵ライアン二等兵を戦場から救出せよという命令が下された。彼には3人の兄がいたが、全員が死亡。兄弟全てを戦死させる訳に行かないと考えた軍上層部の決定であった。ミラーは中隊から7人の兵士を選び出し、生死も定かでないライアン二等兵を探すために戦場へと出発するのだが……。
羊たちの沈黙(1991)
| 監督 | ジョナサン・デミ |
| 評価 | 4.28 |
解説
若い女性を殺害しその皮を剥ぐという猟奇事件が続発。捜査に行きづまったFBIは、元精神科医の殺人鬼ハンニバル・レクターに示唆を受けようとする。訓練生ながらその任に選ばれたクラリスは獄中のレクターに接触する。レクターはクラリスが、自分の過去を話すという条件付きで、事件究明に協力するが……。トマス・ハリスの同名ベストセラーを完全映画化したサイコ・スリラー。アカデミー賞の作品・監督・主演女優・主演男優賞といった主要部門を独占。
パラサイト 半地下の家族(2019)
| 監督 | ポン・ジュノ |
| 評価 | 4.04 |
解説
『母なる証明』などのポン・ジュノが監督を務め、第72回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した人間ドラマ。裕福な家族と貧しい家族の出会いから始まる物語を描く。ポン・ジュノ監督作『グエムル -漢江の怪物-』などのソン・ガンホをはじめ、『新感染 ファイナル・エクスプレス』などのチェ・ウシク、『最後まで行く』などのイ・ソンギュンらが出演。
あらすじ
半地下住宅に住むキム一家は全員失業中で、日々の暮らしに困窮していた。ある日、たまたま長男のギウ(チェ・ウシク)が家庭教師の面接のため、IT企業のCEOを務めるパク氏の豪邸を訪ね、兄に続いて妹のギジョン(パク・ソダム)もその家に足を踏み入れる。
映画レポート
世界共通の社会問題である“貧富の格差”は、映画界においても多くの著名監督たちがそれぞれの切り口で追求しているテーマだ。カンヌ国際映画祭パルムドールに輝き、全米賞レースでも猛烈な勢いで外国語映画賞を総なめにしている「パラサイト 半地下の家族」は、おそらく映画史上最も鮮烈に“格差”の視覚化に成功した作品だろう。
全員失業中のキム一家は、日当たりが悪く不衛生で、WiFiの電波もろくに届かない半地下住宅で暮らしている。一方、高台の豪邸に住んでいるIT社長のパク一家は、勝ち組を絵に描いたような大富豪。キム家の息子が身分を詐称してパク家の娘の家庭教師になったことをきっかけに、ふたつの家族の人生が交錯していくという物語だ。両家の途方もない格差を象徴する“家”のデザインにこだわったポン・ジュノ監督は、思うがままのカメラワークを駆使した空間演出のタクトをふるうべく、このふたつの主要舞台の大規模なオープンセットを建造して撮影を行った。
悪意なき貧乏人であるキム一家には、パク一家への恨みなど一切ない。手荒い手段で財産を奪う“侵略”ではなく、密かにまとわりついて幸せという名の養分を吸い取る“寄生”が彼らの狙いだ。「パラサイト」とは、何とうまく的を射たタイトルだろう。ユーモアとサスペンスを変幻自在に操るポン監督は、中盤の意外なほど早いタイミングで達成されるパク一家のパラサイト計画のプロセスを、痛快なブラック・コメディに仕立ててみせた。
壮大などんでん返しが待ち受けるその後の展開はジャンルもトーンも一変し、クライマックスに向かって怒濤のスペクタクルが炸裂する。ポン監督のさらなる格差の視覚化を成す重要なエッセンスは“雨”と“階段”だ。もしも災害レベルの豪雨が降ったら、半地下住宅と高台の豪邸のどちらが甚大な被害を被るかは一目瞭然。そして極めて映画的な装置である階段は、本作に隠されたもうひとつの階層の存在をあぶり出すシークエンスで絶大な威力を発揮する。その暗黒の異界への扉が開かれた瞬間、寄生する者とされる者の構図は激しくねじ曲がり、パラサイト計画の行く末は予測不能のカオスと化していく。
そのほか“桃”や“体臭”などポン監督の尋常ならざるディテール描写が冴えるモチーフはいくつもあるが、娯楽性満点の本作のエンディングは決して爽快ではない。格差というものの恐ろしい断絶の視覚化までも試みたこの映画は、ほの暗い複雑な余韻となって、鑑賞後も私たち観客の心にパラサイトしてくるのだ。
リメンバー・ミー(2017)
| 監督 | リー・アンクリッチ |
| 評価 | 4.36 |
解説
1年に1度だけ他界した家族と再会できるとされる祝祭をテーマにした、ディズニー/ピクサーによる長編アニメ。死者の国に足を踏み入れた少年が、笑いと感動の冒険を繰り広げる。監督と製作には、『トイ・ストーリー3』のリー・アンクリッチ監督と、製作を担当したダーラ・K・アンダーソンが再び集結。テーマパークのような死者の国の描写、祖先や家族を尊ぶ物語に引き込まれる。
あらすじ
過去の出来事が原因で、家族ともども音楽を禁止されている少年ミゲル。ある日、先祖が家族に会いにくるという死者の日に開催される音楽コンテストに出ることを決める。伝説的ミュージシャンであるデラクルスの霊廟に飾られたギターを手にして出場するが、それを弾いた瞬間にミゲルは死者の国に迷い込んでしまう。元の世界に戻れずに困っていると、ヘクターという謎めいたガイコツが現れ……。
映画レポート
子供の頃、夜の暗闇が怖かったし、限りある命という言葉に気が重くなった。そして何よりも、人が死んだらどこに行くのか、想像するだけで夜眠れなくなった。もしもあの時の自分がこんなワンダフルでマーベラスな映画と出会っていれば、一体どれほど楽になれただろう。ピクサーが「インサイド・ヘッド」(15)で人間の複雑な感情を擬人化した時にも感嘆させられたが、今回はさらにその上をゆく未知なる領域への挑戦がある。これは映画史に残る偉業と言えるのかもしれない。
まずもって特定の宗教にとらわれず、メキシコの伝統行事「死者の日」にスポットを当てているのが本当にうまい。この時期に合わせて、各家庭では先祖をお迎えすべく祭壇を華やかに彩り始める。物語はそんな中、少年ミゲルの表情をクローズアップ。音楽コンテストへの参加を家族に大反対された彼は、失意のどん底にいた。この家系ではある理由から音楽がタブーとなっているのだ。それでも夢を諦めきれないミゲルが、ふとした拍子に生きながら「死者の国」へと紛れ混んでしまったことで、事態は意外な展開に----。
マリーゴールドの花びらがいざなう死者の国は、思わず目が歓喜するほどカラフルで美しい。また、ファンタジックな街並みをガイコツ姿(怖いというよりも可愛らしい!)の死者たちが闊歩する様は実にユニーク。こんな世界観を提示できただけでも十分ゴールに達しているのに、本作はさらに面影のあるガイコツ姿のご先祖様たちが入り乱れての見事なアドベンチャーへ発展していくのだ。
祭壇に写真を飾る理由。名曲「リメンバー・ミー」に謳われる切なる想い。音楽にまつわる過去……。あらゆる展開に心が大きく揺さぶられる。そして本作が最終的に帰着していくのは、死そのものではない。むしろ家族という名のルーツ、決して失われることのない絆だ。これらは何ら特別な答えではないが、だからこそ一番身近な宝物を見つけたような感慨がある。自分が長い長い物語の延長上にあることに気づき、両親や祖父母、そのまた先祖へのたまらない愛情の念が沸き起こっていく。それはきっと生を見つめ直すことにもつながるはず。
鑑賞後、すっかり色あせた古いアルバムを広げ、亡くなった人たちに久々に会いたいと思った。その日の夢の中で、もうずいぶん長い間忘れていた曽祖母のシワシワの手に触れた気がした。忘れない、と心に刻んだ。
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(2019)
| 監督 | クエンティン・タランティーノ |
| 評価 | 3.93 |
解説
『ジャンゴ 繋がれざる者』のレオナルド・ディカプリオ、『イングロリアス・バスターズ』のブラッド・ピットとクエンティン・タランティーノ監督が再び組んだ話題作。1969年のロサンゼルスを舞台に、ハリウッド黄金時代をタランティーノ監督の視点で描く。マーゴット・ロビー、アル・パチーノ、ダコタ・ファニングらが共演した。
あらすじ
人気が落ちてきたドラマ俳優、リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)は、映画俳優への転身に苦心している。彼に雇われた付き人兼スタントマンで親友のクリフ・ブース(ブラッド・ピット)は、そんなリックをサポートしてきた。ある時、映画監督のロマン・ポランスキーとその妻で女優のシャロン・テート(マーゴット・ロビー)がリックの家の隣に引っ越してくる。
映画レポート
クエンティン・タランティーノ9本目の監督作は、その題名が示す通り、これまでの彼の作品以上に彼が愛する映画の世界に至近距離で寄り添い、彼の趣味を全編に散りばめながら、思いを馳せ、懐古し、創造し、妄想する60年代ハリウッドへの挽歌にして極私的グラフィティ。
舞台はその栄光に陰りが見え始めていた69年のハリウッド。主人公はレオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットが演じるマカロニ・ウエスタンに活路を見出す落ち目のスターとそのスタントマン。タランティーノはこの2人の姿に、華麗なる成功者ではなく、スティーヴ・マックィーンやクリント・イーストウッドにはなれなかった、勝ちきれなかった者たちの悲哀を込める。
だが、タランティーノが最大の愛情を込めて描くこの映画の真の主人公は、マーゴット・ロビー演じる実在した女優シャロン・テートだ。
この50年間、マンソン・ファミリーが起こしたハリウッド史上最も凄惨な事件の被害者としてしか記憶されてこなかった一人の美しき女優を、タランティーノはスクリーンに活き活きと蘇えらせ、ロマン・ポランスキー監督と過ごした彼女の最も幸福な時を観客に共有させることで彼女を映画史にもう一度輝かせる。そして“映画の神”として、ある優しくもバイオレントな奇跡を起こすのだ。
よほどマニアックな映画ファンでなければシャロン・テートを覚えている人はいないだろう。だが、それでも自分がヒロインとして出演した「サイレンサー 破壊部隊」を映画館で見た後の満足げな彼女の美しい笑顔は涙無しには見られない。
もちろん、ハリウッド現役2トップの初共演も笑わせ、ホロリとさせ、手に汗握らせて満足度は高く、アル・パチーノ、カート・ラッセル、ブルース・ダーンといったベテランの味もガツンと効いて、映画ファンのためのお楽しみが頭から尻尾までギュっと詰まった必見のエンタテインメントである。
が、すでに各方面で言及されているように、ブルース・リーやマカロニ・ウエスタン、マンソン・ファミリーに関する描写は、あくまでもタランティーノの個人的主観で描かれるので、各分野に詳しい人から見ると“ちょっと違う”という意見も出て、公開後の賛否両論激突も必至。そのあたりは当然、タランティーノ自身も織り込み済みだろう。
L.A.コンフィデンシャル(1997)
| 監督 | カーティス・ハンソン |
| 評価 | 4.14 |
解説
縄張り争いが激化する'50年代のロス。街のコーヒーショップで元刑事を含む6人の男女が惨殺される事件が発生した。殺された刑事の相棒だった バド(ラッセル・クロウ)が捜査を開始。殺された女と一緒にいたブロンド美人リン(キム・ベイシンガー)に接近する。彼女はスターに似た女を集めた高級娼婦組織の一員。同じ頃、その組織をベテラン刑事のジャック(ケビン・スペイシー)が追っていた。野心家の若手刑事エドも事件を追い、容疑者を射殺。事件は解決したかに見えたが……。
映画レポート
1998年の第70回アカデミー賞は、作品賞を含む11部門を制した「タイタニック」の独壇場となった。しかし当初、前哨戦の結果なども含め作品賞の本命と目されていたのが、カーティス・ハンソン監督がメガホンをとった「L.A.コンフィデンシャル」である。結果は助演女優賞(キム・ベイシンガー)と脚色賞の2部門受賞に留まったが、90年代を代表するフィルム・ノワールとして未だ色褪せることなく、最高峰の作品といえる。
舞台となるのは、終戦から10年も経っていない50年代の米ロサンゼルス。戦勝国のアメリカであっても混沌とした状況が続いており、ましてや当時のロス市警はマフィアとの癒着が強固で無法地帯だったと言われている。その不穏な様子は本編にもちりばめられており、刑事たちの尋問などはめちゃくちゃ。その手口は、現代では「拷問」レベルである。
作家ジェイムズ・エルロイは、そんなロスの暗黒部分を「ブラック・ダリア」に始まる「L.A.4部作」として発表。3作目となる今作は、元刑事を含む6人が惨殺された事件を受け、ロス市警の刑事たちが警察内部にうごめく腐敗と対峙し、多くの血が流れていくさまを描いている。原作では8年間にわたる物語だが、映画では3カ月間に凝縮したことで先の読めない展開を演出している。
ストーリーを牽引していくのは、女性に暴力をふるう男を憎悪する腕っぷしの強い熱血刑事バド(ラッセル・クロウ)、出世のためなら簡単に仲間を売るため孤立するエリート刑事エド(ガイ・ピアース)、刑事ドラマのアドバイザーをしているが裏でゴシップ記者に情報を流し賄賂を受け取る汚職刑事ジャック(ケビン・スペイシー)の3人。それぞれの思惑が三者三様で飽きさせることがないのだが、更に警察上層部、マフィア、娼婦、億万長者、検事などが絡んでくるため、情報量が多すぎて見る者に多少の混乱を招く。
だが、この混乱は欠点ではない。ご都合主義的な要素は一切なく、伏線が張られまくっているため、3人の刑事が持ち寄る情報が組み合わさっていくさまは、実にスリリングで小気味いい。さらに、50年代のロスを見事に再現してみせたプロダクションデザイン、決して華美ではないが仕立ての良さが伝わる刑事たちのさりげない衣装も秀逸だ。
クロウとピアースにとっては出世作となったわけだが、その若々しく溌剌とした姿に隔世の感を覚える。スペイシーが随所に見せる“顔芸”も当時からのもので、不意にほくそ笑んでしまう。最後になるが、今作は謎解きを楽しむ類の作品ではない。あくまでも、主人公たちの心の動きを追うことに主眼を置くべきである。鑑賞後に体感する寂寥感を伴う余韻は、正統派フィルム・ノワールの系譜を受け継いでいることを証明しているのだから。
アデル、ブルーは熱い色(2013)
| 監督 | アブデラティフ・ケシシュ |
| 評価 | 3.67 |
解説
第66回カンヌ国際映画祭で史上初、パルムドールが主演女優2人にも贈られ話題を集めたラブストーリー。ジュリー・マロによるフランスの人気コミックを原作に、運命的に出会った女性同士の真っすぐな愛の行方を大胆なラブシーンを交えて繊細に描き出す。監督はこれまで数々の映画賞に輝いてきた俊英、アブデラティフ・ケシシュ。『マリー・アントワネットに別れをつげて』などのレア・セドゥと、『カレ・ブラン』のアデル・エグザルコプロスの体当たり演技が光る。
あらすじ
教師を夢見る高校生アデル(アデル・エグザルコプロス)は、運命的に出会った青い髪の画家エマ(レア・セドゥ)の知性や独特の雰囲気に魅了され、二人は情熱的に愛し合うようになる。数年後、念願の教師になったアデルは自らをモデルに絵を描くエマと一緒に住み、幸せに満ちあふれた毎日を過ごしていた。しかしエマの作品披露パーティーをきっかけに、二人の気持ちは徐々に擦れ違っていき……。
映画レポート
ボブ・マーリーとサルトルが同列に語られる。そのまさかの接続。預言者と哲学者は同じだと主人公は言う。そんな発言を聞けば、微妙に納得はできるものの、ジャマイカのレゲエの聖者であり闘士でもある歌い手と、西欧の近代思想の核となる哲学者とをこうやって繋げることの出来る女子高生とは一体何者か? それがフランスであると言ってしまえばそれまでなのだが、いずれにしてもこの映画が常に示すのは、こういった不意の出会い、あらぬ方向へと繋がる接続である。
通学バスに乗り遅れそうになった主人公が焦って走るシーンから始まるこの映画は、いつもどこか息せき切っているように見える。焦っているというより、もしかすると今ここで起こるかもしれない不意の出会いを逃すまいとする研ぎすまされた時間感覚と言った方がいいだろう。自分の身体の周囲に延びて行く触毛のような神経細胞が感じる時間とも言える。「私」という個人がはっきりと確立する前の高校生の物語、という設定も、そんなことを思わせるのかもしれない。また、主人公の性的な立場の不安定さもその一因かもしれない。
とにかくそこに生まれる輪郭の微妙な揺れを、カメラがとらえる。画面に映る風景の中に流れる空気の動きが、自然に身体に伝わる。気がつくとその空気に乗って、街角から見知らぬ音楽が聞こえてくる。そしてその一瞬、時間の流れが緩やかになり、主人公は交差点で運命の人とすれ違うのだった。不意の出会いの訪れとはこのようなものなのだと、全身でこの映画を肯定したくなる。その積み重ね。だからすべてが不安定で、もしかするとあったかもしれない別の人生が、そこからふと顔をのぞかせる。その可能性を身体中に染み込ませ、私たちも主人公も大人になるのだ。そんなことを思わせる3時間。もちろん最後に再びあの音楽が……。こうやって映画も人生も、あったかもしれない別の人生もまた、果てしなく広がり続ける。だからこそ私たちは、いつまでも映画を観続けるのだろう。
ユージュアル・サスペクツ(1995)
| 監督 | ブライアン・シンガー |
| 評価 | 4.04 |
解説
船舶の炎上事故を調べていた捜査官クラインは尋問していたヴァーバルから奇妙な話を聞かされる。6週間前に銃器強奪事件の容疑者として集められた5人が、釈放後、協力して宝石強奪を決行。ブツをさばくためにLAの故買屋と接触した5人は、そこで新たなヤマを依頼されるが、宝石と聞かされていた獲物は麻薬で、トラブルから相手を射殺してしまう。そして恐慌状態の彼らの前に、伝説のギャング“カイザー・ソゼ”の右腕と名乗る弁護士が現れたというのだ……。
映画レポート
この映画のエンディングを見終えてからというもの、似たような設定やキャラクターが映画やドラマに出てきた時、もしくは実生活においても裏で何か得体の知れない大きな力が働いているのではないかと感じた時などにふと思い出す名前がある。それほどブライアン・シンガー監督の「ユージュアル・サスペクツ」(1995)のラストに鳥肌が立ったのを覚えている。
シンガー監督は、長篇デビュー作「パブリック・アクセス」(1993)でサンダンス映画祭グランプリを受賞。次に手がけたこの「ユージュアル・サスペクツ」で一躍注目を集めた。5人の前科者による犯罪計画の顛末を巧妙なストーリー展開で描いたクライム・サスペンスで、脚本はその後トム・クルーズといくつもの作品でタッグを組んでいるクリストファー・マッカリーが手がけた。第68回アカデミー賞で脚本賞を受賞している。
そして、その巧妙なストーリー展開と演出をさらに魅力あるものにしているのがキャストだ。クセのある前科者5人を演じた、ガブリエル・バーンの渋み、スティーブン・ボールドウィンとベニチオ・デル・トロのキレ味、ケビン・ポラックの狂気、ケビン・スペイシーの不敵な笑みが相乗効果を発揮。さらにチャズ・パルミンテリ、ピート・ポスルスウェイトらが脇を固めている。彼らの絶妙な演技の応酬が、この映画のもう一つの見どころだ。
なかでも物語の語り手であり、左側の手足が不自由で気弱な詐欺師のヴァーバル・キントを演じたスペイシーは、この演技により第68回アカデミー賞で助演男優賞を受賞。同年製作の「セブン」(デビッド・フィンチャー監督)でも圧巻の存在感を見せ、「L.A.コンフィデンシャル」(1997)に続く「アメリカン・ビューティー」(1999)では第72回アカデミー賞主演男優賞を受賞した。そのほかドラマ「ハウス・オブ・カード 野望の階段」などでの名演を今さら映画ファンに説明する必要はないだろう。(但し2017年から告発が相次いだ性的暴行疑惑のため現在は主だった俳優活動を行っていない)
黒澤明監督の「羅生門」(1953)では複数の登場人物の回想によって物語が進行するが、「ユージュアル・サスペクツ」ではパルミンテリ演じる関税局捜査官が、多数の死者が見つかった麻薬密輸船爆発事件の生き残りの一人であるキントを尋問する形で、回想シーンが効果的に用いられている。キントが語る出来事によって事件が次第に明かされていくが、その中に出てくる、実在しないとも言われる伝説のギャングの名前が“カイザー・ソゼ”だ。
まるでパズルを組み合わせていくような面白さがあるのだが、次第にキントが語る話はどこまでが真実なのか、映画を見ながら組み合わせていたパズルが果たしてあっているのか、見終わった後に自分の頭の中で組み直すことになるだろう。そして、“カイザー・ソゼ”が事あるごとに頭の中でリピートされるようになったら、この映画の術中に嵌ったことになる。
ノマドランド(2020)
| 監督 | クロエ・ジャオ |
| 評価 | 3.81 |
解説
ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション小説を原作に、「ノマド(遊牧民)」と呼ばれる車上生活者の生きざまを描いたロードムービー。金融危機により全てを失いノマドになった女性が、生きる希望を求めて放浪の旅を続ける。オスカー女優フランシス・マクドーマンドが主人公を演じ、『グッドナイト&グッドラック』などのデヴィッド・ストラザーンをはじめ、実際にノマドとして生活する人たちが出演。『ザ・ライダー』などのクロエ・ジャオがメガホンを取り、第77回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で金獅子賞を獲得した。
あらすじ
アメリカ・ネバダ州に暮らす60代の女性ファーン(フランシス・マクドーマンド)は、リーマンショックによる企業の倒産で住み慣れた家を失ってしまう。彼女はキャンピングカーに荷物を積み込み、車上生活をしながら過酷な季節労働の現場を渡り歩くことを余儀なくされる。現代の「ノマド(遊牧民)」として一日一日を必死に乗り越え、その過程で出会うノマドたちと苦楽を共にし、ファーンは広大な西部をさすらう。
映画レポート
放浪生活への憧れは、アメリカの西部開拓時代からの伝統と言えるかもしれない。古くは「野性の呼び声」「マーティン・イーデン」で知られる作家ジャック・ロンドン、50年代には、「路上」でビート・ジェネレーションを代表したジャック・ケルアック、最近では映画「イントゥ・ザ・ワイルド」のモデルで、アラスカで命を落とした青年、クリス・マッキャンドレスがいた。
前作「ザ・ライダー」で、中西部に生きる現代のカウボーイの姿を描いたクロエ・ジャオ監督も、そんな憧れを持つひとりである。
だが、ジェシカ・ブルーダー原作の映画化である「ノマドランド」は、ロマンチックな放浪の夢とは趣を異にする。主人公のファーンは会社の倒産で職を失い、病で夫も亡くした61歳の女性。彼女は致し方なく、愛着のあるぽんこつキャラバンに夫との思い出の品を積み、当てのない旅に出る。生活のため、ところどころで季節労働をするうちに、自分の意志でノマド生活をする「ホームレスではなくハウスレス」な人々と出会い、新しい世界を発見する。
ジャオ監督は前作と同じ手法で、実際のノマドたちを「起用する」というよりは、彼らの生活にとけ込み、その横顔をカメラに収めた。そのなかに混じったフランシス・マクドーマンドもまた、演技ではなく、そこにただ存在し、ノマド生活を営んでいる。その佇まいはフィクションとドキュメンタリーの境界を超え、もはや観る者の先入観も消し去るほど、真実を差し出す。役を生きるとは、こういうことなのだろう。
自分の生き方を貫くことは生易しいことではない。とくにそれが現代社会の慣習に反するようなものなら、なおさらだ。ノマドたちは、「この生活の素晴らしいところは最後の“さよなら”がないから。“また路上で会おう”と言うだけ」と語るが、それはまた、死に際に誰にも看取ってもらえない可能性もあるということだ。否、圧倒的にその確率の方が高い。
だから自ら辺境の人生を選ぶのなら、何があっても後悔しないような覚悟がいる。この映画は、そんなノマド生活の厳しさも十分に掬い取った上で、それでも、そこにある何かかけがえのないロマンを謳いあげる。
ファーンはひとり、静けさに満ちた神秘的な岩山や、激しい風雨の吹き付ける海岸に佇む。ときに神々しい美しさをたたえ、圧倒的な力に満ちた自然の前で、彼女は無力でちっぽけであり同時に、自由で、大地と繋がった存在でもある。
現代におけるノマド生活を通して、人間の生きる意味とは何なのか、といった本質的なテーマに思いを至らせる、それが本作の底知れない力だ。
セブン(1995)
| 監督 | デヴィッド・フィンチャー |
| 評価 | 4.15 |
解説
キリスト教の“七つの大罪”になぞらえた奇怪な連続殺人事件を追う二人の刑事を描いたサイコ・サスペンスで、アメリカ・日本ともに大ヒットを記録した。凝りに凝ったオープニングが象徴するように、デヴィッド・フィンチャーのスタイリッシュな画造りと、ブラッド・ピット&モーガン・フリーマンの渋い演技が光る一編。
行き止まりの世界に生まれて(2018)
| 監督 | ビン・リュー |
| 評価 | 3.86 |
解説
かつて繁栄したものの今は衰退した、アメリカの「ラストベルト(錆びついた工業地帯)」を舞台にしたドキュメンタリー。鬱屈(うっくつ)した思いをスケートボードにぶつけ、成長していく3人の若者の姿を映し出す。今回出演も果たすビン・リューが監督・製作・撮影・編集を担当し、キアー・ジョンソン氏とザック・マリガン氏らが共演。第91回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞と、第71回エミー賞の「Outstanding Documentary Or Nonfiction Special」などにノミネートされた。
あらすじ
家庭環境に恵まれないキアー・ジョンソン氏、ザック・マリガン氏、ビン・リュー監督の3人の若者は、イリノイ州ロックフォードで暮らしている。厳しい現実から逃れるようにスケートボードに熱中する彼らにとって、スケート仲間はもうひとつの家族であり、ストリートこそが自分たちの居場所だった。やがて彼らも成長し、目の前に立ちはだかるさまざまな現実に向き合う時期がやって来る。
映画レポート
“名もなき市井の人”を描く――そんな触れ込みの映画がこれまでに何万本作られてきただろう。しかしフィクションであってもドキュメンタリーであっても、作り手の視点が介在する限り、100%純粋な現実に近づくことは難しい。
しかしアカデミー賞候補にもなったこのドキュメンタリー映画は、限りなく本物の現実を映すことに成功しているように思える。なぜなら“名もなき市井の人”である当事者が監督し、(最初はたまたま)自分たちに12年間カメラを向け続け、しかもドキュメンタリー作家に必要な観察眼を備えていたという、奇跡のようなめぐり合わせで生まれた作品だからだ。
中国系移民のビン・リューは、荒廃した人口15万人の町ロックフォードで、スケートボード仲間とスケートビデオを撮影する少年だった。やがてリューは町を出て映画業界で働き始めるのだが、地元の仲間たちのことも撮影し続けていた。スケートビデオは、いつしか仲間たちの人生を追うドキュメンタリー映画に発展していく。
主人公に選ばれたのは、父親に暴力を振るわれている黒人の少年キアーと、仲間の中でカリスマ的な存在だった若者ザック。ザックはガールフレンドとの間に子供が生まれ、懸命にいい父親になろうとしていた。少なくとも最初のうちは……。
この作品がどんな形に仕上がるのか、監督も含め誰もわかっていなかっただろう。しかし一緒に育った仲間であるリュー監督の前で、キアーやザックは飾らぬ本音を語り、時にみっともない姿もさらけ出す。そして「家庭内の暴力の連鎖」というテーマに踏み込んだことで、リュー監督は自分自身や母親にもカメラを向ける決意をしたという。彼自身も継父の家庭内暴力に苦しんだ当事者だったからだ。
筋書きのない人生を映しているから、この映画に明快なストーリーやゴールはない。タイムカプセルのようにかけがえのない瞬間を封じ込めている、と言えば聞こえはいいが、聡明なリュー監督は、自分たちをノスタルジーで包んで美化しようとはしない。
例えば仲間たちがフザケて黒人をネタに冗談を飛ばしている時、カメラはキアーの複雑な表情を見逃さない。輝くような青年だったザックの凋落からも目をそらしたりはしない。自分たちの未来は不安定で、善悪の境目は限りなく曖昧で、すべては道半ば。しかしそれでも、友情や希望のかけらは残っている。変化する人間関係と流れていく時間を描いた、とても正直で知的で優しい映画だと思う。
ラ・ラ・ランド(2016)
| 監督 | デイミアン・チャゼル |
| 評価 | 4.10 |
解説
『セッション』などのデイミアン・チャゼルが監督と脚本を務めたラブストーリー。女優の卵とジャズピアニストの恋のてん末を、華麗な音楽とダンスで表現する。『ブルーバレンタイン』などのライアン・ゴズリングと『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』などのエマ・ストーンをはじめ、『セッション』でチャゼル監督とタッグを組んで鬼教師を怪演したJ・K・シモンズが出演。クラシカルかつロマンチックな物語にうっとりする。
あらすじ
何度もオーディションに落ちてすっかりへこんでいた女優志望の卵ミア(エマ・ストーン)は、ピアノの音色に導かれるようにジャズバーに入る。そこでピアニストのセバスチャン(ライアン・ゴズリング)と出会うが、そのいきさつは最悪なものだった。ある日、ミアはプールサイドで不機嫌そうに1980年代のポップスを演奏をするセバスチャンと再会し……。
映画レポート
ハイウェイの渋滞に業を煮やした人々が踊り出すプロローグのダイナミックなミュージカルシーンは、運搬橋を舞台にキャラバン隊が踊る「ロシュフォールの恋人たち」を連想させる。一方、エピローグで恋人たちの数年後に話が飛ぶところは、「シェルブールの雨傘」を思わせる。ジャック・ドゥミ監督のミュージカル映画へのオマージュがブックエンドをなす「ラ・ラ・ランド」には、他にも「バンド・ワゴン」のエレガントな公園のダンスから「世界中がアイ・ラヴ・ユー」の空中浮遊まで、新旧ミュージカル映画のエッセンスが詰め込まれている。が、デイミアン・チャゼル監督の本領はそうした引用のうまさではなく、リアルな描写からファンタジーへとミュージカルシーンをなめらかに昇華させるテクニックを心得ていることだろう。恐るべき32歳だ。
ミュージカル映画定番の「芸能界の内幕物」に属するストーリーも魅力だ。女優志望のミア(エマ・ストーン)と売れないジャズマンのセブ(ライアン・ゴズリング)が繰り広げる愛らしいラブストーリーには、2種類の悲哀が宿っている。ひとつはアーティストの悲哀。生活のために売れ線のバンドに加わるセブと、才能の限界を感じるミア。妥協を突きつけられる2人の揺れる心情が切なさをかきたてる。もうひとつは恋愛の悲哀。人生の浮き沈みのタイミングのすれ違いが恋愛の行方を微妙に左右する設定は、ハラハラさせると同時に胸をキュンとしめつける。
この2種の悲哀が絡み合ってドラマを生む構成は「ニューヨーク・ニューヨーク」と同じだが、主人公を見守りたいと思わせる共感度の高さは「ラ・ラ・ランド」が勝っている。それがラストで生きる。かなった夢とかなわなかった夢、逃した幸福とつかんだ幸福。誰もが経験するであろう人生の忘れ物が走馬燈のようにかけめぐる至福の15分間。これを見たら、インスピレーションの元になった「巴里のアメリカ人」のビンセント・ミネリ監督も誇りに思うに違いない。
運命の女(2002)
| 監督 | エイドリアン・ライン |
| 評価 | 3.48 |
解説
コニー・サムナーはニューヨーク郊外で暮らす専業主婦。マンハッタンで会社を経営する夫エドワードと9歳になる息子チャーリーと3人で、平凡だが幸せな生活を送っていた。ある日、コニーはチャーリーの誕生日プレゼントを買うためマンハッタンへ出掛けた。通りを歩いていたコニーは、大量の本を抱えた青年と衝突した。その青年、フランス人でブック・ディーラーのポール・マーテルは、膝を怪我したコニーの治療をするため彼女を自分のアパートに招き入れる。以来、何度か彼を訪ねることになったコニーは、やがて越えてはならない一線を越えてしまう…。
映画レポート
不倫に殺人事件。下手をするとテレビの安いサスペンス劇場や昼メロになりそうな題材だし、“いかにも”感に満ちたスタッフ、キャストの顔ぶれには派手さも新味もない。でも、これはその“ありがち”で“そこそこ”な題材と顔ぶれだからこそ驚きも興奮も大きな、見応え満点のサスペンス・ドラマだ。
まず何といってもダイアン・レイン。かつての「リトル・ロマンス」の天才美少女が腹をくくって艶じるぶりは、感慨深くも感動的。今年の賞レースでも本命必至のその演技レベルは少なくとも、「ビューティフル・マインド」や「チョコレート」の女優たちよりかなり上。一方、ハリウッドの元セックス・シンボル、リチャード・ギアも苦悩する普通の中年男を自然体の脂抜き芝居で演じて異様に好感度高し。この2人の元スターの本物の役者への成長ぶりだけでもかなりの収穫だ。
さらに驚きなのが、インモラル映像職人エイドリアン・ラインの官能シーンだけではなく、登場人物の内面にまでしっかり迫った風格漂う名匠ぶり。ありきたりな人道主義に持っていかないオチの処理も鮮やかで、案外あなどっていた旧作まで見返してみたくなった。
典型的な外見とは裏腹に、演技も演出も腰の据わったプロの仕事を堪能させてくれる、極めて珍しいまっとうなハリウッド映画。先入観を捨てて見て欲しい必見作だ。
グッドフェローズ(1990)
| 監督 | マーティン・スコセッシ |
| 評価 | 3.89 |
解説
実在の人物をモデルに、少年の頃からギャングに憧れ、その仲間入りを果たした一人の男の波瀾に満ちた半生を、主人公のモノローグを織り込みながら描いた犯罪ドラマ。
ゲット・アウト(2017)
| 監督 | ジョーダン・ピール |
| 評価 | 3.73 |
解説
『パラノーマル・アクティビティ』シリーズなどを手掛けてきたプロデューサー、ジェイソン・ブラムが製作に名を連ねたスリラー。恋人の実家を訪ねた黒人の青年が、そこで想像を絶する恐怖を体験する。メガホンを取るのはコメディアンのジョーダン・ピール。『Chatroom/チャットルーム』などのダニエル・カルーヤ、ドラマシリーズ「GIRLS/ガールズ」などのアリソン・ウィリアムズらが出演する。
あらすじ
ニューヨークで写真家として活動している黒人のクリス(ダニエル・カルーヤ)は、週末に恋人の白人女性ローズ(アリソン・ウィリアムズ)の実家に招かれる。歓待を受けるが、黒人の使用人がいることに違和感を覚え、さらに庭を走り去る管理人や窓に映った自分を凝視する家政婦に驚かされる。翌日、パーティーに出席した彼は白人ばかりの中で一人の黒人を見つける。古風な格好をした彼を撮影すると、相手は鼻血を出しながら、すさまじい勢いでクリスに詰め寄り……。
映画レポート
今年2月に全米チャート1位を記録し、興収1億ドルの大台超えを軽々と達成したスリラー映画である。今なおアメリカ社会に根深く残る人種差別というテーマを恐怖と笑いに転化させたのは、これが監督デビュー作となる人気コメディアンのジョーダン・ピール。さて、そのお手並みはいかなるほどか?
インテリ写真家の黒人青年クリスは、ルックスも気立ても抜群の白人女性ローズと交際中。しかし往年の社会派ドラマ「招かれざる客」のシドニー・ポワチエさながらに、ニューヨーク郊外にあるローズの実家を訪ねることになった彼の胸の内は不安でいっぱいだ。ローズいわく「私のパパはオバマ大統領の支持者」だそうだが、ポワチエのあの映画だってリベラルな白人層の欺瞞を痛烈に暴いていたではないか。対面早々、相手に「出て行け!(get out!)」と怒鳴られるのではないかと、戦々恐々となるのも無理はない。
この導入部からして好奇心をそそる本作は、観客の予想もつかない"衝撃の展開"が用意されているのだが、それに至るまでのスリルの盛り上げ方が実にうまい。やけにほがらかなローズの両親に歓待されてホッとひと息つくクリスだが、すぐさま宣伝コピーにもなっている"何かがおかしい"感覚にまとわりつかれるはめになる。ニタニタと薄気味悪い笑みを浮かべるメイド、真夜中に広大な庭を全力疾走で駆ける管理人の男(どちらも黒人だ!)、過剰なまでにフレンドリーなパーティーの白人客たち。彼らがまきちらす微妙な違和感が、ふとした弾みで"明らかにおかしい"サプライズへと変わりゆくショック描写が効果的にちりばめられ、しかもそれがいちいち後半への予兆と伏線になっている。これは決してアイデア勝負の一発芸ではなく、知的で抜け目のない演出、脚本に裏打ちされた"人種差別スリラー"なのだ。
クリスを絶望のどん底に突き落とすギミックのひとつとして、催眠術が用いられることを明かしてもネタバレには抵触しないだろう。少年時代にあるトラウマを負った主人公が心の深層に眠る"究極の恐怖"をえぐり出される様を、映画ならではのシュールな飛躍に満ちた悪夢的イメージで映像化。その後のあっと驚く展開はかなり荒唐無稽なのだが、そこにもねっとりとした嫌らしい生々しさがみなぎる。これだからアメリカのジャンル映画を観るのは止められないと思わされる大収穫の怪作、いや鮮やかな快作なのであった。
スラムドッグ$ミリオネア(2008)
| 監督 | ダニー・ボイル |
| 評価 | 4.04 |
解説
『トレインスポッティング』『28週後…』など多彩なジャンルで観客を魅了する、鬼才ダニー・ボイルの最高傑作といわれる感動的なヒューマン・ドラマ。インドを舞台に、テレビのクイズ番組に出演して注目を集めたある少年が、たどってきた生い立ちと運命の恋をボリウッド風の持ち味を生かしながらつづっていく。主演はこの作品でデビューし、数々の映画賞を受賞したデヴ・パテル。底知れないパワーと生命力を感じさせる人間讃歌に息をのむ。
あらすじ
テレビ番組「クイズ$ミリオネア」に出演し、賞金を獲得したジャマール(デヴ・パテル)だったが、インドのスラム街で育った少年が正解を知るはずがないと不正を疑われ逮捕される。ジャマールになぜこれほどの知識があり、この番組に出演するに至ったのか。警察の尋問によって、真実が明らかになっていく。
映画レポート
ムンバイの若者の現在と過去を、英国人監督が描き出す本作には、笑いと涙、夢と冒険、アクションとロマンス、ありとあらゆる要素が詰め込まれている。基軸は、困難に打ち克つサクセスストーリー。そう、人と場所は違えども、これは典型的な“ハリウッド映画”である。
クイズ番組に出演した青年が全問正解を前にして、不正を疑われ司会者に告発される。逮捕された挙げ句、拷問まで受けるのだが、まさかあり得ないと思わせないカオスがこの街にはある。高層ビルとスラムが混在する大都市が、過激な出来事にもリアリティをもたらすのだ。なぜ無学の彼がクイズに答え続けられたのかというミステリーの下、青年の生い立ちが明らかになっていく。その忌まわしく陰惨な過去には、格差社会、幼児虐待、裏ビジネス、宗教暴動、急激な近代化といった、インド現代史が凝縮されている。社会の底辺を駆け抜けてきたからこそ、必要な知識を身につけていたという一見あざとい構成。しかし、「トレインスポッティング」に原点回帰したダニー・ボイルの疾走感あふれる演出は、インドの現実をデフォルメしていく上で実に効果的だ。
スピルバーグの映画会社ドリームワークスがインド資本となり、ハリウッドが衰弱しきったご時世、アメリカは失われたドリームをこの地に見て、大量のオスカーを与えたのだろう。いや、同時不況にあえぐ今、インドのエネルギッシュな夢物語は、世界中で歓迎されるに違いない。
シンドラーのリスト(1993)
| 監督 | スティーヴン・スピルバーグ |
| 評価 | 4.36 |
解説
ナチによるユダヤ虐殺をまのあたりにしたドイツ人実業家オスカー・シンドラーは、秘かにユダヤ人の救済を決心する。彼は労働力の確保という名目で、多くのユダヤ人を安全な収容所に移動させていくのだが……。スピルバーグが長年あたためていたT・キニーリーの原作を遂に映画化。念願のアカデミー賞(作品・監督・脚色・撮影・編集・美術・作曲)に輝いた作品。
英国王のスピーチ(2010)
| 監督 | トム・フーパー |
| 評価 | 3.91 |
解説
吃音(きつおん)に悩む英国王ジョージ6世が周囲の力を借りながら克服し、国民に愛される王になるまでを描く実話に基づく感動作。トロント国際映画祭で最高賞を受賞したのを皮切りに、世界各国の映画祭などで話題となっている。監督は、テレビ映画「エリザベス1世 ~愛と陰謀の王宮~」のトム・フーパー。ジョージ6世を、『シングルマン』のコリン・ファースが演じている。弱みや欠点を抱えた一人の男の人間ドラマと、実話ならではの味わい深い展開が見どころ。
あらすじ
幼いころから、ずっと吃音(きつおん)に悩んできたジョージ6世(コリン・ファース)。そのため内気な性格だったが、厳格な英国王ジョージ5世(マイケル・ガンボン)はそんな息子を許さず、さまざまな式典でスピーチを命じる。ジョージの妻エリザベス(ヘレナ・ボナム=カーター)は、スピーチ矯正の専門家ライオネル(ジェフリー・ラッシュ)のもとへ夫を連れていくが……。
映画レポート
人生を左右する出会いには必然性がある。吃音に悩んでいたヨーク公(のちのジョージ6世=コリン・ファース)と、医師の免許もなくパッとしない人生を送っていたスピーチ矯正師ローグ(ジェフリー・ラッシュ)の場合も例外ではない。もしこの出会いがなかったら2人の人生はもちろん、イギリスの命運も変わっていただろう。そう思わせるほど、吃音の克服と2人の人生の山場がドラマチックにクロスしている。フィクションを超えた実話の面白さに魅了されてしまった。
とにかくこの映画に出てくるエピソードはどれも面白すぎる。一番驚いたのはヨーク公の悲惨な幼年時代だ。強くて怖い父親と自由奔放な兄に挟まれ、左利きやX脚の矯正を無理強いされ、乳母にまで虐待されていたとは。そして、純愛物語として有名なエドワード8世の「王冠をかけた恋」は、わがままな兄が突然家業を放り出して自信のない弟に責任を押しつけるという、兄弟の葛藤にフォーカスされている。王室ものとして以上に、威圧的な親が息子を抑圧するファミリードラマとして面白いし、立場が違えば同じ事件でもこんなに違う様相になるというのも興味深い。
ヨーク公の苦悩をベースにした落ち着いたトーンに、ローグとの関係の変化を3段階で表現してアクセントをつけた脚本の構成も見事だ。閉じこもっていた殻から一歩踏み出すヨーク公をユーモラスに見せるトレーニングシーン。自分の運命はローグに託すしかないと決断する戴冠式のリハーサル。そして、2人の信頼関係が最高の効果を発揮するラストのラジオ放送だ。このシーンで、ローグはオーケストラの指揮者、ジョージ6世はそのタクトに導かれる演奏者のように見えて感動した。ファース、ラッシュ、そしてヘレナ・ボナム・カーターら俳優たちの素晴らしさは言うまでもない。
ディパーテッド(2006)
| 監督 | マーティン・スコセッシ |
| 評価 | 3.53 |
解説
巨匠マーティン・スコセッシが、香港映画『インファナル・アフェア』をリメイクしたアクションサスペンス。マフィアに潜入した警察官と、警察に潜入したマフィアの死闘がスリリングに描かれる。レオナルド・ディカプリオとマット・デイモンが主人公の警察官とマフィアをそれぞれ熱演。名優ジャック・ニコルソンがマフィアのボス役で脇を固める。ボストンを舞台に描かれた本作は、スコセッシ監督らしいバイオレンスシーンと、敵対組織に潜入した男ふたりの心理描写に注目。
あらすじ
犯罪者の一族に生まれたビリー(レオナルド・ディカプリオ)は、自らの生い立ちと決別するため警察官を志し、優秀な成績で警察学校を卒業。しかし、警察に入るなり、彼はマフィアへの潜入捜査を命じられる。一方、マフィアのボス、コステロ(ジャック・ニコルソン)にかわいがられて育ったコリン(マット・デイモン)は、内通者となるためコステロの指示で警察官になる。
映画レポート
「グッドフェローズ」以来、久々にホレボレするクライムストーリーだ。ワルとデカが互いに“ネズミ”(潜入者)を送り込んだことから悲劇を招く。筋立てはご存じ香港スリラー「インファナル・アフェア」の焼き直しだ。だが物語ばかり追いかけると見逃してしまう、映画の醍醐味がこの映画にはある。それは、独特のリズムとビートを刻む魔術的なカメラワーク(撮影)と、圧倒的な「プロテクション・ショット」から選ばれた神業のようなカッティング(編集)だ。いかにもスコセッシ映画らしい、カトリック的罪悪感やアイルランド系移民(マイノリティ)の叫びが通奏低音として響きあい、オリジナルとひと味違う。
ディカプリオもニコルソンも、スコセッシ好みの“重層的”でカラフルなキャラクターで、彼らの黒いアンサンブルが不気味なハーモニーを奏でる。また、ローリング・ストーンズ「ギミー・シェルター」、ピンク・フロイドの名曲「コンフォタブリー・ナム」、ロイ・ブキャナンの超絶ギターにシビレる「スウィート・ドリームス」、ハワード・ショア作曲のタンゴ調テーマ曲(ドブロの旋律が最高)といったゴキゲンな音楽が人物をリズミカルに躍動させる。その1曲1曲に、映画的かつ音楽的“引用”がある。その秘密を知るとき、得体のしれない魔力に襲われるのだ。
パンズ・ラビリンス(2006)
| 監督 | ギレルモ・デル・トロ |
| 評価 | 3.83 |
解説
1944年のスペイン内戦下を舞台に現実と迷宮の狭間で3つの試練を乗り越える少女の成長を描くダーク・ファンタジー。『デビルズ・バックボーン』のギレルモ・デル・トロ監督がメガホンをとり、ファシズムという厳しい現実から逃れるため、架空の世界に入り込む少女を通じて人間性の本質に鋭く切り込む。イマジネーションあふれる壮大な視覚技術を駆使して生まれたクリーチャーや深く考察されたテーマに根ざした巧みな演出が衝撃的。
あらすじ
1944年のスペイン内戦で父を亡くし、独裁主義の恐ろしい大尉と再婚してしまった母と暮らすオフェリア(イバナ・バケロ)は、この恐ろしい義父から逃れたいと願うばかり自分の中に新しい世界を創り出す。オフェリアが屋敷の近くに不思議な迷宮を見つけ出して足を踏み入れると、迷宮の守護神が現われ彼女に危険な試練を与える。
映画レポート
過酷な現実を生きる少女が出会った牧羊神パンは、彼女にささやく、「あなたは本当は魔法の王国のプリンセス。3つの試練を果たせば王国に帰れます」。だが、この牧羊神が招く地下の迷宮は恐怖に充ちている。そこは血と泥に塗れ、妖精の羽は萎れて体は乾涸らび、掌に眼を持つ肥大化した胎児のような異形の者が追いかけてくる。これは、読書好きの少女が現実から逃れるために創った世界ではない。もちろん、彼女は物語を必要とするが、それは物語というものの力が、現実を凌駕することがあるからなのだ。人間にはなぜ物語が必要なのか。監督ギレルモ・デル・トロのこの問いへの答えがこれだ。
そのうえで、幾重にも重ねられた多彩なモチーフが映画を豊かにする。牧羊神パンのキリスト教伝播以前の森の土着神としての顔。幼児だけが持つ母親への無条件の憧憬と賞讃。女としての母。歪められた子供としての義父。ゲリラ軍の姉と弟の愛。そしてそれらの通底音として流れるのは、少女の性の目覚めの予感だ。少女が開く未来を記された魔法の本は血に染まり、母の下半身は血に染まり、母のベッドの下のマンドラゴラの根は蠢く。初潮を迎える寸前の少女だけが持つ無意識の不安と恐怖が、迷宮の血の匂いを濃密にし、同時に彼女の無垢さをより輝かせている。
コメント
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です。
関連記事
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】ivfree.asiaは安全?視聴方法や代わりサイトまで一気にご紹介!
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】カリビアンコムのダウンロード廃止?今なら使えるカリビアンコム動画のダウンロード方法!
- Aoi / 2023-12-26【高品質かつ安全】Supjavからアダルト動画をダウンロードする方法
- Aoi / 2023-12-21【23年最新】Avgle ダウンロードの裏技を公開!簡単に高画質動画を入手~Android・iPhone/iPad・PC全環境対応
- Aoi / 2023-11-30av4.usが閉鎖!?代わりの無料アダルト動画サイトをまとめ
- Aoi / 2023-11-29【無料】TokyoMotionダウンロードする方法、その操作手順まで詳しくご紹介!(PC&スマホ)
最新記事 人気記事
Kira / 2024-09-24
【無料】ディズニー動画ダウンロード方法おすすめ|ディズニー+から映画を保存してオフラインで視聴しよう
Kira / 2024-09-24
SwitchでHuluは見れません!その理由と今後の動向を予想して裏技まで紹介します
Melody / 2024-09-24
【2023年】Huluを録画する方法!裏ワザ?真っ黒にならないソフトを紹介します
Kira / 2024-09-24
AbemaTVをダウンロード&録画できるツール7選!DRM解除できるものだけを厳選
HANA / 2024-09-24
【ABEMA ダウンロード】ABEMA(旧AbemaTV)動画をダウンロードする方法、ダウンロードできない原因と対策
youjinkin / 2024-09-24
U-NEXTで鑑賞できるおすすめアニメ作品TOP 20
Kira / 2024-09-24
U-NEXTがダウンロードできるツールトップ7!録画ソフトも
Melody / 2024-09-24
【完全保存版】U-NEXTのダウンロード方法!できない時の原因と解決法も
Tetsuko / 2024-09-24
StreamFab myFansダウンローダーの機能や使い方、評判をレビューして徹底解説!
Tetsuko / 2024-05-09
Missavの無料エロ動画をダウンロードするツール5選
展開 ∨ 折りたたみ ∧
ホットトピックス

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次
Copyright © 2024 entametalk.jp All Rights Reserved.
年齢認証

あなたは18歳以上ですか?
エンタメTALKはアダルトコンテンツを含みますので、18歳未満の方の閲覧を固くお断りいたします。
いいえ はい