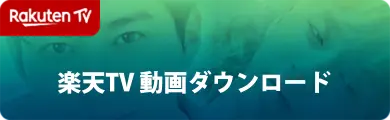StreamFab 動画 ダウンローダー
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次>
万引き家族(2018)
| 監督 | 是枝裕和 |
| 評価 | 4.08 |
解説
『誰も知らない』『そして父になる』などの是枝裕和監督による人間ドラマ。親の年金を不正に受給していた家族が逮捕された事件に着想を得たという物語が展開する。キャストには是枝監督と何度も組んできたリリー・フランキー、樹木希林をはじめ、『百円の恋』などの安藤サクラ、『勝手にふるえてろ』などの松岡茉優、オーディションで選出された子役の城桧吏、佐々木みゆらが名を連ねる。
あらすじ
治(リリー・フランキー)と息子の祥太(城桧吏)は万引きを終えた帰り道で、寒さに震えるじゅり(佐々木みゆ)を見掛け家に連れて帰る。見ず知らずの子供と帰ってきた夫に困惑する信代(安藤サクラ)は、傷だらけの彼女を見て世話をすることにする。信代の妹の亜紀(松岡茉優)を含めた一家は、初枝(樹木希林)の年金を頼りに生活していたが……。
映画レポート
子どもは生まれてくるとき環境を選べない。でも、もし選択の自由があったら? 虐待する親と、愛情かけて万引きをやらせる親。あなたはどちらと一緒に暮らすだろう?
劇中、治(リリー・フランキー)が不憫に思って家に連れ帰る5歳の少女は、虐待する実親の元へ戻らず、治たち家族の一員になる道を選ぶ。一方、治の息子の祥太(城桧吏)は、治に指南された万引きの正当性に疑問を持ち始めたことから、「この家族と同じ価値観を共有していけるだろうか?」と迷うようになる。
大人の不正と、自身の心に芽生えた正義感の間で揺れる祥太の葛藤は、ダルデンヌ兄弟監督の「イゴールの約束」で、違法外国人労働者の売人をする父を手伝う少年イゴールが体験するものに似ている。イゴールも祥太も、汚れ仕事以外に生きる術を知らない大人の保護下で、自分はどう生きるべきかを自問する。これは、そんな少年の成長と選択を描く超一級の思春期映画だ。
おそらく是枝裕和監督作品の中では、「誰も知らない」の遺伝子をいちばん多く受け継いでいるだろう。しかし、児童虐待から独居老人まで、いまどき日本の社会問題を6人の登場人物に背負わせた群像劇でもあるこの映画には、さらなる是枝的要素が混ざり合っている。子どもたちを愛し、愛される親になろうと奮闘する治と信代(安藤サクラ)の物語は、「そして父になる」の続編だ。また、法律的な善人が犯す悪(少女の親による虐待)と、法律的な悪人が成す善(治による虐待児の保護)を対比させた点は、「三度目の殺人」の流れを汲んでいる。まさしく集大成だ。
この映画の創作を思い立ったとき、「犯罪でしかつながれなかった」というキャッチコピーを最初に思い浮かべたという是枝監督は、「この家族が何でつながっているか?」という問いを見る側にも投げかける。私に見えた答えは「不安」だ。6人はそれぞれの不安を埋め合うように肩寄せ合って暮らし、同時に秘密が露見することに対する不安を共有している。そして、最も幸せな瞬間にもそれは消えることがない。その心象風景を、寒色で表現した映像が素晴らしい。(矢崎由紀子)
40歳の解釈:ラダの場合(2020)
| 監督 | ラダ・ブランク |
解説
[Netflix作品]ラダ・ブランクが監督・脚本・主演をこなしたコメディー。40歳を目前に控えたニューヨークに住む主人公が、劇作家としての成功を夢見るもののなかなか実現せず、別のアプローチで自らの本音を表現しようとする。ピーター・キムやオズウィン・ベンジャミン、『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』などのイマニ・ルイスらが共演。本作はサンダンス映画祭で、ドラマ(アメリカ国内)部門の監督賞を受賞した。
あらすじ
ニューヨークで暮らすラダ(ラダ・ブランク)は、40歳を目前に何とか劇作家として活路を開こうともがいていた。だが、残されていたラストチャンスさえ自分のミスで逃してしまい、ついに成功への道は閉ざされてしまう。にっちもさっちもいかなくなった彼女は、今の自分の本音をさらけ出し、ラッパーの「ラダムスプライム」として再スタートを切る。
ハスラーズ(2019)
| 監督 | ローリーン・スカファリア |
| 評価 | 3.25 |
解説
ニューヨークで実際に立てられた計画を基にしたクライムムービー。ストリップクラブの女性たちが、ウォール街で働く人々から大金を奪おうとする。メガホンを取るのは『エンド・オブ・ザ・ワールド』などのローリーン・スカファリア。『クレイジー・リッチ!』などのコンスタンス・ウー、『ザ・セル』などのジェニファー・ロペス、『セイブ・ザ・ラストダンス』などのジュリア・スタイルズのほか、キキ・パーマー、リリ・ラインハート、リゾ、カーディ・Bらが出演する。
あらすじ
デスティニー(コンスタンス・ウー)は、母に捨てられた自分を育ててくれた祖母の面倒を見るために、ストリップクラブで働き始める。先輩ストリッパーのラモーナ(ジェニファー・ロペス)やダイヤモンド(カーディ・B)から仕事のノウハウを教わり生活は安定するが、リーマン・ショックが起きて世界の経済が揺らぎ、彼女たちの仕事も不況のあおりを受ける。ある日ラモーナが、経済危機を引き起こしながら裕福な生活を送るウォール街の金融マンから大金を奪おうと仲間に持ち掛ける。
映画レポート
舞台はリーマンショック前後、ニューヨークのストリップクラブ。ウォール街のスーツ男たちから金を巻き上げようと、欲望のダンスを踊り続けた女たちのクライム・ストーリー。雑誌に載った実録記事を、ローリーン・スカファリアが脚色・監督した野心作だ。チームを組んだ女たちが「オーシャンズ8」よろしく痛快にやってくれるのかと思えば、さにあらず。もっとリアルでえげつなくて人間臭く、しかもパワフルかつエモーショナルで面白い!
幕開けは、いろいろな意味で象徴的。ジャネット・ジャクソンの「Control」を背景に、クラブの奥へと入っていくアジア系の新入りストリッパー、デスティニーを追うカメラは否応なしに「グッドフェローズ」を思わせる。そして、運命の出会いだ。クラブのステージで美しいポールダンスを踊るラモーナに、観客だって息を飲み、衝撃を受けるだろう。これが、御年50になろうというJ.Lo(ジェニファー・ロペス)なのだ! 半裸のまま屋上に出たデスティニーを、毛皮のコートを広げて「入りな」と迎え入れ、温めてくれるラモーナは、まるでひな鳥を抱く親鳥だ。
必要なことをすべて教え、家族のように支え、悪いことにも巻き込むことになる、カリスマ的姐御ラモーナ。バブルがはじけ、再びどん底を味わった後で、女たちはこの親鳥の下に身を寄せて疑似姉妹になる。そして相変わらずリッチな金融マン相手に汚い犯罪をエスカレートさせていくのだ。けしからん金持ちから金を巻き上げる彼女たちを、映画は正義のロビン・フッドには見せない。ただ、女たちを取り巻く世界のシビアさをこれでもかと描き、彼女たちを簡単にはジャッジさせない……どころか、#MeToo運動後の世界に共感と同情を呼びまくるのである。ここにあるのは女(しかも有色人種)であるがゆえの楽しさ、哀しみ、悔しさ、強さ、生きづらさ……。「グッドフェローズ」のギャングたちは、自分が男であることをこんなに噛みしめることはなかったはずだ。
そしてもちろん、女の友情(シスターフッド)映画としての素晴らしさは、特筆に値する。なぜか女の友情というのは男の友情ほど単純に「女が女に惚れた」だけでは終わらず、嫉妬や憎しみで濁りがちなのだ、とくに映画では。しかしこの作品はめずらしく、びっくりするほど純粋なラブストーリーになっている! 回想の中でキラキラと輝く幸せな記憶は「男の友情」映画のように直球で刺さるし、ラストのJ.Loはきっと甘やかな痛みと懐かしさを誘うだろう。かつて仲がよかったのにすっかり疎遠になってしまったあの旧友のように。
プロミシング・ヤング・ウーマン(2020)
| 監督 | エメラルド・フェネル |
| 評価 | 4.01 |
解説
ドラマシリーズ「ザ・クラウン」などで知られる女優、エメラルド・フェネルが監督と脚本を務めたサスペンスドラマ。輝かしい未来を歩もうとしていた女性が、ある出来事を契機に思わぬ事態に直面する。『ワイルドライフ』などのキャリー・マリガン、『ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ』などのボー・バーナムのほか、ラヴァーン・コックス、アリソン・ブリーらが出演する。
あらすじ
明るい未来が約束されていると思われていたものの、理解しがたい事件によってその道を絶たれてしまったキャシー(キャリー・マリガン)。以来、平凡な生活を送っているように思えた彼女だったが、夜になるといつもどこかへと出かけていた。彼女の謎めいた行動の裏側には、外見からは想像のできない別の顔が見え隠れしていた。
映画レポート
かわいらしくてポップでガーリー。なのに毒々しくショッキングで、ブラックだがロマンティックな一面もあり、笑える。そしてひどく切ない。相反する味わいをミックスしてあらゆる意味で観客の意表を突いてくる、果敢なリベンジ・エンターテインメントである。復讐の天使、キャシー(キャリー・マリガン)が鉄槌を下す相手、それは自分をナイスガイだと思っている、世の罪深き男どもだ。
10数年前、大学の医学部に在籍する“将来有望な若き女性”だったキャシーは、ある事件で親友のニーナを失う。そして人生のすべてを見失ってしまったのだ。
いまの日本にとって実にタイムリーなテーマだ。昨年度のアカデミー賞脚本賞候補作なのだが脚本・監督のエメラルド・フェネルは予知能力があるのかと思うほど。森元首相(元東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長)の問題発言などで男性の無自覚な女性差別意識が露呈し、「ふざけるなー」と叫びたくなっている女性にとって、キャシーはカタルシスをもたらしてくれる必殺仕置き人かもしれない。だが、それだけでは終わらないのがこの映画だ。中盤以降の展開はまさに予測不可能。観客はピンボールの球になったかのような衝撃&アップダウンを味わうことになるだろう。選曲のセンスや笑いの直後に戦慄させる急旋回などはタランティーノにも通じるテイストがあるが、リアルで斬新! ぜひこれ以上の情報を入れずに驚きとスリルを感じてほしい。
この先は鑑賞後の読者へ。男性のなかには「アンフェアだ」と感じる人がいるかもしれないが、そうだろうか? キャシーは女性の代弁者かもしれないがヒーローではない。惨めさを自ら深掘りし続ける彼女みたいになりたいなんて、誰が思う? それにお仕置きは男性だけではなく、無自覚に罪を犯した女性たちにも及んでいる。
一番グッと来たのは、観客の想像力に委ね、感情を揺さぶる描写力だ。ニーナは登場しないし回想シーンもない。だが、ずっと強く感じていたのはこれがキャシーとニーナのラブ・ストーリーだということ。純粋な友愛だったのだろうが直接描かず、その深さを観客が想像できるように導いて余韻を残す。現在進行形で初恋のように燃え上がるライアンへの恋心さえ、適わない愛……。すべてのなりゆきと結果は、愛ゆえなのである。
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド(2019)
| 監督 | クエンティン・タランティーノ |
| 評価 | 3.93 |
解説
『ジャンゴ 繋がれざる者』のレオナルド・ディカプリオ、『イングロリアス・バスターズ』のブラッド・ピットとクエンティン・タランティーノ監督が再び組んだ話題作。1969年のロサンゼルスを舞台に、ハリウッド黄金時代をタランティーノ監督の視点で描く。マーゴット・ロビー、アル・パチーノ、ダコタ・ファニングらが共演した。
あらすじ
人気が落ちてきたドラマ俳優、リック・ダルトン(レオナルド・ディカプリオ)は、映画俳優への転身に苦心している。彼に雇われた付き人兼スタントマンで親友のクリフ・ブース(ブラッド・ピット)は、そんなリックをサポートしてきた。ある時、映画監督のロマン・ポランスキーとその妻で女優のシャロン・テート(マーゴット・ロビー)がリックの家の隣に引っ越してくる。
映画レポート
クエンティン・タランティーノ9本目の監督作は、その題名が示す通り、これまでの彼の作品以上に彼が愛する映画の世界に至近距離で寄り添い、彼の趣味を全編に散りばめながら、思いを馳せ、懐古し、創造し、妄想する60年代ハリウッドへの挽歌にして極私的グラフィティ。
舞台はその栄光に陰りが見え始めていた69年のハリウッド。主人公はレオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットが演じるマカロニ・ウエスタンに活路を見出す落ち目のスターとそのスタントマン。タランティーノはこの2人の姿に、華麗なる成功者ではなく、スティーヴ・マックィーンやクリント・イーストウッドにはなれなかった、勝ちきれなかった者たちの悲哀を込める。
だが、タランティーノが最大の愛情を込めて描くこの映画の真の主人公は、マーゴット・ロビー演じる実在した女優シャロン・テートだ。
この50年間、マンソン・ファミリーが起こしたハリウッド史上最も凄惨な事件の被害者としてしか記憶されてこなかった一人の美しき女優を、タランティーノはスクリーンに活き活きと蘇えらせ、ロマン・ポランスキー監督と過ごした彼女の最も幸福な時を観客に共有させることで彼女を映画史にもう一度輝かせる。そして“映画の神”として、ある優しくもバイオレントな奇跡を起こすのだ。
よほどマニアックな映画ファンでなければシャロン・テートを覚えている人はいないだろう。だが、それでも自分がヒロインとして出演した「サイレンサー 破壊部隊」を映画館で見た後の満足げな彼女の美しい笑顔は涙無しには見られない。
もちろん、ハリウッド現役2トップの初共演も笑わせ、ホロリとさせ、手に汗握らせて満足度は高く、アル・パチーノ、カート・ラッセル、ブルース・ダーンといったベテランの味もガツンと効いて、映画ファンのためのお楽しみが頭から尻尾までギュっと詰まった必見のエンタテインメントである。
が、すでに各方面で言及されているように、ブルース・リーやマカロニ・ウエスタン、マンソン・ファミリーに関する描写は、あくまでもタランティーノの個人的主観で描かれるので、各分野に詳しい人から見ると“ちょっと違う”という意見も出て、公開後の賛否両論激突も必至。そのあたりは当然、タランティーノ自身も織り込み済みだろう。
ウルフウォーカー(2020)
| 監督 | トム・ムーア |
| 評価 | 4.35 |
解説
アイルランド・キルケニーに中世から伝わる伝説を基に描くアニメーション。眠ると魂が抜け出しオオカミに変身するウルフウォーカーと、ハンターの父を持つ少女の友情を映し出す。アイルランドのアニメーションスタジオであるカートゥーン・サルーンが、『ブレンダンとケルズの秘密』『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』に続くケルト3部作の完結編として製作。アカデミー賞長編アニメ賞に2度ノミネートされたトム・ムーアと、『ブレンダンとケルズの秘密』のアートディレクター、ロス・スチュワートが監督を務める。
あらすじ
中世アイルランドの町キルケニーでは、人々が森に住むウルフウォーカーについてひそかにささやき合っていた。少女ロビンは、オオカミ退治のためイングランドからハンターの父と共に、キルケニーにやって来る。ある日、父の後を追いかけて森に入った彼女は、人間とオオカミが一つの体に共存し、魔力で傷を癒やすヒーラーでもあるウルフウォーカーのメーヴと出会い、仲良くなる。
映画レポート
なんと豊かな映像だろう。キャラクターからはみ出すほどに自由な輪郭線が感情に応じて変化し、森と街の対比的で詩情豊かな色彩、ダイナミックな構図と3Dを駆使した躍動感あるカメラワークと美しい手描きアニメーションの数々にすっかり魅了されてしまった。
これまで製作した長編映画全てがアカデミー賞にノミネートされている、躍進著しいアイルランドのアニメーションスタジオ、カートゥーン・サルーンは、本作でさらに一段階上に到達した。野生のオオカミが残る中世アイルランドを舞台に、父に憧れハンターを目指す少女と、オオカミと共に生き、自らもオオカミに変身する能力を持った少女が、都市と自然の分断を乗り越え友情を育んでいく。ケルト神話から着想を得た作品で、キリスト教的人間中心主義とは異なる、かつて存在した思想の豊穣さに目を向け、人とオオカミが共に暮らせる、あり得たかもしれない世界に想いを馳せる稀有な作品だ。
主人公の少女は二重に抑圧された存在だ。狩人は男がなるもので、子どもは街の外に出ることを禁じられている。そんな抑圧的な街はモノトーン調に描かれ、対照的に森は自由を象徴するかのように豊かな色彩が広がる。対比的構図はキャラクターデザインにも表れている。町の人物たちは鋭く鋭角で、ウルフウォーカーのメーヴやその母は、丸みを帯びた包容力を感じさせるデザインになっている。この対比には、既存の人間社会の硬直さが表れている。
そして、縦横無尽のアニメーションはひとときも観客を飽きさせない。人物の感情に合わせて自由に形状を変化させる輪郭線、ヒトからオオカミへと変身してゆくメタモルフォーゼは、クラシカルなアニメーションの魅力をたっぷり持ち合わせ、3Dを駆使したダイナミックで奥行きあるカメラワークがそれに加わり、懐かしさと新鮮さを併せ持ったマジカルな映像を生み出している。
自由を求める少女たちを、自由なスタイルのアニメーションで活写し、アニメーションの豊穣さを示した傑作だ。
マリッジ・ストーリー(2019)
| 監督 | ノア・バームバック |
| 評価 | 3.88 |
解説
[Netflix作品]『イカとクジラ』『フランシス・ハ』などのノア・バームバック監督が、離婚に向かう夫婦の心情を描いた人間ドラマ。すれ違っていく結婚生活の葛藤を、夫と妻それぞれの視点で紡ぎ、ベネチア国際映画祭、トロント国際映画祭などで上映された。『スター・ウォーズ』シリーズなどのアダム・ドライヴァーと『アベンジャーズ』シリーズなどのスカーレット・ヨハンソンが夫婦を演じ、『わたしに会うまでの1600キロ』などのローラ・ダーンらが共演。
あらすじ
女優のニコール(スカーレット・ヨハンソン)と監督兼脚本家のチャーリー(アダム・ドライヴァー)は、かわいい息子がいる仲のいい家庭を築いていたが、夫婦の関係は少しずつ悪化していき、離婚を決める。円満な協議離婚を望んでいたが、ため込んできた相手への怒りを爆発させ、負けず嫌いの二人は離婚弁護士を雇って争う。
映画レポート
これは、気がつかないうちに相手を傷つけ、自らも傷を負う二人の男女の物語だ。
アダム・ドライヴァーが演じるチャーリーは、離婚調停の捜査員の目の前で思わぬ怪我をする。原因はさりげないことだったのに、その傷は深い。それは彼とニコールの別れに似ている。最初は弁護士抜きで進むはずだった離婚は拗れて泥沼にはまっていく。二人でレンタカーの後部座席にチャイルド・シートを取り付ける。お酒に酔ってよろめいたニコールをチャーリーが受け止める。それは離れていく二人がお互いに見せた思いやりの身振りだったはずだが、離婚調停の場でそれぞれの弁護士の手に渡ると、安全だったジェスチャーは互いにとって命取りの武器となる。行き違い、誤解、遠慮、我がまま。結婚の土台を少しずつ崩していった小さな傷が次々と明らかになっていく。
これは、男性と女性、家庭と仕事、ニューヨークとロサンゼルス、創作者と演技者のパワー・バランスについての映画でもある。
ハリウッドの新進女優だったニコールは自らキャリアの舵を切ってチャーリーとの劇団の仕事を選んだはずだった。しかし月日が経って彼女に残ったのは「(自分が)夫の才能に寄与してしまった」という想い。映画はチャーリーとニコール、双方の視点を行き来するが、ニコールの本来の足場であるロサンゼルスで話が展開することが多い。親権の確保のために劇団の仕事を離れ、ロスに部屋を借りざるを得ないチャーリーは、自分の場所を奪われたニコールの孤独を追体験する。
これは、私小説的な作品を作ってきたノア・バームバックらしい映画だ。「イカとクジラ」で両親の離婚に対する少年の想いを“大人は分かってくれない”という映画として撮った青年は、自らの離婚を下敷きに、別れていく父母の事情と想いを知り得ない八歳の少年を主人公夫婦の間に置いて、“子供は分かってくれない”という映画を撮る円熟した中年になった。
大人になったバームバックは、家庭を失った男の視点だけで物語を描くようなことはしない。チャーリーに、ニコールが最後に見せる優しさ。それは偶然にも、演じるスカーレット・ヨハンソンが「ジョジョ・ラビット」(19)でも見せたジェスチャーと重なる。一つの身振りが一人の女優によって二つの映画で繰り返されることで、観客にとってそれは愛の行為として刻まれることになる。
そして気がつく。これは離婚ではなく、結婚の物語なのだと。
Mank/マンク(2020)
| 監督 | デヴィッド・フィンチャー |
| 評価 | 3.47 |
解説
[Netflix作品]『市民ケーン』の脚本家、ハーマン・J・マンキウィッツを主人公にした人間ドラマ。黄金期のハリウッドを背景に、「マンク」と呼ばれた脚本家がアルコール依存症に苦しみながらも、後に名作となる脚本を仕上げる。『ソーシャル・ネットワーク』などのデヴィッド・フィンチャーが監督を手掛け、『ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男』などのゲイリー・オールドマンが主人公を演じ、『マンマ・ミーア!』シリーズなどのアマンダ・セイフライドや、『あと1センチの恋』などのリリー・コリンズらが共演している。
あらすじ
社会を鋭く風刺するのが持ち味の脚本家・マンク(ゲイリー・オールドマン)は、アルコール依存症に苦しみながらも新たな脚本と格闘していた。それはオーソン・ウェルズが監督と主演などを務める新作映画『市民ケーン』の脚本だった。しかし彼の筆は思うように進まず、マンクは苦悩する。
映画レポート
「ゴーンガール」(14)以来6年ぶりとなる監督デヴィッド・フィンチャーの新作は、自身のフィルモグラフィ初のオンライン動画サービスを主発信とする長編であり、そして初のモノクロなど特色づくしだ。加えて実在人をベースとする久々の伝記として、1941年の映画「市民ケーン」に対する創造の疑問、すなわち「誰がこの名作を生み出しだのか?」にひとつの回答を提示する。
本作はそんな歴史的傑作の脚本を手がけた“マンク”ことハーマン・J・マンキウィッツ(ゲイリー・オールドマン)を主人公に、その執筆過程を描いたものだ。作家性という観点から「市民ケーン」は、主に監督・主演を務めたオーソン・ウェルズの功績と認識されている。だがマンクがクレジットの権利を契約上破棄したことから、真の貢献者を問う議論をたびたび起こしてきた。
「Mank マンク」はこの「市民ケーン」問題に主眼を寄せ、マンキウィッツと表題キャラのモデルとなったメディア王ウィリアム・R・ハーストとの接触や、彼を取り巻く30?40年代ハリウッドのスタジオ勢力、ならびに政治的な動向に推論を行き渡らせ、マンクの同作への開発動機をあぶりだす。こうした作りが結果として、観る者の興味を引くのに充分な、才能豊かだが一筋縄でない脚本家の半生をあらわにしていく。
先進的な作り手であるフィンチャーにしてはネタが古風だが、もともと「Mank マンク」の脚本は自身の父親の遺稿で、長いこと映画化が塩漬けにされてきた。そんな経緯を踏まえれば、作品は一見、肉親への義理を果たした感が強い。だが自作「ソーシャル・ネットワーク」(11)では、他者と繋がろうとすればするほど孤独に陥るマーク・ザッカーバーグ(Facebook創設者)の顛末を「現代の『市民ケーン』」と評され、フィンチャー自身も監督デビュー作「エイリアン3」(92)でスタジオの意向や妨害に翻弄された身であって、決して他人事ではない題材といえよう。
なによりフィンチャーらしいのは、この映画の話法ならびに視覚への執拗なこだわりだ。それは過去と現在を行き来する非クロノジカルな構成や、名撮影監督グレッグ・トーランドの手法を模したディープフォーカスや主光源の射し込むライティングなど、「市民ケーン」に目配せしたアプローチに顕著だろう。ハリウッド黄金期のスタジオ集権体質をも冷笑する作品が、新時代のメディア覇王Netflixから配信されるというのもシャレが効き過ぎていて可笑しい。
ペイン・アンド・グローリー(2019)
| 監督 | ペドロ・アルモドバル |
| 評価 | 3.77 |
解説
『トーク・トゥ・ハー』などのペドロ・アルモドバル監督がメガホンを取ったドラマ。生きがいを失った映画監督が、自身の過去と向き合う。『チリ33人 希望の軌跡』などのアントニオ・バンデラスが主演を務め、『あなたのママになるために』などのアシエル・エチェアンディア、『エンド・オブ・トンネル』などのレオナルド・スバラーリャのほか、ノラ・ナバス、フリエタ・セラーノ、ペネロペ・クルスらが共演した。
あらすじ
サルバドール(アントニオ・バンデラス)は世界的な映画監督として活躍していたが、脊椎の痛みで心身共に疲弊し、引退同然の生活を送っていた。彼は、母親のことや幼少期に引っ越したスペイン・バレンシアでの出来事など、過去を回想するようになる。あるとき、32年前に撮った作品の上映依頼が舞い込む。
映画レポート
初期の狂気をはらんだエキセントリックで倒錯的な作風から、近年は、瞑想風で思索的な深みをたたえた、ヒロインを礼讃する〈女性映画〉の秀作を連作するに至ったペドロ・アルモドバルは文字通り、ヨーロッパを代表する巨匠といってよい。そのアルモドバルが70歳を迎えて自伝的なモチーフに挑んだのが「ペイン・アンド・グローリー」である。主人公の映画監督サルバドール(アントニオ・バンデラス)は世界的な名声を得た映画監督だが、四年前に最愛の母を亡くし、背中の激痛、片頭痛など肉体的・精神的な変調をきたし、引退同様の日々を送っている。
映画は、サルバドールがプールの底で浮遊しているシーンから始まる。明らかに母胎の羊水のなかでまどろむイメージだ。次のカットでは彼の幼少期、川辺で洗濯しながら猥雑な会話に興じる母と女たちの間で優しく庇護される光景が映し出される。アルモドバルにとって<水>は、つねに特権的な至福のイメージを形づくっている。
映画監督の苦悩と自己探求といえば、フェリーニの傑作「8 1/2」(63)を思い浮かべないわけにはいかない。実際、貧しさゆえに神学校に入れられた幼少期の記憶、映画が撮れないスランプ、精神的な危機を迎えた映画監督の魂の遍歴という主題は「8 1/2」にそっくりだ。さらに昔の恋人フェデリコ(レオナルド・スパラーリャ)と三十年ぶりに再会し、彼が別れ際に「君の映画はどれも僕の人生の〝祝祭〟だった」と呟く時、「人生は祭りだ、共に生きよう」という「8 1/2」のラストで輪舞を繰り広げる映画監督グイドの名セリフを否応なく想起させる。
だが、壮年期の映画作家の不安とその救済というフェリーニの楽天的な連帯感の表明と比べると、老境にさしかかったアルモドバルは、自らの同性愛というセクシュアリティに真摯に向き合い、鬱病を患い、迫りくる<死>の予感に絶えず脅かされている点において、作品自体はずっと苦く、屈折した、内省的なものにならざるを得ないのだ。映画の前半を覆い尽くす形容しがたい暗さは、主人公が囚われている<タナトス>の反映そのものだ。しかし、激痛から逃れるためにヘロインに手を出し、苦痛でのたうち回る満身創痍のなかで、夢想される〝初めての欲望〟の美しいエピソードから映画は一挙に艶やかな息吹を帯びる。アルモドバルにとって欲望こそが、果てしない創造力の源泉なのだ。フィクションと現実の入れ子構造を巧みに駆使したエンディングには、そんな晴れやかなアルモドバルの新境地が伺えるのである。
失くした体(2019)
| 監督 | ジェレミー・クラパン |
| 評価 | 3.71 |
解説
『アメリ』などの脚本を担当したギョーム・ローランの小説を原作にしたアニメーション。切断された手が自分の体を捜すためにパリをさまよう。『スキゼン』などの短編を手掛けてきたジェレミー・クラパン監督の長編デビュー作。アヌシー国際アニメーション映画祭でクリスタル賞と観客賞を獲得した。
あらすじ
体から切り離された手が、まるで意志を持つようにパリを縦横無尽に動き回り、もとの体の持ち主であるピザ配達人のナウフェルを求めてさすらっていた。手は、ネズミやハトに追いかけられたり、ゾッとするような体験をしたりする。さらに手が何かに触れると、ナウフェルの幼いころの思い出や恋心がよみがえる。
ミナリ(2020)
| 監督 | リー・アイザック・チョン |
| 評価 | 3.45 |
解説
『ムーンライト』などの映画スタジオA24とブラッド・ピットの制作会社プランBが組み、成功を夢見てアメリカ南部に移住した韓国系移民一家を描く人間ドラマ。さまざまな困難に直面しながらもたくましく生きる家族の物語は、サンダンス映画祭でグランプリと観客賞を受賞した。監督と脚本はリー・アイザック・チョン。『バーニング』シリーズなどのスティーヴン・ユァンが一家の父親を演じ、『春の夢』などのハン・イェリ、『チャンス商会 ~初恋を探して~』などのユン・ヨジョンらが共演する。
あらすじ
1980年代、農業で成功したいと意気込む韓国系移民のジェイコブ(スティーヴン・ユァン)は、アメリカ・アーカンソー州に家族と共に移住。広大な荒地とおんぼろのトレーラーハウスを見た妻は、夫の無謀な冒険に危うさを感じる。一方、しっかり者の長女アンと好奇心豊かな弟デビッドは新天地に希望を見いだし、デビッドは口の悪い破天荒な祖母とも風変わりな絆を育む。しかし、干ばつなどのために窮地に立たされた一家をさらなる試練が襲う。
映画レポート
ポン・ジュノ監督「パラサイト 半地下の家族」が、昨年の第92回アカデミー賞で外国語映画として史上初となる作品賞ほか4部門を獲得した衝撃は未だ記憶に新しいが、韓国文化への熱狂はその後も続いているようだ。2020年1月開催の第36回サンダンス映画祭でグランプリと観客賞を受賞した「ミナリ」は、これまでに61の受賞、185のノミネート(2月現在)を受け、世界の映画賞を席巻している。第93回アカデミー賞でも6部門にノミネートされ、波乱を巻き起こすのではないかと注目を集めている。
この作品は1980年代のアメリカ南部を舞台に、韓国出身の移民一家が理不尽な運命に翻弄されながらもたくましく生きる姿を描いた家族の物語だ。農業での成功を目指す父に「バーニング 劇場版」で印象的な演技をみせたスティーブン・ユァン、荒れた新天地に不安を抱く妻に「海にかかる霧」のハン・イェリと演技派俳優が顔を揃えた。さらに韓国で敬愛されているベテラン女優のユン・ヨジョンが毒舌で破天荒な祖母を演じ、その存在感ある演技が絶賛されている。監督・脚本は、「君の名は。」のハリウッド実写版を手掛けることでも注目を集めている韓国系アメリカ人のリー・アイザック・チョン。
しかし本作は韓国映画ではない。「ムーンライト」など話題性と作家性の強い作品で高い評価を得ているスタジオ「A24」と、「それでも夜は明ける」など良質な作品を手掛けてきたブラッド・ピットの製作会社「PLAN B」が、チョン監督の脚本にほれ込み、タッグを組んで作った映画だ。劇中の大半が韓国語であるにもかかわらず、このような強力な体制で、韓国人が主人公の企画が成立したのは、多様性が求められている昨今の社会情勢やそんな企画を探しているハリウッド事情も追い風となったのであろう。ユァンはブラピとともに製作総指揮にも名を連ねている。
アメリカにやってきた移民が主人公の映画はこれまでにも数多く作られているが、このタイミングで韓国出身の移民一家の映画が作られ、高い評価を受けているのは興味深い。だが、いつの時代も様々な困難に翻弄されながらもたくましく生きていこうとする家族の姿には人種を超えた普遍性があり、文化や価値観、宗教観の違いはあっても共感を呼ぶのであろう。アメリカの大地は美しくも厳しく、そこで生きていくには順応していくしかないが、一方でより自身のアイデンティティや同郷のコミュニティのつながり、そして神とは何かを問われることになる。
チョン監督は、葛藤する夫婦、親の子への愛、そして祖母と好奇心旺盛な孫の絆という3世代の家族を見つめ、所々にどこか懐かしく美しいカットを挿入しながら、運命に打ちひしがれても人生は続いていく貴さを描いている。祖母が請け負い、失い、そして子と孫に残すものが、静かに深い感動を呼ぶ。
バーニング 劇場版(2018)
| 監督 | イ・チャンドン |
| 評価 | 3.30 |
解説
『ポエトリー アグネスの詩(うた)』などのイ・チャンドン監督が、村上春樹の短編小説「納屋を焼く」を大胆に翻案したミステリー。小説家志望の主人公の周囲で起こる不可解な出来事を、現代社会に生きる若者の無力さや怒りを織り交ぜながら描く。主演は『ベテラン』などのユ・アイン。ドラマシリーズ「ウォーキング・デッド」などのスティーヴン・ユァン、オーディションで選ばれたチョン・ジョンソらが共演する。
あらすじ
小説家を目指しながらアルバイトで生計を立てているジョンス(ユ・アイン)は、幼なじみのヘミ(チョン・ジョンソ)からアフリカ旅行へ行くのでペットの猫を預かってほしいと頼まれる。帰国したヘミに旅先で出会ったベン(スティーヴン・ユァン)を紹介されたジョンスはある日、ベンに秘密を打ち明けられ、恐ろしい予感が頭から離れなくなる。
映画レポート
村上春樹の短編小説「納屋を焼く」を映画化し、昨年のカンヌ国際映画祭で「万引き家族」とパルムドールを競い合った韓国映画。しかも、2010年の「ポエトリー アグネスの詩」以来となるイ・チャンドン監督の久々の新作だ。そんないくつもの必見の要素が詰まった本作は、観る者の感性と解釈次第でいかようにも変容するミステリアスな作品である。
文庫本でわずか30ページの原作は独自の脚色がさまざまに施されているが、おそらくイ監督にとって最も重要だったであろうポイントは、主要キャラクターの男女3人を“今を生きる韓国の若者たち”として明確に位置づけたことだ。主人公のジョンスは母に捨てられ、父は暴力沙汰を起こして裁判中で、アルバイトで食いつないでいる。そんなどん詰まりの人生が日常化したジョンスが再会した幼なじみの女の子ヘミは、彼の心のよりどころとなるが、外車を乗り回して高級マンションで暮らす年上の青年ベンの出現によって、ジョンスのかすかな希望は打ち砕かれていく。
いわば、これは韓国における若い世代の失業や格差といった経済問題を取り込んだ三角関係の青春映画であり、イ監督は社会の底辺を漂流するジョンスの内なる鬱屈した感情を狂おしいほど生々しくあぶり出す。ところが本作がいっそう興味深いのは、原作小説に欠落していたその狂おしさがひたすら空転し、ジョンスとともに観る者を不穏に謎めく映画的迷宮の奥底へと引きずり込んでいくことだ。至るところにちりばめられたメタファーと伏線。例えば、そこに“ない”ものを“ある”ように見せかけるパントマイムをめぐる禅問答のようなエピソードは、現実と虚構の境界線が曖昧なメタ構造を持つこの映画の特異性を象徴する一方、生きる意味とは何かという深遠なテーマのヒントを仄めかしているようにも読み取れる。
また中盤過ぎには、夕暮れ時の淡い光と闇が溶け合ったマジックアワーの素晴らしい長回しショットがあるのだが、その場面を転換点としてストーリーが激しく捻れ出す。3人の登場人物のうち、ひとりが突然消失してしまう謎。そして納屋ならぬビニールハウスを定期的に焼くのが趣味だと言い放つベンの謎。この一見関連性のないふたつのミステリーが脳内で結びついたとき、視界不良の霧の中にさまよい込んだ私たち観客は、それぞれ朧気な“答え”を夢想することができる。先にNHKにて吹替で放映された短縮バージョンでは終盤がばっさりカットされていただけに、ぜひともこの劇場版の底知れなく深い迷宮に身を委ねてほしい。
行き止まりの世界に生まれて(2018)
| 監督 | ビン・リュー |
| 評価 | 3.86 |
解説
かつて繁栄したものの今は衰退した、アメリカの「ラストベルト(錆びついた工業地帯)」を舞台にしたドキュメンタリー。鬱屈(うっくつ)した思いをスケートボードにぶつけ、成長していく3人の若者の姿を映し出す。今回出演も果たすビン・リューが監督・製作・撮影・編集を担当し、キアー・ジョンソン氏とザック・マリガン氏らが共演。第91回アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞と、第71回エミー賞の「Outstanding Documentary Or Nonfiction Special」などにノミネートされた。
あらすじ
家庭環境に恵まれないキアー・ジョンソン氏、ザック・マリガン氏、ビン・リュー監督の3人の若者は、イリノイ州ロックフォードで暮らしている。厳しい現実から逃れるようにスケートボードに熱中する彼らにとって、スケート仲間はもうひとつの家族であり、ストリートこそが自分たちの居場所だった。やがて彼らも成長し、目の前に立ちはだかるさまざまな現実に向き合う時期がやって来る。
映画レポート
“名もなき市井の人”を描く――そんな触れ込みの映画がこれまでに何万本作られてきただろう。しかしフィクションであってもドキュメンタリーであっても、作り手の視点が介在する限り、100%純粋な現実に近づくことは難しい。
しかしアカデミー賞候補にもなったこのドキュメンタリー映画は、限りなく本物の現実を映すことに成功しているように思える。なぜなら“名もなき市井の人”である当事者が監督し、(最初はたまたま)自分たちに12年間カメラを向け続け、しかもドキュメンタリー作家に必要な観察眼を備えていたという、奇跡のようなめぐり合わせで生まれた作品だからだ。
中国系移民のビン・リューは、荒廃した人口15万人の町ロックフォードで、スケートボード仲間とスケートビデオを撮影する少年だった。やがてリューは町を出て映画業界で働き始めるのだが、地元の仲間たちのことも撮影し続けていた。スケートビデオは、いつしか仲間たちの人生を追うドキュメンタリー映画に発展していく。
主人公に選ばれたのは、父親に暴力を振るわれている黒人の少年キアーと、仲間の中でカリスマ的な存在だった若者ザック。ザックはガールフレンドとの間に子供が生まれ、懸命にいい父親になろうとしていた。少なくとも最初のうちは……。
この作品がどんな形に仕上がるのか、監督も含め誰もわかっていなかっただろう。しかし一緒に育った仲間であるリュー監督の前で、キアーやザックは飾らぬ本音を語り、時にみっともない姿もさらけ出す。そして「家庭内の暴力の連鎖」というテーマに踏み込んだことで、リュー監督は自分自身や母親にもカメラを向ける決意をしたという。彼自身も継父の家庭内暴力に苦しんだ当事者だったからだ。
筋書きのない人生を映しているから、この映画に明快なストーリーやゴールはない。タイムカプセルのようにかけがえのない瞬間を封じ込めている、と言えば聞こえはいいが、聡明なリュー監督は、自分たちをノスタルジーで包んで美化しようとはしない。
例えば仲間たちがフザケて黒人をネタに冗談を飛ばしている時、カメラはキアーの複雑な表情を見逃さない。輝くような青年だったザックの凋落からも目をそらしたりはしない。自分たちの未来は不安定で、善悪の境目は限りなく曖昧で、すべては道半ば。しかしそれでも、友情や希望のかけらは残っている。変化する人間関係と流れていく時間を描いた、とても正直で知的で優しい映画だと思う。
ファーザー(2020)
| 監督 | フロリアン・ゼレール |
| 評価 | 4.01 |
解説
世界中で上演された舞台を映画化したヒューマンドラマ。年老いた父親が認知症を患い、次第に自分自身や家族のことも分からなくなり、記憶や時間が混乱していく。原作を手掛けたフロリアン・ゼレールが監督と脚本を担当し、『羊たちの沈黙』などのアンソニー・ホプキンスが父親、『女王陛下のお気に入り』などのオリヴィア・コールマンが娘を演じ、『SHERLOCK/シャーロック 忌まわしき花嫁』などのマーク・ゲイティスや、『ビバリウム』などのイモージェン・プーツらが共演する。
あらすじ
ロンドンで独りで暮らす81歳のアンソニー(アンソニー・ホプキンス)は、少しずつ記憶が曖昧になってきていたが、娘のアン(オリヴィア・コールマン)が頼んだ介護人を断る。そんな折、アンが新しい恋人とパリで暮らすと言い出して彼はぼう然とする。だがさらに、アンと結婚して10年になるという見知らぬ男がアンソニーの自宅に突然現れたことで、彼の混乱は深まる。
映画レポート
気丈な親が、まるで子供のように振る舞い自分を頼るようになる。親子の関係が逆転していくことへの戸惑い、せつなさ、思いの通じないもどかしさ。認知症の家族を持ったことがある人にとっては、きっとよく知る感情に違いない。
下馬評通りアンソニー・ホプキンスがアカデミー賞主演男優賞に輝いた本作は、記憶を失って行く父と、人生の再スタートを切ろうとしている娘の物語だ。自身の著名な戯曲を自ら映画化して監督デビューを果たしたフロリアン・ゼレールは、人間が老いる上で避けられない問題を、親子の絆を通して見つめる。
ホプキンスはこの主人公アンソニーを、彼自身に大きなトラウマを与えた父親を思い出しながら演じたという。あるときはおどけてダンスを踊るかと思えば、次の瞬間、人が変わったかのように不機嫌で攻撃的になる。その驚くべき演技は、悲しみのみならず、ユーモア、軽妙さ、はたまた恐れ、ノスタルジー、悔恨といった感情の幅を自在に行き来する。
ゼレールの脚本が巧みなのは、そこにもうひとつ「過去の亡霊」というテーマを加えることで、親子の関係を一層複雑なものにしたことにある。娘のアンには、じつは亡くなった妹のルーシーがいて、彼女の方が父のお気に入りだった。彼の頭のなかでは、ルーシーはいまだ世界のどこかを旅している。屈辱と憎しみ。アンは父に対する愛憎の狭間で揺れ動く。それを巧みに表現するオリヴィア・コールマンもまた、控えめながらホプキンスに劣らぬ名演を見せている。
もっとも、本作が欧米でこれほど評価された大きな理由は、その映像スタイルにあるだろう。ゼレール監督はこれが一作目とは思えないほど鮮やかに、演劇的な要素を映像的な表現に切り替えている。とくにアンソニーの頭のなかの混乱を、時間感覚が麻痺するようなシチュエーションの反復を用いたり、ふたりの俳優に同じ役を演じさせ他者の認識を曖昧にすることで観客に体感させるのだ。まったく見知らぬ人間が居間にいて、娘の夫だと名乗るかと思えば、見慣れぬ女が娘として振る舞い、夫などいないと主張する。不条理で不確かな世界に身を置く恐怖が、ひしひしと伝わって来る。
結局のところ老いは誰にとっても避けられないものであり、どう老いていくかなど知る由もない。そんな手に負えない難題を冷徹に、しかし細やかな配慮と慈しみをもって描き出す本作は、心に重い錨を降ろす。
ノマドランド(2020)
| 監督 | クロエ・ジャオ |
| 評価 | 3.81 |
解説
ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション小説を原作に、「ノマド(遊牧民)」と呼ばれる車上生活者の生きざまを描いたロードムービー。金融危機により全てを失いノマドになった女性が、生きる希望を求めて放浪の旅を続ける。オスカー女優フランシス・マクドーマンドが主人公を演じ、『グッドナイト&グッドラック』などのデヴィッド・ストラザーンをはじめ、実際にノマドとして生活する人たちが出演。『ザ・ライダー』などのクロエ・ジャオがメガホンを取り、第77回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で金獅子賞を獲得した。
あらすじ
アメリカ・ネバダ州に暮らす60代の女性ファーン(フランシス・マクドーマンド)は、リーマンショックによる企業の倒産で住み慣れた家を失ってしまう。彼女はキャンピングカーに荷物を積み込み、車上生活をしながら過酷な季節労働の現場を渡り歩くことを余儀なくされる。現代の「ノマド(遊牧民)」として一日一日を必死に乗り越え、その過程で出会うノマドたちと苦楽を共にし、ファーンは広大な西部をさすらう。
映画レポート
放浪生活への憧れは、アメリカの西部開拓時代からの伝統と言えるかもしれない。古くは「野性の呼び声」「マーティン・イーデン」で知られる作家ジャック・ロンドン、50年代には、「路上」でビート・ジェネレーションを代表したジャック・ケルアック、最近では映画「イントゥ・ザ・ワイルド」のモデルで、アラスカで命を落とした青年、クリス・マッキャンドレスがいた。
前作「ザ・ライダー」で、中西部に生きる現代のカウボーイの姿を描いたクロエ・ジャオ監督も、そんな憧れを持つひとりである。
だが、ジェシカ・ブルーダー原作の映画化である「ノマドランド」は、ロマンチックな放浪の夢とは趣を異にする。主人公のファーンは会社の倒産で職を失い、病で夫も亡くした61歳の女性。彼女は致し方なく、愛着のあるぽんこつキャラバンに夫との思い出の品を積み、当てのない旅に出る。生活のため、ところどころで季節労働をするうちに、自分の意志でノマド生活をする「ホームレスではなくハウスレス」な人々と出会い、新しい世界を発見する。
ジャオ監督は前作と同じ手法で、実際のノマドたちを「起用する」というよりは、彼らの生活にとけ込み、その横顔をカメラに収めた。そのなかに混じったフランシス・マクドーマンドもまた、演技ではなく、そこにただ存在し、ノマド生活を営んでいる。その佇まいはフィクションとドキュメンタリーの境界を超え、もはや観る者の先入観も消し去るほど、真実を差し出す。役を生きるとは、こういうことなのだろう。
自分の生き方を貫くことは生易しいことではない。とくにそれが現代社会の慣習に反するようなものなら、なおさらだ。ノマドたちは、「この生活の素晴らしいところは最後の“さよなら”がないから。“また路上で会おう”と言うだけ」と語るが、それはまた、死に際に誰にも看取ってもらえない可能性もあるということだ。否、圧倒的にその確率の方が高い。
だから自ら辺境の人生を選ぶのなら、何があっても後悔しないような覚悟がいる。この映画は、そんなノマド生活の厳しさも十分に掬い取った上で、それでも、そこにある何かかけがえのないロマンを謳いあげる。
ファーンはひとり、静けさに満ちた神秘的な岩山や、激しい風雨の吹き付ける海岸に佇む。ときに神々しい美しさをたたえ、圧倒的な力に満ちた自然の前で、彼女は無力でちっぽけであり同時に、自由で、大地と繋がった存在でもある。
現代におけるノマド生活を通して、人間の生きる意味とは何なのか、といった本質的なテーマに思いを至らせる、それが本作の底知れない力だ。
パラサイト 半地下の家族(2019)
| 監督 | ポン・ジュノ |
| 評価 | 4.04 |
解説
『母なる証明』などのポン・ジュノが監督を務め、第72回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した人間ドラマ。裕福な家族と貧しい家族の出会いから始まる物語を描く。ポン・ジュノ監督作『グエムル -漢江の怪物-』などのソン・ガンホをはじめ、『新感染 ファイナル・エクスプレス』などのチェ・ウシク、『最後まで行く』などのイ・ソンギュンらが出演。
あらすじ
半地下住宅に住むキム一家は全員失業中で、日々の暮らしに困窮していた。ある日、たまたま長男のギウ(チェ・ウシク)が家庭教師の面接のため、IT企業のCEOを務めるパク氏の豪邸を訪ね、兄に続いて妹のギジョン(パク・ソダム)もその家に足を踏み入れる。
映画レポート
世界共通の社会問題である“貧富の格差”は、映画界においても多くの著名監督たちがそれぞれの切り口で追求しているテーマだ。カンヌ国際映画祭パルムドールに輝き、全米賞レースでも猛烈な勢いで外国語映画賞を総なめにしている「パラサイト 半地下の家族」は、おそらく映画史上最も鮮烈に“格差”の視覚化に成功した作品だろう。
全員失業中のキム一家は、日当たりが悪く不衛生で、WiFiの電波もろくに届かない半地下住宅で暮らしている。一方、高台の豪邸に住んでいるIT社長のパク一家は、勝ち組を絵に描いたような大富豪。キム家の息子が身分を詐称してパク家の娘の家庭教師になったことをきっかけに、ふたつの家族の人生が交錯していくという物語だ。両家の途方もない格差を象徴する“家”のデザインにこだわったポン・ジュノ監督は、思うがままのカメラワークを駆使した空間演出のタクトをふるうべく、このふたつの主要舞台の大規模なオープンセットを建造して撮影を行った。
悪意なき貧乏人であるキム一家には、パク一家への恨みなど一切ない。手荒い手段で財産を奪う“侵略”ではなく、密かにまとわりついて幸せという名の養分を吸い取る“寄生”が彼らの狙いだ。「パラサイト」とは、何とうまく的を射たタイトルだろう。ユーモアとサスペンスを変幻自在に操るポン監督は、中盤の意外なほど早いタイミングで達成されるパク一家のパラサイト計画のプロセスを、痛快なブラック・コメディに仕立ててみせた。
壮大などんでん返しが待ち受けるその後の展開はジャンルもトーンも一変し、クライマックスに向かって怒濤のスペクタクルが炸裂する。ポン監督のさらなる格差の視覚化を成す重要なエッセンスは“雨”と“階段”だ。もしも災害レベルの豪雨が降ったら、半地下住宅と高台の豪邸のどちらが甚大な被害を被るかは一目瞭然。そして極めて映画的な装置である階段は、本作に隠されたもうひとつの階層の存在をあぶり出すシークエンスで絶大な威力を発揮する。その暗黒の異界への扉が開かれた瞬間、寄生する者とされる者の構図は激しくねじ曲がり、パラサイト計画の行く末は予測不能のカオスと化していく。
そのほか“桃”や“体臭”などポン監督の尋常ならざるディテール描写が冴えるモチーフはいくつもあるが、娯楽性満点の本作のエンディングは決して爽快ではない。格差というものの恐ろしい断絶の視覚化までも試みたこの映画は、ほの暗い複雑な余韻となって、鑑賞後も私たち観客の心にパラサイトしてくるのだ。
ソウルフル・ワールド(2020)
| 監督 | ピート・ドクター |
| 評価 | 4.12 |
解説
[配信作品]生まれる前にどんな人間になるかを決める「魂(ソウル)の世界」をテーマにした、ディズニー&ピクサーによるアニメ。青くかわいらしい姿をした「ソウル」たちが存在する世界に迷い込んだ音楽教師が、自分のやりたいことを見つけられずにいるソウルに出会う。監督は『モンスターズ・インク』や『インサイド・ヘッド』などのピート・ドクター。共同監督をドラマシリーズ「スター・トレック:ディスカバリー」の脚本に携わったケンプ・パワーズが務める。
あらすじ
ジャズピアニストになることを夢見る音楽教師のジョーに、ニューヨークのジャズクラブで演奏するチャンスが巡ってくる。しかし喜びもつかの間、彼はマンホールに落ちてしまう。そこには青くかわいい姿の魂(ソウル)たちの世界が広がり、人間として生まれる前にどんな自分になるかを決めていた。夢を追い続けるジョーがそこで出会ったのは、自分がどのようになりたいかを決められない「ソウルの22番」だった。
映画レポート
ピクサー作品は、見ていて「こういうオチになるだろうな」と予想する一歩先を見せてくれることが多い。ファミリー映画のジャンルのなかで人生の深みを感じさせる描写をさらっと描き、手垢のついた教訓や結末とは異なるフレッシュなエンディングで見る人をうならせる。多くの頭脳によって考えぬかれたストーリーの妙に、どうやってこの話を思いついたのだろうと驚かせてくれる。
11才の少女の感情をキャラクター化した「インサイド・ヘッド」で、ネガティブにとらえられがちなある感情をポジティブに描いた(これにも驚かされた)ピート・ドクター監督が選んだ舞台は、人間が生まれる前の「ソウル(魂)」の世界。中年男性のジョーと、人間の世界に興味がもてない22番と呼ばれるソウルが、バディとなって現実世界とソウルの世界を行き来する。
ジャズミュージシャンになる夢を叶える寸前にソウルの世界に迷い込み、なんとしても現実世界に帰りたいジョーと、夢中になれる「人生のきらめき」を見つけられず現実世界に出たくない22番。音楽に夢中で生きてきたジョーに感化された22番は人間的成長をとげ、ジョーは現実世界で念願のミュージシャンへの道を歩みはじめる――予告編や本編の途中まで見て思い描くストーリーの一歩先を本作では見せてくれる。
この映画を見た人は、ジョーが夢見たライブでの演奏シーンよりエモーショナルに描かれる、ある日常の場面にハッとさせられたはずだ。何かに夢中になることが必ずしも人生の目的ではないことを圧倒的な映像力で見せ、人生のメンター(指導者)であるジョーは、単なる生活の一部だと思っていた日々の日常にこそ「人生のきらめき」が宿っていることを、人生の後輩である22番から教えられる。明石家さんまの名言「生きてるだけで丸儲け」を思わせる人生賛歌にたどりつく物語と、この物語が観客に届くと信じたピクサーの心意気に、私も少し人生が変えられた気がした。
マ・レイニーのブラックボトム(2020)
| 監督 | ジョージ・C・ウルフ |
| 評価 | 3.37 |
解説
[Netflix作品]『フェンス』の原作者でピュリッツァー賞を2度受賞した劇作家オーガスト・ウィルソンの戯曲を映画化。伝説的歌手のレコーディングの過程で、歌手や野心的なバンドメンバーが火花を散らす。オスカー女優ヴィオラ・デイヴィス、『ブラックパンサー』などのチャドウィック・ボーズマンのほか、グリン・ターマン、コールマン・ドミンゴらが出演。『フェンス』に出演したデンゼル・ワシントンがプロデューサーに名を連ね、『サヨナラの代わりに』などのジョージ・C・ウルフが監督を務めた。
あらすじ
1927年のシカゴ。ある録音スタジオで「ブルースの母」と称される歌手マ・レイニー(ヴィオラ・デイヴィス)のレコーディングが行われようとしていた。彼女の到着を待つバンドメンバーの間にはもめ事の火種がくすぶり、マ・レイニー自身も白人のマネジメント陣と楽曲制作の主導権をめぐり激しく対立する。一方、野心的な若きコルネット奏者レヴィー(チャドウィック・ボーズマン)は音楽業界で自らの実力を示そうと燃えていた。
映画レポート
昨年8月、チャドウィック・ボーズマンが逝去した。彼の演じた数々のレジェンドに比べると本作の役どころは小さな存在に思える。だが「Black Lives Matter」を経て大きなうねりの渦中にある今、ボーズマンが病を押して挑んだ最後の役柄“トランペット吹きのレヴィ”がアフリカ系アメリカ人文化を代表するキャラクターとして記憶に刻まれるのは確実だろう。
原作はオーガスト・ウィルソンによる戯曲シリーズのひとつ。かつてデンゼル・ワシントンが主演、監督を務めた「フェンス」(16)もこの中の一作にあたるが、今回は彼がプロデュースに徹し、ブルースの女王がシカゴのスタジオに招かれ、依頼主やバックバンドとすったもんだを繰り返しながらレコーディングを行う“たった数時間の人間模様”を濃密に描く。
なぜこれがアフリカ系アメリカ人文化にとって重要なのか。それを理解する上では、こちら側から率先して彼らの目線へと飛び込んでいく必要がある。そうやって初めて、バンドメンバーが交わすリズミカルな言葉の中に、彼らのルーツや人生観、日常的な差別、搾取、暴力、さらには「我々は何者で、どこへ向かうのか」という精神性までもが星屑の如く散りばめられていることに気づくはず。
そこへ“マ・レイニー”が到着すると緊張とうねりは最高潮に達する。彼女の威厳たっぷり、いや、威圧的で高慢とも言える要求の数々はかなり強烈だ。かと思えば、なぜ自分がそのように振る舞うのかという心境が赤裸々に語られ、彼女の一側面ばかりを見つめていた我々の固定観念は大きく揺さぶられる。
一方の“レヴィ”も複雑なキャラクターだ。彼は天下を取るという野心を抱きつつ、しかし過去の記憶が心に影をもたらしている。その上、“靴”や“扉”というメタファーを挟み込むことで他のメンバーとの生き方や考え方の違いは際立ち、一見するとシンプルな本作は、多様性と多面性を伴って奥深さを増していく。こういったリアルな声によって織りなされた映画が生まれること自体がマイノリティにとって一つの大きな達成であるし、彼らの目線に寄り添うことは観る側にとっても意義深い機会となろう。
そしてエンドクレジットで胸をよぎるのはやはりボーズマンのことだ。キャリアを通じての影響力、ひいては本作に注目が集まることによって、映画界は多様性と尊厳を持って進化していくはず。その意味で、彼は文化的なヒーローでもあったことをいま改めて強く噛みしめたい。
アポロ11 完全版(2019)
| 監督 | トッド・ダグラス・ミラー |
| 評価 | 4.11 |
解説
アメリカ国立公文書記録管理局(NARA)とアメリカ航空宇宙局(NASA)によって発掘されたアポロ11号にまつわる秘蔵映像と音源をまとめたドキュメンタリー。人類史上初めて月に着陸する前後9日の様子が、ナレーションやインタビューなしの4Kリマスター映像で映し出される。監督をトッド・ダグラス・ミラーが務めた。本作は科学館・博物館限定公開の『アポロ11:ファースト・ステップ版』の長尺版。
あらすじ
1969年7月20日、宇宙船アポロ11号は月面着陸を達成する。それから時は経ち、アメリカ国立公文書記録管理局(NARA)とアメリカ航空宇宙局(NASA)が、70ミリフィルムのアーカイブ映像や1万1,000時間以上もの音声データを新たに発見する。そこには飛行士たちが宇宙服を着用する姿やミッション完了後に回収船に乗り込む様子、リチャード・ニクソン大統領の姿などが記録されていた。
コメント
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です。
関連記事
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】ivfree.asiaは安全?視聴方法や代わりサイトまで一気にご紹介!
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】カリビアンコムのダウンロード廃止?今なら使えるカリビアンコム動画のダウンロード方法!
- Aoi / 2023-12-26【高品質かつ安全】Supjavからアダルト動画をダウンロードする方法
- Aoi / 2023-12-21【23年最新】Avgle ダウンロードの裏技を公開!簡単に高画質動画を入手~Android・iPhone/iPad・PC全環境対応
- Aoi / 2023-11-30av4.usが閉鎖!?代わりの無料アダルト動画サイトをまとめ
- Aoi / 2023-11-29【無料】TokyoMotionダウンロードする方法、その操作手順まで詳しくご紹介!(PC&スマホ)
最新記事 人気記事
Kira / 2024-09-24
【無料】ディズニー動画ダウンロード方法おすすめ|ディズニー+から映画を保存してオフラインで視聴しよう
Kira / 2024-09-24
SwitchでHuluは見れません!その理由と今後の動向を予想して裏技まで紹介します
Melody / 2024-09-24
【2023年】Huluを録画する方法!裏ワザ?真っ黒にならないソフトを紹介します
Kira / 2024-09-24
AbemaTVをダウンロード&録画できるツール7選!DRM解除できるものだけを厳選
HANA / 2024-09-24
【ABEMA ダウンロード】ABEMA(旧AbemaTV)動画をダウンロードする方法、ダウンロードできない原因と対策
youjinkin / 2024-09-24
U-NEXTで鑑賞できるおすすめアニメ作品TOP 20
Kira / 2024-09-24
U-NEXTがダウンロードできるツールトップ7!録画ソフトも
Melody / 2024-09-24
【完全保存版】U-NEXTのダウンロード方法!できない時の原因と解決法も
Tetsuko / 2024-09-24
StreamFab myFansダウンローダーの機能や使い方、評判をレビューして徹底解説!
Tetsuko / 2024-05-09
Missavの無料エロ動画をダウンロードするツール5選
展開 ∨ 折りたたみ ∧
ホットトピックス

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次
Copyright © 2024 entametalk.jp All Rights Reserved.
年齢認証

あなたは18歳以上ですか?
エンタメTALKはアダルトコンテンツを含みますので、18歳未満の方の閲覧を固くお断りいたします。
いいえ はい