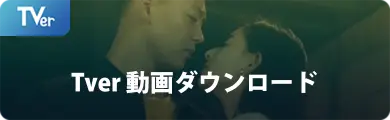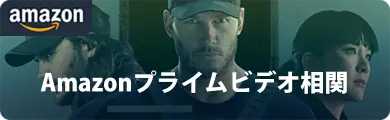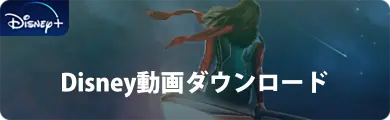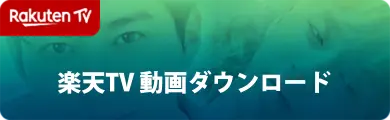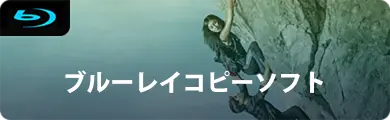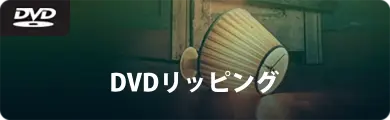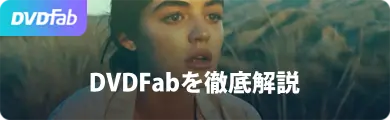StreamFab 動画 ダウンローダー
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次>
ニュー・シネマ・パラダイス(1989)
| 監督 | ジュゼッペ・トルナトーレ |
| 評価 | 4.36 |
解説
イタリアの名匠ジュゼッペ・トルナトーレによる、映画史に残る至高の名作。イタリアのシチリアを舞台に、少年と映写技師が映画を通して心を通わせていく様を、感動的な音楽と繊細な人物描写で描き出す。映画に魅了された少年トト役を、サルヴァトーレ・カシオが愛くるしい演技で演じきった。年齢を超えた友情や少年時代の夢など、世代や時代を超えた人々に愛される物語に、“映画の魔法”という名の感動が存分につまっている。
あらすじ
映画監督のサルヴァトーレ(ジャック・ペラン)は、映写技師のアルフレード(フィリップ・ノワレ)という老人が死んだという知らせを受け、故郷のシチリアに帰郷する。
映画レポート
もはや説明不要なほどに知られた、不朽の名作である。ジュゼッペ・トルナトーレが全編を通して紡ぐ映画への愛はどこまでも尊く、長きにわたり世界中の映画ファンへの問答無用のラブレターであった。1989年の第42回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で、審査員特別グランプリを受賞してから30余年。その間、世界中で様々な出来事が起きたが、映画を愛する人々にとって、そして映画を生業とする人々にとっても、今ほどこの作品を必要とする時代はないのではないだろうか。
新型コロナウイルスの感染拡大により、何もかもが変わってしまった。これまでの何気ない日常が、どれほどかけがえのないものであったかを誰もが痛感させられているはず。世界中の映画館が休業を余儀なくされている。いったい誰が、映画館のない日常を想像することが出来ただろう。
「ニュー・シネマ・パラダイス」に登場する小さな映画館「パラダイス座」は、シチリア島の小さな村の中心に位置する広場にあり、教会を兼ねている。第二次世界大戦終結直後で誰もが貧しく、楽しみといえば映画だけだった。本編には、「駅馬車」「チャップリンの拳闘」「ジキル博士とハイド氏」「風と共に去りぬ」「街の灯」「カサブランカ」「素晴らしき哉、人生!」「夏の嵐」「ならず者」「ローマの休日」など、数え切れないほどの名作が登場する。映写技師として働くアルフレードと、「トト」と呼ばれていた映画に魅了された少年サルヴァトーレの心の交流は、この場所から始まる。
今作には、大きく二分すると劇場公開版とオリジナル版が存在する。前者はパラダイス座が物語の中心として鎮座するのに対し、後者はトトの人生に主眼が置かれている。まるで趣が異なるが、その是非を論じるのは野暮というもの。トトとアルフレードの触れ合いは実に温もりにあふれ、人はひとりでは生きていけず、行動しなければ何も始まらないということを、見る者に静かに提示してくる。
火災によって失明したアルフレードが、突き放すようにトトに告げるセリフが強く胸を打つ。「今のおまえは私より盲目だ。人生はおまえが見てきた映画とは違う。人生はもっと困難なものだ。行くんだ! おまえは若い。もう、おまえとは話したくない。おまえの噂が聞きたい」。
鑑賞機会を重ねれば重ねるほど、シーンひとつひとつの持つ意味合いが染み入ってくる。少年時代のトトが映写室の小窓から覗き込んだ世界には、銀幕を食い入るように見つめる好奇心に満ちた眼差しがあった。戦後の日本が迎えた、空前の映画ブームも然り。笑いも涙も、客席に座る誰もが等しく共有できた。この光景を、失くしてはならない。冒頭で今作を「映画ファンへの問答無用のラブレター」と記述したが、いまはトトとアルフレードが鎮魂歌(レクイエム)を奏でているようにも感じられる。そう遠くない将来、人々が本当の意味で日常を取り戻すまで、そして世界中の映画館に人々が戻ってくるまで、何度だって2人が激励してくれるはずだ。
グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち(1997)
| 監督 | ガス・ヴァン・サント |
| 評価 | 4.27 |
解説
深い心の傷を負った天才青年と、同じく失意の中にいた精神分析医がお互いにあらたな旅立ちを自覚して成長してゆく姿を描く感動のヒューマン・ドラマ。ボストンに住む青年ウィルは、幼い頃から天才ゆえに周囲から孤立していた。だが、彼の才能に気付いた数学教授のランボーは、ウィルに精神分析医のショーンを紹介する。ウィルはショーンにしだいに心を開いてゆくが、彼の才能に気付いた政府機関や大企業が接近してくる。
ダークナイト(2008)
| 監督 | クリストファー・ノーラン |
| 評価 | 4.39 |
解説
映画『バットマン ビギンズ』の続編で、バットマンの最凶最悪の宿敵であるジョーカーの登場で混乱に陥ったゴッサムシティを守るべく、再びバットマンが死闘を繰り広げるアクション大作。監督は前作から続投のクリストファー・ノーラン。またクリスチャン・ベイルも主人公、バットマンを再び演じる。そして敵役のジョーカーを演じるのは2008年1月に亡くなったヒース・レジャー。シリーズで初めてタイトルからバットマンを外し、新たな世界観を広げたダークな展開に目が離せない。
あらすじ
悪のはびこるゴッサム・シティーを舞台に、ジム警部補(ゲイリー・オールドマン)やハービー・デント地方検事(アーロン・エッカート)の協力のもと、バットマン(クリスチャン・ベイル)は街で起こる犯罪撲滅の成果を上げつつあった。だが、ジョーカーと名乗る謎の犯罪者の台頭により、街は再び混乱と狂気に包まれていく。最強の敵を前に、バットマンはあらゆるハイテク技術を駆使しながら、信じるものすべてと戦わざるを得なくなっていく。
映画レポート
ジョーカーが化けた。「バットマン」第1作でジャック・ニコルソンが扮したジョーカーは「究極のオブジェ」だった。装置や衣裳が印象的だったあの映画のなかでも、ニコルソンの姿は極彩色のオブジェだった。単騎で際立つ彼の言動に、私は笑った。
「ダークナイト」ではヒース・レジャーだ。こちらのジョーカーは、観客を凍りつかせる。裂かれた口も紫の上着もずっと地味だが、その無意識はアナーキーの極致だ。広い背を丸めて邪悪の限りを尽くし、黄色い歯の間から毒に満ちた言葉を吐く。己の異形がバットマンの異形の補完物であることを自覚し、「俺はおまえを殺したくない。おまえは俺を完成させてくれるからだ」とつぶやけば、「ダークナイト」の闇とカオスは一気に深まる。
ジョーカーを通してモラルの境界で揺れる無意識を際立たせたのは、脚本の功績だ。クリストファーとジョナサンのノーラン兄弟は、白騎士デント検事(アーロン・エッカート)と黒騎士バットマン(クリスチャン・ベール)との間にもきわどい軋みを忍び込ませる。そこにジョーカーをからめた三角関係、というよりも三重衝突がこの映画の急所だ。が、哲学の深みは映画の運動感を落とさない。陰と陽と半陰陽は猛スピードで交錯し、バットポッドにまたがったバットマンは、両刃の剣と化しつつゴッサムシティの戦場を駆け抜ける。「ダークナイト」は、濃くて速くて脳髄にからみつく傑作だ。
グリーンブック(2018)
| 監督 | ピーター・ファレリー |
| 評価 | 4.49 |
解説
黒人ピアニストと彼に雇われた白人の用心棒兼運転手が、黒人用旅行ガイド「グリーンブック」を手に人種差別が残るアメリカ南部を巡る人間ドラマ。『はじまりへの旅』などのヴィゴ・モーテンセンと、『ムーンライト』などのマハーシャラ・アリが共演。『メリーに首ったけ』などのピーター・ファレリーが監督を務めた。アカデミー賞の前哨戦の一つとされるトロント国際映画祭で、最高賞の観客賞を獲得した。
あらすじ
1962年、ニューヨークの高級クラブで用心棒を務めるトニー・リップ(ヴィゴ・モーテンセン)は、クラブの改装が終わるまでの間、黒人ピアニストのドクター・シャーリー(マハーシャラ・アリ)の運転手として働くことになる。シャーリーは人種差別が根強く残る南部への演奏ツアーを計画していて、二人は黒人用旅行ガイド「グリーンブック」を頼りに旅立つ。出自も性格も違う彼らは衝突を繰り返すが、少しずつ打ち解けていく。
映画レポート
アメリカでは「ドライビング・MISS・デイジー」になぞらえて語られがちだが、それよりもテイストが似ているのはフランスのコメディ映画「最強のふたり」の方だろう。時代や人種差別の社会背景的にはもちろん前者と重なるが、この2人はもっとユーモラスで、簡単に響き合うからだ。生い立ちも性格も正反対、お互いへの嫌悪感を隠そうともしなかった白人と黒人が、徐々にお互いへの理解を深め、自分にない長所を尊重して認め合う。このプロセスを見るのは、なんて心地いいものなんだろう! ピーター・ファレリー監督はこのシンプルなドラマを素直に、丁寧に紡ぎ出し、この上なくいい気分にしてくれる。
“グリーンブック”とは50年代から60年代、人種差別の激しかった南部に旅をする黒人のために作られた施設利用ガイドのこと。1962年、イタリア移民でマフィア御用達のクラブ用心棒だったトニー・リップことバレロンガはこのガイドを渡され、イヤイヤながら新しい仕事に就くことになる。カーネギーホールに住む黒人天才ピアニスト、ドン・シャーリーの南部演奏ツアーに運転手兼ボディガートとして同行するのだ。
知的な芸術家で品がよくて繊細なのが黒人、無知なマッチョで単純かつガサツなのが白人と、従来の映画とは設定が逆なわけだが、彼らは実在の人物であり、ベースは実話。このキャラクターの描き方が面白い。ドンを演じるマハーシャラ・アリは想定内の好演だが、驚くべきはトニー役のビゴ・モーテンセン。「ロード・オブ・ザ・リング」のアラゴルンでおなじみの彼は、デンマーク生まれで哲学者のような、詩人のようなパーソナリティの持ち主なのだが、化けた。「ケンタッキーっていやぁケンタッキー・フライド・キチンだろ!」とチキンを頬張るトニーのガハハ笑いを、好きにならずにいられるか? この2人の化学反応は、映画の美点そのものと言える。
とにかくこの映画、人種差別をテーマにした作品としては、あり得ないほど口当たりがいいのである。心が痛くなるような場面もあるにはあるが、全体的には白人寄りの目線だし、スパイク・リーなら「暢気すぎるだろ!」と怒っているかもしれない。それもそのはず。だってこれはトニー・リップの息子、ニック・バレロンガがプロデュースと共同脚本を手がけ、「父から聞かされたいい話」を映画化した作品だから。つまり「いい話」を「いい話」として伝えることに重点が置かれているのだ。ここを物足りない、という人もいるだろう。しかしラストの多幸感は格別。多くの観客にとって、最高に愛すべき映画であることに間違いはない。
ゼロ・グラビティ(2013)
| 監督 | アルフォンソ・キュアロン |
| 評価 | 3.66 |
解説
『しあわせの隠れ場所』などのサンドラ・ブロックと『ファミリー・ツリー』などのジョージ・クルーニーという、オスカー俳優が共演を果たしたSFサスペンス。事故によって宇宙空間に放り出され、スペースシャトルも大破してしまった宇宙飛行士と科学者が決死のサバイバルを繰り広げる。監督を務めるのは、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』『トゥモロー・ワールド』などの鬼才アルフォンソ・キュアロン。極限状況下に置かれた者たちのドラマはもとより、リアルな宇宙空間や事故描写を創造したVFXも必見。
あらすじ
地表から600キロメートルも離れた宇宙で、ミッションを遂行していたメディカルエンジニアのライアン・ストーン博士(サンドラ・ブロック)とベテラン宇宙飛行士マット・コワルスキー(ジョージ・クルーニー)。すると、スペースシャトルが大破するという想定外の事故が発生し、二人は一本のロープでつながれたまま漆黒の無重力空間へと放り出される。地球に戻る交通手段であったスペースシャトルを失い、残された酸素も2時間分しかない絶望的な状況で、彼らは懸命に生還する方法を探っていく。
映画レポート
暗い部屋からもっと暗い次の間を覗くと、次の間が深く見える。闇が深く見えるだけでなく、奥行も深く感じられるのだ。子供のころ、私はそれが不思議でならなかった。
アルフォンソ・キュアロンも、似たような体験をしたのではないか。「ゼロ・グラビティ」を見て、私は思った。冒頭の長まわしが、闇のなかから別の闇に見入っている彼の視線を思わせる。もともと彼には「見入る」癖がある。傑作「トゥモロー・ワールド」で廃墟を凝視してみせた場面などはその好例だ。
「ゼロ・グラビティ」の設定は、みなさんご存じだろう。作業中の宇宙飛行士(サンドラ・ブロックとジョージ・クルーニー)が、地球から600キロ以上離れた空間を漂流する。重力はない。助けは来ない。声は届かない。
キュアロンは、このシンプルな設定で90分間、観客を宙吊りにする。発想の基本は「活動大写真」だ。一難去ってまた一難。序盤の快活な雰囲気は、いつしか底知れぬ悪夢へと変貌していく。ただし、この活動大写真はゲーム的ではない。「スター・トレック」に白ける私が身を乗り出したのには理由がある。
ひとつは、サンドラ・ブロックの頑健な肉体に複雑なニュアンスを帯びさせたことだ。ブロックは、腰も太腿も二の腕もたくましい。その肉体が、浮遊と漂流をつづけるうち、寂寥と絶望を滲ませていく。宇宙空間での孤立はそこまで深い。その心細さは、われわれ観客にも伝染する。漂流を体感するだけでなく、ブロックの生理まで体感してしまうのだ。もし彼女の遭難した場所が大海原や高山だったら、ここまで深い寂寥感を作り出すことはできなかったのではないか。青い光を放つ地球を背景にした宇宙空間は、3Dの大画面と文句なしに相性がよい。
グレイテスト・ショーマン(2017)
| 監督 | マイケル・グレイシー |
| 評価 | 4.28 |
解説
19世紀に活躍した伝説のエンターテイナー、P・T・バーナムを『X-MEN』シリーズや『レ・ミゼラブル』などのヒュー・ジャックマンが演じるミュージカル。空想家の主人公が卓越したアイデアと野心で世界中を熱狂させるさまと、ロマンチックな愛の物語が描かれる。監督はマイケル・グレイシー。ミシェル・ウィリアムズやザック・エフロンらが共演。『ラ・ラ・ランド』で第89回アカデミー賞歌曲賞を受賞した、ベンジ・パセックとジャスティン・ポールが音楽を担当している。
あらすじ
P・T・バーナム(ヒュー・ジャックマン)は妻(ミシェル・ウィリアムズ)と娘たちを幸せにすることを願い、これまでにないゴージャスなショーを作ろうと考える。イギリスから奇跡の声を持つオペラ歌手ジェニー・リンド(レベッカ・ファーガソン)を連れてアメリカに戻った彼は、各地でショーを開催し、大成功を収めるが……。
映画レポート
ミュージカル映画は音楽次第で古いものを新しくリノベートすることができる。つくづく音楽が持つパワーは無敵と痛感させられるのが、本作「グレイテスト・ショーマン」だ。19世紀半ばのアメリカで、人と違うルックスを持つ人間ばかりを集めた見世物ショーで大成功を収めた実在の興行師、P・T・バーナムの成功物語は、衣装やセットはもろ19世紀でも、代表的なミュージカルシーケンスはヒップホップ。8ビート、16ビートで刻まれるリズムに合わせて、バーナム役のヒュー・ジャックマン以下、メインのパフォーマーたちがキレキレのダンスを披露する。その古くて新しい感覚が、当初は戸惑う観客をいつしか不思議な幸福感で満たし始めるのだ。
今年のアカデミー主題歌賞受賞が期待されるメインテーマ“THIS IS ME”を始め、全9曲を書き下ろしたベンジ・パセック&ジャスティン・ポールの作詞作曲コンビが、前作「ラ・ラ・ランド」と同じくまたも音楽で時代を超越。それらポップな曲に連動して演じられる、360度どの位置からも歌と踊りと空中ブランコが楽しめる立体パフォーマンスは、現代最高の総合芸術“シルク・ドゥ・ソレイユ”の原型か?「グレイテスト」という謳い文句はあながちホラでもない気がする。
実物のバーナムは、興行師になる前は事業に失敗。その後、創刊した新聞で取り上げた記事が名誉毀損訴訟に発展し、訴追を受けて収監されたこともある。やはりホラ男、山師と呼ばれても仕方がない人物だった。そもそも、見た目が人と違う人間を見世物にすることが芸術と呼べるのかという疑問はある。しかし映画では、バーナムの純粋に人々を楽しませたいと願う無垢な情熱が、個性的なパフォーマーたちを劣等感から解放していくプロセスを、ストレートに抽出して行く。
そこに嫌味がないのは、一重に、ヒュー・ジャックマンが放つ“いい人オーラ”のせい。今も賛否が分かれる興行界のレジェンドを理解するため、関連の書籍を36冊読み漁り、演技の手助けにしたというジャックマン。そんな彼の情熱が役柄にも乗り移って、作品はポップで心和む最新ミュージカルとして完成したという次第。ここ数年は役作りで体も顔も過剰にマッチョ化して、まるで別人のようだったザック・エフロンも、ジャックマンにつられて古巣のミュージカルへと帰還して、何だか生き生きと楽しそうではないか!?
パラサイト 半地下の家族(2019)
| 監督 | ポン・ジュノ |
| 評価 | 4.04 |
解説
『母なる証明』などのポン・ジュノが監督を務め、第72回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した人間ドラマ。裕福な家族と貧しい家族の出会いから始まる物語を描く。ポン・ジュノ監督作『グエムル -漢江の怪物-』などのソン・ガンホをはじめ、『新感染 ファイナル・エクスプレス』などのチェ・ウシク、『最後まで行く』などのイ・ソンギュンらが出演。
あらすじ
半地下住宅に住むキム一家は全員失業中で、日々の暮らしに困窮していた。ある日、たまたま長男のギウ(チェ・ウシク)が家庭教師の面接のため、IT企業のCEOを務めるパク氏の豪邸を訪ね、兄に続いて妹のギジョン(パク・ソダム)もその家に足を踏み入れる。
映画レポート
世界共通の社会問題である“貧富の格差”は、映画界においても多くの著名監督たちがそれぞれの切り口で追求しているテーマだ。カンヌ国際映画祭パルムドールに輝き、全米賞レースでも猛烈な勢いで外国語映画賞を総なめにしている「パラサイト 半地下の家族」は、おそらく映画史上最も鮮烈に“格差”の視覚化に成功した作品だろう。
全員失業中のキム一家は、日当たりが悪く不衛生で、WiFiの電波もろくに届かない半地下住宅で暮らしている。一方、高台の豪邸に住んでいるIT社長のパク一家は、勝ち組を絵に描いたような大富豪。キム家の息子が身分を詐称してパク家の娘の家庭教師になったことをきっかけに、ふたつの家族の人生が交錯していくという物語だ。両家の途方もない格差を象徴する“家”のデザインにこだわったポン・ジュノ監督は、思うがままのカメラワークを駆使した空間演出のタクトをふるうべく、このふたつの主要舞台の大規模なオープンセットを建造して撮影を行った。
悪意なき貧乏人であるキム一家には、パク一家への恨みなど一切ない。手荒い手段で財産を奪う“侵略”ではなく、密かにまとわりついて幸せという名の養分を吸い取る“寄生”が彼らの狙いだ。「パラサイト」とは、何とうまく的を射たタイトルだろう。ユーモアとサスペンスを変幻自在に操るポン監督は、中盤の意外なほど早いタイミングで達成されるパク一家のパラサイト計画のプロセスを、痛快なブラック・コメディに仕立ててみせた。
壮大などんでん返しが待ち受けるその後の展開はジャンルもトーンも一変し、クライマックスに向かって怒濤のスペクタクルが炸裂する。ポン監督のさらなる格差の視覚化を成す重要なエッセンスは“雨”と“階段”だ。もしも災害レベルの豪雨が降ったら、半地下住宅と高台の豪邸のどちらが甚大な被害を被るかは一目瞭然。そして極めて映画的な装置である階段は、本作に隠されたもうひとつの階層の存在をあぶり出すシークエンスで絶大な威力を発揮する。その暗黒の異界への扉が開かれた瞬間、寄生する者とされる者の構図は激しくねじ曲がり、パラサイト計画の行く末は予測不能のカオスと化していく。
そのほか“桃”や“体臭”などポン監督の尋常ならざるディテール描写が冴えるモチーフはいくつもあるが、娯楽性満点の本作のエンディングは決して爽快ではない。格差というものの恐ろしい断絶の視覚化までも試みたこの映画は、ほの暗い複雑な余韻となって、鑑賞後も私たち観客の心にパラサイトしてくるのだ。
ノマドランド(2020)
| 監督 | クロエ・ジャオ |
| 評価 | 3.81 |
解説
ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション小説を原作に、「ノマド(遊牧民)」と呼ばれる車上生活者の生きざまを描いたロードムービー。金融危機により全てを失いノマドになった女性が、生きる希望を求めて放浪の旅を続ける。オスカー女優フランシス・マクドーマンドが主人公を演じ、『グッドナイト&グッドラック』などのデヴィッド・ストラザーンをはじめ、実際にノマドとして生活する人たちが出演。『ザ・ライダー』などのクロエ・ジャオがメガホンを取り、第77回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で金獅子賞を獲得した。
あらすじ
アメリカ・ネバダ州に暮らす60代の女性ファーン(フランシス・マクドーマンド)は、リーマンショックによる企業の倒産で住み慣れた家を失ってしまう。彼女はキャンピングカーに荷物を積み込み、車上生活をしながら過酷な季節労働の現場を渡り歩くことを余儀なくされる。現代の「ノマド(遊牧民)」として一日一日を必死に乗り越え、その過程で出会うノマドたちと苦楽を共にし、ファーンは広大な西部をさすらう。
映画レポート
放浪生活への憧れは、アメリカの西部開拓時代からの伝統と言えるかもしれない。古くは「野性の呼び声」「マーティン・イーデン」で知られる作家ジャック・ロンドン、50年代には、「路上」でビート・ジェネレーションを代表したジャック・ケルアック、最近では映画「イントゥ・ザ・ワイルド」のモデルで、アラスカで命を落とした青年、クリス・マッキャンドレスがいた。
前作「ザ・ライダー」で、中西部に生きる現代のカウボーイの姿を描いたクロエ・ジャオ監督も、そんな憧れを持つひとりである。
だが、ジェシカ・ブルーダー原作の映画化である「ノマドランド」は、ロマンチックな放浪の夢とは趣を異にする。主人公のファーンは会社の倒産で職を失い、病で夫も亡くした61歳の女性。彼女は致し方なく、愛着のあるぽんこつキャラバンに夫との思い出の品を積み、当てのない旅に出る。生活のため、ところどころで季節労働をするうちに、自分の意志でノマド生活をする「ホームレスではなくハウスレス」な人々と出会い、新しい世界を発見する。
ジャオ監督は前作と同じ手法で、実際のノマドたちを「起用する」というよりは、彼らの生活にとけ込み、その横顔をカメラに収めた。そのなかに混じったフランシス・マクドーマンドもまた、演技ではなく、そこにただ存在し、ノマド生活を営んでいる。その佇まいはフィクションとドキュメンタリーの境界を超え、もはや観る者の先入観も消し去るほど、真実を差し出す。役を生きるとは、こういうことなのだろう。
自分の生き方を貫くことは生易しいことではない。とくにそれが現代社会の慣習に反するようなものなら、なおさらだ。ノマドたちは、「この生活の素晴らしいところは最後の“さよなら”がないから。“また路上で会おう”と言うだけ」と語るが、それはまた、死に際に誰にも看取ってもらえない可能性もあるということだ。否、圧倒的にその確率の方が高い。
だから自ら辺境の人生を選ぶのなら、何があっても後悔しないような覚悟がいる。この映画は、そんなノマド生活の厳しさも十分に掬い取った上で、それでも、そこにある何かかけがえのないロマンを謳いあげる。
ファーンはひとり、静けさに満ちた神秘的な岩山や、激しい風雨の吹き付ける海岸に佇む。ときに神々しい美しさをたたえ、圧倒的な力に満ちた自然の前で、彼女は無力でちっぽけであり同時に、自由で、大地と繋がった存在でもある。
現代におけるノマド生活を通して、人間の生きる意味とは何なのか、といった本質的なテーマに思いを至らせる、それが本作の底知れない力だ。
アナと雪の女王(2013)
| 監督 | クリス・バック |
| 評価 | 3.66 |
解説
アンデルセンの童話「雪の女王」をヒントに、王家の姉妹が繰り広げる真実の愛を描いたディズニーミュージカル。触れた途端にそのものを凍結させてしまう秘密の力を持つ姉エルサが、真夏の王国を冬の世界に変えてしまったことから、姉と王国を救うべく妹アナが雪山の奥深くへと旅に出る。監督は、『サーフズ・アップ』のクリス・バックと『シュガー・ラッシュ』の脚本家ジェニファー・リー。愛情あふれる感動的なストーリーはもちろん、美しい氷の世界のビジュアルや個性的なキャラクター、壮大な音楽など、ファンタジックな魅力に酔いしれる。
あらすじ
エルサとアナは美しき王家の姉妹。しかし、触ったものを凍らせてしまう秘められた力を持つ姉エルサが、真夏の王国を冬の世界に変化させてしまった。行方不明になったエルサと王国を何とかすべく、妹のアナは山男のクリストフ、トナカイのスヴェン、夏に憧れる雪だるまのオラフと一緒に山の奥深くへと入っていく。
映画レポート
主題歌賞、長編アニメーション賞のオスカー2冠に輝き、全世界興収ナンバーワンアニメの座も射程圏内ときては、しばらくディズニーアニメから遠ざかっていた向きも放っておけないだろう。この大成功をもたらした最大の理由は、もちろんブロードウェイの一流スタッフ・キャストを起用して、大人も堪能できるミュージカルに仕上げたことにある。
雪の女王となるエルサ(トニー賞女優イディナ・メンゼル)がオスカー受賞曲「Let It Go」を歌い上げるなか、ディズニーならではのハイクオリティのCGアニメで氷の城が築き上げられていく壮麗さ。ディズニーアニメ初のWヒロインの対照的なキャラと苦悩を見せるアナとエルサのデュエットの重厚さ。その迫力はどれも期待以上。そうした熱唱系ナンバーで高揚させ、夏に憧れる奇妙な雪だるまオラフが歌うコミカルなナンバーで楽しませるあたりは、さすがディズニー。アメリカでは観客がスクリーンに合わせて一緒に歌える〈Sing Along Version〉が公開されて、さらに興収を伸ばしているというのも頷ける。いや、ほんと、思わず熱唱したくなる「Let It Go」の威力、恐るべし。
わかりやすい「善と悪」の対立ではなく、「愛と恐れ」を描く物語もまた巧い。ディズニー・クラシックの伝統を引き継ぐ“王子様のキス”を織り込んだり、アナと冒険をともにするオラフの無償の愛に目頭を熱くさせたりしつつ、現代社会でも数々の悲劇を生んできた「孤立」を避けるためにはどうあるべきかにも気づかせるのだ。子供も素直に楽しめる世界だが、大人ならひねりの効いたストーリーやユーモアに感心せずにいられなくなる。これでアナを取り巻く2人の男子キャラが日本人の目にもイケメンに見えるデザインだったら、女子的にも萌えだったのだが……。とはいえ、最初はアナにも不気味がられるオラフといい、それぞれの内面が伝わるキャラクターデザインはやはりお見事。今度の冬は、オラフ型の雪だるまが増えそうだ。
トップガン(1986)
| 監督 | トニー・スコット |
| 評価 | 3.91 |
解説
カリフォルニア州ミラマー海軍航空基地。そこにF-14トムキャットを操る世界最高のパイロットたちを養成する訓練学校、通称“トップガン”がある。若きパイロットのマーヴェリックもパートナーのグースとともにこのトップガン入りを果たし、自信と野望を膨らませる。日々繰り返される厳しい訓練も、マーヴェリックはグースとの絶妙なコンビネーションで次々と課題をクリアしていく。しかしライバルのアイスマンは、彼の型破りな操縦を無謀と指摘する。その一方で、マーヴェリックは新任の女性教官チャーリーに心奪われていく。
ボヘミアン・ラプソディ(2018)
| 監督 | ブライアン・シンガー |
| 評価 | 4.50 |
解説
「伝説のチャンピオン」「ウィ・ウィル・ロック・ユー」といった数々の名曲で知られるロックバンド、クイーンのボーカル、フレディ・マーキュリーの伝記ドラマ。華々しい軌跡の裏の知られざる真実を映す。『X-MEN』シリーズなどのブライアン・シンガーが監督を務めた。ドラマシリーズ「MR. ROBOT/ミスター・ロボット」などのラミ・マレック、『ジュラシック・パーク』シリーズなどのジョー・マッゼロらが出演。フレディにふんしたラミが熱演を見せる。
あらすじ
1970年のロンドン。ルックスや複雑な出自に劣等感を抱くフレディ・マーキュリー(ラミ・マレック)は、ボーカルが脱退したというブライアン・メイ(グウィリム・リー)とロジャー・テイラー(ベン・ハーディ)のバンドに自分を売り込む。類いまれな歌声に心を奪われた二人は彼をバンドに迎え、さらにジョン・ディーコン(ジョー・マッゼロ)も加わってクイーンとして活動する。やがて「キラー・クイーン」のヒットによってスターダムにのし上がるが、フレディはスキャンダル報道やメンバーとの衝突に苦しむ。
映画レポート
木村拓哉主演ドラマの主題歌となった「ボーン・トゥ・ラヴ・ユー」、数々のCMで使われている「ウィ・ウィル・ロック・ユー」「伝説のチャンピオン」などなど、もはや、クイーンの楽曲をまったく聴いたことがないという日本人はいないのではないか? 70~80年代に世界を席巻し、日本でも高い人気を誇ったロックバンド。本作はそのボーカリスト、フレディ・マーキュリーの壮絶な半生とクイーンの軌跡を描いた物語だ。これは単なる伝記ドラマという枠を超えて、彼らの曲をまったく耳にしたことがない人が観たとしても、心が引き込まれてしまうに違いない王道エンターテインメントとして完成している。
インド系移民という複雑な出自と容姿によってコンプレックスまみれだったフレディが、個性あふれる仲間たちとともに、己の流儀を貫くことによって世界的バンドへと飛躍していく。どうだろう、「ロッキー」や「ザ・エージェント」ほか、私たちが大好きでグッとくる傑作ストーリーそのものじゃないか。さらに、エイズ発症によって死去したフレディのセクシャリティからも目を背けず、彼の苦悩や葛藤にも深く踏み込む。心から愛しながらも、決して添い遂げることはできなかった恋人メアリーとの関係性に、胸を痛める観客も多いはずだ。
圧巻は、死期を察したフレディが堕落から這い上がり、仲間たちとともに上がる20世紀最大のチャリティ・イベント“ライブ・エイド”のステージ。本当の安らぎと絆を得たフレディが挑む、7万5000人の観衆が埋め尽くすスタジアムでの命懸けのパフォーマンス。伝説的ライブのスペクタクルが、映画館をスタジアムの一角に変える。
そして、数々の名曲の誕生エピソードにも注目。タイトルになった“英国史上最高のシングル”「ボヘミアン・ラプソディ」のシーンはその最たるもので、周囲の反対を押し切り、独創的な手法で制作した楽曲がNo.1ヒットを勝ち取る展開が痛快だ。マイク・マイヤーズがプロデューサー役で出演しているが、これは同曲が挿入曲の主演作「ウェインズ・ワールド」(92)への目配せ。爆笑したいなら、同作を観ておくことも忘れずに。
007 スペクター(2015)
| 監督 | サム・メンデス |
| 評価 | 3.79 |
解説
長い間人々をとりこにしてきた大ヒット作『007』シリーズで、ダニエル・クレイグが4度目のジェームズ・ボンドを体当たりで演じたアクション大作。前作同様サム・メンデス監督がメガホンを取り、新たなる敵スペクターとボンドの死闘を描く。ボンドガールを『サイの季節』などのモニカ・ベルッチと、『アデル、ブルーは熱い色』などのレア・セドゥというイタリアとフランスを代表する美女が熱演。苦悩するボンドの葛藤はもとより、明らかになる彼の幼少期の秘密に期待。
あらすじ
ボンド(ダニエル・クレイグ)は、少年時代の思い出が詰まった生家“スカイフォール”で焼け残った写真を受け取る。彼はM(レイフ・ファインズ)が止めるのも無視して、その写真の謎を解き明かすため単身メキシコとローマを訪れる。死んだ犯罪者の妻ルチア(モニカ・ベルッチ)と滞在先で巡り合ったボンドは、悪の組織スペクターの存在を確信する。
映画レポート
ボンド映画の製作会社であるイオン・プロが、007シリーズ第24作目となる本作を50余年守り通して来た「公式」を遵守し超一流のエンターテイメント作品へと仕上げた。それでいてすばらしい「ミスター・キスキスバンバン」ぶりなのだ。これはスゴい、スゴすぎる。
本作では「カジノ・ロワイヤル」「慰めの報酬」「スカイフォール」で散りばめた伏線を、ストーリー中で巧みに回収している。しかも「ロシアより愛をこめて」や「007は二度死ぬ」や「女王陛下の007」など古き良き1960年代の007シリーズへの「目配せ」(オマージュ)もある。さらに、これまで権利関係で使えなかった「スペクター」と「ブロフェルド」が40年ぶりに復活しており、そういう意味でとてもカラフルなヴィランをクリストフ・ヴァルツが演じている。彼は声がいい。思わず聴き入ってしまうほどだ。
今回の007には二人のボンドガールが登場する。モニカ・ベルッチのファンは不満だろうが、本作はもう一人のボンドガール、レア・セドゥに思わず恋をしてしまうように出来ている。まさに後半出ずっぱりで、「ロシアより愛をこめて」のダニエラ・ビアンキや「カジノ・ロワイヤル」のエヴァ・グリーンのような深い印象を残す。
そして、毎度のことながら唸らされるのがボンドの愛車や彼が着用するアイテムの数々。アストンマーティンDB10、オメガシーマスター、トム・フォードの高級スーツ。男の一流品しか身につけないボンドだが、今回も過不足なくストーリー中に組み込まれている。
メキシコシティの「死者の日」、古都ローマ、冬のオーストリアアルプス、モロッコと、風光明媚なロケ地を訪ねて旅情を誘ってくれるのもすばらしい。
ダニエル・クレイグ版007シリーズではベストともいえる出来だ。ある部分内省的とも言えるサム・メンデス監督の筆致が、本作では見事なまでに突き抜けているところにも注目だ。
トゥルーマン・ショー(1998)
| 監督 | ピーター・ウィアー |
| 評価 | 3.88 |
解説
典型的なアメリカ市民・トゥルーマン。だが彼の暮らす環境は、どことなく不自然だ。それもそのはず、実は彼の人生は、隠しカメラによってTV番組「トゥルーマン・ショー」として世界中に放送されていたのだ!家族や友人を含めたこれまでの人生が全てフィクションだったと知った彼は、現実の世界への脱出を決意する…。メディアによって作られた人生の悲喜劇に、見事なリアリティを与えているジム・キャリーの熱演が光る傑作コメディ。
映画レポート
離島の保険会社に勤めるトゥルーマン・バーバンク(ジム・キャリー)の1日は、こんな挨拶から始まる。「おはよう! 念のため“こんにちは”と“こんばんは”も」。何気ない朝のひと幕――とは言えない。世界220カ国の人々が、その光景を見守っているからだ。テレビ番組「トゥルーマン・ショー」は、ひとりの男が知らぬ間に提供していたリアルを糧とし、1万909日目の放映を迎えていた。
「ガタカ」のアンドリュー・ニコルが紡いだ脚本を基に、名匠ピーター・ウィアーが創り上げたのは「人生の全てをテレビのリアリティショーとして生中継されていた男の物語」。町はドーム型の超巨大セット、周囲の人々は全員俳優、身の回りのアイテムは広告絡みの商品ばかり。自身の名前に反して、真実を知らなかったトゥルーマンが、世界の違和感に気づき行動を起こすさまが描かれていく。
トゥルーマンが自らの正しさを認識するには、自分以外の全てを虚構だと証明しなくてはならない。それも独りきりでだ。培った愛や友情、キャリアを嘘だと認めることは、全人生の否定へとつながる。しかも味方はゼロに等しい。下手をすれば陰謀論を唱える「狂人」扱いされる可能性もあるだろう。友人を演じ続けた男は「全てがリアル。この番組に作り物は一切ない。操作されているだけ」と開き直り、妻役の女性ですら「公(おおやけ)と個人の生活をわけていない」とすっかり番組のシンパ。物語はコメディタッチで進行するが、「トゥルーマンの犠牲が、彼以外の幸せを生み出す」という設定には恐怖を覚える。
ジム・キャリーの芝居は、掛け値なしの名演と言っていい。お得意の顔面変化芸を要所要所で挟みつつ、クライマックスでは、世界の真実に触れたことで生じた感情、葛藤、そして決意を“背中”で雄弁に語ってみせる。「役者としての自分を虹に例えるなら、それまでは赤や緑や黄色だけだったけど、この作品で紫が加わった。それで初めて虹が完成するんだ。僕にとっては新しい色を出せたのが一番の収穫だった」と断言するほどの記念碑的作品になったのだ。
独創的なストーリー、キャラクターの魅力に比重を置いた作品だが、「作り物感」を強調する細やかな視覚効果にも注目してほしい。妙に明るく美しい光の加減、地平線の不自然なカットや湾曲によって、閉ざされた人工的な世界を表現。隠しカメラを意識したアングル、撮影者の意図がにじむズームを多用し、トゥルーマンがテレビの中で生きていることを印象づけている。
エクソシスト(1973)
| 監督 | ウィリアム・フリードキン |
| 評価 | 4.00 |
解説
12才の少女リーガンに取り付いた悪魔パズズと二人の神父の戦いを描いたウィリアム・ピーター・ブラッティ(オスカーを受賞した脚色も担当)の同名小説を映画化したセンセーショナルな恐怖大作で一大オカルト・ブームを巻き起こした。
映画レポート
1974年7月に公開された「エクソシスト」は前評判通りの大ヒットとなり、年間興行成績の首位を獲得。当時の日本はベストセラー「ノストラダムスの大予言」「日本沈没」の映像化によるパニック映画ブーム、ユリ・ゲラーのスプーン曲げがきっかけの超能力ブーム、中岡俊哉著「恐怖の心霊写真集」やTV「あなたの知らない世界」から始まる心霊ブームがほぼ同時に発生。そこに、オイルショックによる高度成長の終焉と、トイレットペーパー騒動や狂乱物価、さらには年300回を超える光化学スモッグ発生に見られる公害の影響が重なる。第二次ベビーブームの真っ只中、それらが引き起こす深刻な世相不安が「エクソシスト」のヒットと一大オカルトブームを大きく牽引したと言えよう。
本作は米公開時から「衝撃の実話」「関係者が次々と死亡」「原因不明の火災でセットが焼失」「観客に失神者続出」というショッキングな報道がなされた。少女リーガンに取り憑いた悪魔パズズと、メリン神父とカラス神父の命がけの悪魔祓いを描いた本作は、ドキュメンタリー出身のフリードキン監督でなければ出せない迫力に満ちている。実際、リアルを追求するために、監督は際どい手法を取っている。
カラス神父役のジェイソン・ミラーから驚愕の表情を引き出すために突然空砲を発砲する、リーガンの緑の吐瀉物を予告なしに顔面にかける(豆のポタージュとのこと)、ダイアー神父演じるウィリアム・オマリーに本番直前にビンタをして、悲嘆にくれるシーンを撮影、ベットで激しく揺さぶられるシーンではリンダ・ブレアは腰と背中に深いダメージを負った、リンダは有名な「スパイダー・ウォーク」でも背中を痛めたが、このシーンはカットされた(ディレクターズ・カット版で復活)、対決シーンでは息が白く見えるようにセットをマイナス40度に冷却、霜がおりるなか俳優には通常の衣装で演技させた、等々。
スタッフ・キャストの奮闘もあり、過激なショック描写と信仰というテーマで「エクソシスト」は73年賞レースの目玉に。ゴールデングローブでは7部門にノミネートされ、作品、監督、脚本、助演(リンダ・ブレア)の4部門を独占。本命オスカーでは「スティング」とともに作品、監督など最多主要10部門にノミネート(受賞は脚色賞と音響賞)。作品賞にノミネートされたホラー映画は「エクソシスト」が初、それ以降は2017年の「ゲット・アウト」まで現れなかった。
イタリア最大のエクソシストで知られる神父がお墨付きを与えるほど、この作品は「悪魔祓い」を真実として取り上げた画期的な映画だった。作中、精神科医の立場で科学的な解決を試みるカラス神父は、次々に襲いかかる超常現象を前に苦悩する。善と悪、神と悪魔は表裏一体であることを知ったカラスは、最後に信仰を取り戻し、命がけの決断で少女を救う。その結末は驚きと共に深い感動を呼び、半世紀経った今も色あせない魅力を放つ。オカルト映画、キワモノという枕詞はあるものの、高い完成度を誇る人間ドラマとして、この機会にぜひ鑑賞して頂きたい。
レ・ミゼラブル(2012)
| 監督 | トム・フーパー |
| 評価 | 4.15 |
解説
文豪ヴィクトル・ユーゴーの小説を基に、世界各国でロングラン上演されてきたミュージカルを映画化。『英国王のスピーチ』でオスカーを受賞したトム・フーパーが監督を務め、貧しさからパンを盗み19年も投獄された男ジャン・バルジャンの波乱に満ちた生涯を描く。主演は、『X-MEN』シリーズのヒュー・ジャックマン。彼を追う警官にオスカー俳優のラッセル・クロウがふんするほか、『プラダを着た悪魔』のアン・ハサウェイ、『マンマ・ミーア!』のアマンダ・セイフライドら豪華キャストが勢ぞろいする。
あらすじ
1815年、ジャン・バルジャン(ヒュー・ジャックマン)は、19年も刑務所にいたが仮釈放されることに。老司教の銀食器を盗むが、司教の慈悲に触れ改心する。1823年、工場主として成功を収め市長になった彼は、以前自分の工場で働いていて、娘を養うため極貧生活を送るファンテーヌ(アン・ハサウェイ)と知り合い、幼い娘の面倒を見ると約束。そんなある日、バルジャン逮捕の知らせを耳にした彼は、法廷で自分の正体を明かし再び追われることになってしまい……。
映画レポート
1985年にロンドンのウエストエンド、その後ニューヨークのブロードウェイでロングランヒットした名作ミュージカルの映画化として、堂々とした風格を備えている。
原作は150年前に書かれたビクトル・ユーゴーの「ああ無情」。19世紀の革命後のフランスを舞台にした“コケが生えた”ような物語だ。観客の多くは結末に至るまでストーリーを熟知していて、予定されたことしか起こらない。貧困や格差にあえぐ民衆たちが自由を求めて蜂起する。しかし民衆は踊らない。3・11後の初めての選挙にも関わらず、国民の4割が選挙権を放棄したいまの日本社会の姿を重ね合わせることができる。この映画の革命は、民衆たちの「無関心」により失敗に終わるのだ。フランスの三色旗が虚しくはためく。
主演のヒュー・ジャックマン(ジャン・バルジャン役)をはじめとした俳優たちの、感情がほとばしるままに溢れ出す歌声が、観ているぼくらの心を揺らす。ミュージカルとは、俳優たちが“楽器”のように全身を共鳴させて奏でる歌声(肉声)を楽しむ芸術なのだ、と改めて思い知る。
アン・ハサウェイ(ファンテーヌ役)が歌う「夢やぶれて」、サマンサ・バークス(エボニーヌ役)が歌う「オン・マイ・オウン」、そしてエディ・レッドメイン(マリウス役)らが歌う「民衆の歌」。この映画には一度聴いたら忘れられない珠玉のミュージカルナンバーが少なくとも(31曲中)3曲はある。映画がハネた後に感動と興奮そのままに、鼻歌で歌いたくなる名曲だ。とくにメインキャストたち全員による歌声が絶妙なアンサンブルを奏で始め、終いにはオーケストラのように重なり合う、クライマックスの「民衆の歌」に涙が止まらなかった。圧倒的な感動のきわみへと誘う歌の力に、全身が熱くなった。
ラ・ラ・ランド(2016)
| 監督 | デイミアン・チャゼル |
| 評価 | 4.10 |
解説
『セッション』などのデイミアン・チャゼルが監督と脚本を務めたラブストーリー。女優の卵とジャズピアニストの恋のてん末を、華麗な音楽とダンスで表現する。『ブルーバレンタイン』などのライアン・ゴズリングと『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』などのエマ・ストーンをはじめ、『セッション』でチャゼル監督とタッグを組んで鬼教師を怪演したJ・K・シモンズが出演。クラシカルかつロマンチックな物語にうっとりする。
あらすじ
何度もオーディションに落ちてすっかりへこんでいた女優志望の卵ミア(エマ・ストーン)は、ピアノの音色に導かれるようにジャズバーに入る。そこでピアニストのセバスチャン(ライアン・ゴズリング)と出会うが、そのいきさつは最悪なものだった。ある日、ミアはプールサイドで不機嫌そうに1980年代のポップスを演奏をするセバスチャンと再会し……。
映画レポート
ハイウェイの渋滞に業を煮やした人々が踊り出すプロローグのダイナミックなミュージカルシーンは、運搬橋を舞台にキャラバン隊が踊る「ロシュフォールの恋人たち」を連想させる。一方、エピローグで恋人たちの数年後に話が飛ぶところは、「シェルブールの雨傘」を思わせる。ジャック・ドゥミ監督のミュージカル映画へのオマージュがブックエンドをなす「ラ・ラ・ランド」には、他にも「バンド・ワゴン」のエレガントな公園のダンスから「世界中がアイ・ラヴ・ユー」の空中浮遊まで、新旧ミュージカル映画のエッセンスが詰め込まれている。が、デイミアン・チャゼル監督の本領はそうした引用のうまさではなく、リアルな描写からファンタジーへとミュージカルシーンをなめらかに昇華させるテクニックを心得ていることだろう。恐るべき32歳だ。
ミュージカル映画定番の「芸能界の内幕物」に属するストーリーも魅力だ。女優志望のミア(エマ・ストーン)と売れないジャズマンのセブ(ライアン・ゴズリング)が繰り広げる愛らしいラブストーリーには、2種類の悲哀が宿っている。ひとつはアーティストの悲哀。生活のために売れ線のバンドに加わるセブと、才能の限界を感じるミア。妥協を突きつけられる2人の揺れる心情が切なさをかきたてる。もうひとつは恋愛の悲哀。人生の浮き沈みのタイミングのすれ違いが恋愛の行方を微妙に左右する設定は、ハラハラさせると同時に胸をキュンとしめつける。
この2種の悲哀が絡み合ってドラマを生む構成は「ニューヨーク・ニューヨーク」と同じだが、主人公を見守りたいと思わせる共感度の高さは「ラ・ラ・ランド」が勝っている。それがラストで生きる。かなった夢とかなわなかった夢、逃した幸福とつかんだ幸福。誰もが経験するであろう人生の忘れ物が走馬燈のようにかけめぐる至福の15分間。これを見たら、インスピレーションの元になった「巴里のアメリカ人」のビンセント・ミネリ監督も誇りに思うに違いない。
リメンバー・ミー(2017)
| 監督 | リー・アンクリッチ |
| 評価 | 4.36 |
解説
1年に1度だけ他界した家族と再会できるとされる祝祭をテーマにした、ディズニー/ピクサーによる長編アニメ。死者の国に足を踏み入れた少年が、笑いと感動の冒険を繰り広げる。監督と製作には、『トイ・ストーリー3』のリー・アンクリッチ監督と、製作を担当したダーラ・K・アンダーソンが再び集結。テーマパークのような死者の国の描写、祖先や家族を尊ぶ物語に引き込まれる。
あらすじ
過去の出来事が原因で、家族ともども音楽を禁止されている少年ミゲル。ある日、先祖が家族に会いにくるという死者の日に開催される音楽コンテストに出ることを決める。伝説的ミュージシャンであるデラクルスの霊廟に飾られたギターを手にして出場するが、それを弾いた瞬間にミゲルは死者の国に迷い込んでしまう。元の世界に戻れずに困っていると、ヘクターという謎めいたガイコツが現れ……。
映画レポート
子供の頃、夜の暗闇が怖かったし、限りある命という言葉に気が重くなった。そして何よりも、人が死んだらどこに行くのか、想像するだけで夜眠れなくなった。もしもあの時の自分がこんなワンダフルでマーベラスな映画と出会っていれば、一体どれほど楽になれただろう。ピクサーが「インサイド・ヘッド」(15)で人間の複雑な感情を擬人化した時にも感嘆させられたが、今回はさらにその上をゆく未知なる領域への挑戦がある。これは映画史に残る偉業と言えるのかもしれない。
まずもって特定の宗教にとらわれず、メキシコの伝統行事「死者の日」にスポットを当てているのが本当にうまい。この時期に合わせて、各家庭では先祖をお迎えすべく祭壇を華やかに彩り始める。物語はそんな中、少年ミゲルの表情をクローズアップ。音楽コンテストへの参加を家族に大反対された彼は、失意のどん底にいた。この家系ではある理由から音楽がタブーとなっているのだ。それでも夢を諦めきれないミゲルが、ふとした拍子に生きながら「死者の国」へと紛れ混んでしまったことで、事態は意外な展開に----。
マリーゴールドの花びらがいざなう死者の国は、思わず目が歓喜するほどカラフルで美しい。また、ファンタジックな街並みをガイコツ姿(怖いというよりも可愛らしい!)の死者たちが闊歩する様は実にユニーク。こんな世界観を提示できただけでも十分ゴールに達しているのに、本作はさらに面影のあるガイコツ姿のご先祖様たちが入り乱れての見事なアドベンチャーへ発展していくのだ。
祭壇に写真を飾る理由。名曲「リメンバー・ミー」に謳われる切なる想い。音楽にまつわる過去……。あらゆる展開に心が大きく揺さぶられる。そして本作が最終的に帰着していくのは、死そのものではない。むしろ家族という名のルーツ、決して失われることのない絆だ。これらは何ら特別な答えではないが、だからこそ一番身近な宝物を見つけたような感慨がある。自分が長い長い物語の延長上にあることに気づき、両親や祖父母、そのまた先祖へのたまらない愛情の念が沸き起こっていく。それはきっと生を見つめ直すことにもつながるはず。
鑑賞後、すっかり色あせた古いアルバムを広げ、亡くなった人たちに久々に会いたいと思った。その日の夢の中で、もうずいぶん長い間忘れていた曽祖母のシワシワの手に触れた気がした。忘れない、と心に刻んだ。
モーリタニアン 黒塗りの記録(2021)
| 監督 | ケヴィン・マクドナルド |
| 評価 | 4.13 |
解説
モハメドゥ・ウルド・スラヒの著書を原作に描く社会派ドラマ。弁護士たちが、アメリカ軍のグアンタナモ基地で何年も投獄生活を送るモーリタニア人青年の弁護を引き受ける。『ブラック・シー』などのケヴィン・マクドナルドが監督を手掛け、『フライトプラン』などのジョディ・フォスター、『ダイバージェント』シリーズなどのシェイリーン・ウッドリー、『エジソンズ・ゲーム』などのベネディクト・カンバーバッチらが弁護士を演じている。
あらすじ
モーリタニア人のモハメドゥ(タハール・ラヒム)は、アメリカ同時多発テロの容疑者として、キューバにあるアメリカ軍のグアンタナモ基地に収容されていた。彼の弁護を引き受けた弁護士のナンシー・ホランダー(ジョディ・フォスター)とテリー・ダンカン(シェイリーン・ウッドリー)は、真相解明のため調査を開始する。彼らに相対するのは、軍の弁護士であるステュアート中佐(ベネディクト・カンバーバッチ)だった。
ディパーテッド(2006)
| 監督 | マーティン・スコセッシ |
| 評価 | 3.53 |
解説
巨匠マーティン・スコセッシが、香港映画『インファナル・アフェア』をリメイクしたアクションサスペンス。マフィアに潜入した警察官と、警察に潜入したマフィアの死闘がスリリングに描かれる。レオナルド・ディカプリオとマット・デイモンが主人公の警察官とマフィアをそれぞれ熱演。名優ジャック・ニコルソンがマフィアのボス役で脇を固める。ボストンを舞台に描かれた本作は、スコセッシ監督らしいバイオレンスシーンと、敵対組織に潜入した男ふたりの心理描写に注目。
あらすじ
犯罪者の一族に生まれたビリー(レオナルド・ディカプリオ)は、自らの生い立ちと決別するため警察官を志し、優秀な成績で警察学校を卒業。しかし、警察に入るなり、彼はマフィアへの潜入捜査を命じられる。一方、マフィアのボス、コステロ(ジャック・ニコルソン)にかわいがられて育ったコリン(マット・デイモン)は、内通者となるためコステロの指示で警察官になる。
映画レポート
「グッドフェローズ」以来、久々にホレボレするクライムストーリーだ。ワルとデカが互いに“ネズミ”(潜入者)を送り込んだことから悲劇を招く。筋立てはご存じ香港スリラー「インファナル・アフェア」の焼き直しだ。だが物語ばかり追いかけると見逃してしまう、映画の醍醐味がこの映画にはある。それは、独特のリズムとビートを刻む魔術的なカメラワーク(撮影)と、圧倒的な「プロテクション・ショット」から選ばれた神業のようなカッティング(編集)だ。いかにもスコセッシ映画らしい、カトリック的罪悪感やアイルランド系移民(マイノリティ)の叫びが通奏低音として響きあい、オリジナルとひと味違う。
ディカプリオもニコルソンも、スコセッシ好みの“重層的”でカラフルなキャラクターで、彼らの黒いアンサンブルが不気味なハーモニーを奏でる。また、ローリング・ストーンズ「ギミー・シェルター」、ピンク・フロイドの名曲「コンフォタブリー・ナム」、ロイ・ブキャナンの超絶ギターにシビレる「スウィート・ドリームス」、ハワード・ショア作曲のタンゴ調テーマ曲(ドブロの旋律が最高)といったゴキゲンな音楽が人物をリズミカルに躍動させる。その1曲1曲に、映画的かつ音楽的“引用”がある。その秘密を知るとき、得体のしれない魔力に襲われるのだ。
ジョーカー(2019)
| 監督 | トッド・フィリップス |
| 評価 | 4.11 |
解説
『ザ・マスター』『ビューティフル・デイ』などのホアキン・フェニックスが、DCコミックスの悪役ジョーカーを演じたドラマ。大道芸人だった男が、さまざまな要因から巨悪に変貌する。『ハングオーバー』シリーズなどのトッド・フィリップスがメガホンを取り、オスカー俳優ロバート・デ・ニーロらが共演。『ザ・ファイター』などのスコット・シルヴァーがフィリップス監督と共に脚本を担当した。
あらすじ
孤独で心の優しいアーサー(ホアキン・フェニックス)は、母の「どんなときも笑顔で人々を楽しませなさい」という言葉を心に刻みコメディアンを目指す。ピエロのメイクをして大道芸を披露しながら母を助ける彼は、同じアパートの住人ソフィーにひそかに思いを寄せていた。そして、笑いのある人生は素晴らしいと信じ、底辺からの脱出を試みる。
映画レポート
ダース・ベイダーに悪感情も恨みもないが、自分はヒール(悪役)の起源を描いた映画を、あまり好ましいものとは思っていない。かつては優しく純粋だった人物が、自己犠牲のすえにやまれず暗黒面へと身を寄せる。そんな綺麗ごとによって正当化される悪に、はたして説得力などあるのだろうか?
ヒーローコミックス「バットマン」の宿敵として登場するジョーカーは、廃液の満ちたタンクに落下し、異貌となった形相が本性を肥大化させ、世界で最も知られるヴィランの一人となった。だが彼の出自を再定義する本作は、そんな固定されたジョーカー伝説とは異質のコースをたどる。心を病み、それでも人々に笑いを提供する貧しい大道芸人が、社会からの孤立や資本主義がもたらす貧富格差といった膿汁で肺を満たされ、呼吸困難からあえぐように悪の水面へと浮かび上がっていく。苦しいのか、それとも開放感から出る笑みなのか分からぬ表情で。
このようにジョーカーこと主人公アーサー(ホアキン・フェニックス)は、自ら道を選んで悪の轍を踏んだわけではない。そこにはダークヒーローなどといった気取ったワードとは無縁の、逃れられない運命の帰結として悪が存在する。人生に選択の余地を与えぬ、容赦ない哀しみの腐臭を放ちながら。
監督のトッド・フィリップスは「ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い」(09)を代表作とするコメディ一辺倒の手練れだが、「全身ハードコア GGアリン」(93)などキャリア初期のドキュメンタリーで得た人間観察の慧眼を助力に、“喜劇”のコントラストとしてそこにある“悲劇”へと踏み込んでいく。なので想定外の人選では決してない。コメディ作家だからこそ到達が可能な、そんな不可触領域にジョーカーは潜在していたのだから。
加えて過去、映像化されたジョーカーの歴任俳優は、それぞれが最高のパフォーマンスをもって役に臨んできた。ホアキン・フェニックスもその例に漏れず、自らをとことんまで追い込みパラノイアを体現することで、狂気の塊のようなキャラクターからつかみどころを見つけ、握った感触を確実にわがものにしている。
“狂っているのは僕か? それとも世間か???“ ドーランを血に代えた、悲哀を極める悪の誕生を見た後では、ジョーカーへの同情が意識を遮断し、もはやバットマンに肩入れすることなどできない。なんと恐ろしい作品だろう。
コメント
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です。
関連記事
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】ivfree.asiaは安全?視聴方法や代わりサイトまで一気にご紹介!
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】カリビアンコムのダウンロード廃止?今なら使えるカリビアンコム動画のダウンロード方法!
- Aoi / 2023-12-26【高品質かつ安全】Supjavからアダルト動画をダウンロードする方法
- Aoi / 2023-12-21【23年最新】Avgle ダウンロードの裏技を公開!簡単に高画質動画を入手~Android・iPhone/iPad・PC全環境対応
- Aoi / 2023-11-30av4.usが閉鎖!?代わりの無料アダルト動画サイトをまとめ
- Aoi / 2023-11-29【無料】TokyoMotionダウンロードする方法、その操作手順まで詳しくご紹介!(PC&スマホ)
最新記事 人気記事
Kira / 2024-09-24
【無料】ディズニー動画ダウンロード方法おすすめ|ディズニー+から映画を保存してオフラインで視聴しよう
Kira / 2024-09-24
SwitchでHuluは見れません!その理由と今後の動向を予想して裏技まで紹介します
Melody / 2024-09-24
【2023年】Huluを録画する方法!裏ワザ?真っ黒にならないソフトを紹介します
Kira / 2024-09-24
AbemaTVをダウンロード&録画できるツール7選!DRM解除できるものだけを厳選
HANA / 2024-09-24
【ABEMA ダウンロード】ABEMA(旧AbemaTV)動画をダウンロードする方法、ダウンロードできない原因と対策
youjinkin / 2024-09-24
U-NEXTで鑑賞できるおすすめアニメ作品TOP 20
Kira / 2024-09-24
U-NEXTがダウンロードできるツールトップ7!録画ソフトも
Melody / 2024-09-24
【完全保存版】U-NEXTのダウンロード方法!できない時の原因と解決法も
Tetsuko / 2024-09-24
StreamFab myFansダウンローダーの機能や使い方、評判をレビューして徹底解説!
Tetsuko / 2024-05-09
Missavの無料エロ動画をダウンロードするツール5選
展開 ∨ 折りたたみ ∧
ホットトピックス

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次
Copyright © 2024 entametalk.jp All Rights Reserved.
年齢認証

あなたは18歳以上ですか?
エンタメTALKはアダルトコンテンツを含みますので、18歳未満の方の閲覧を固くお断りいたします。
いいえ はい