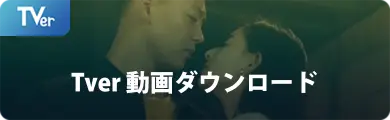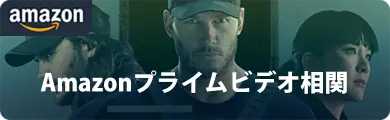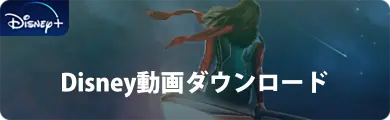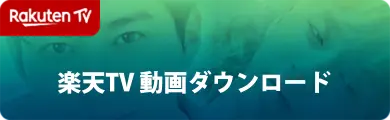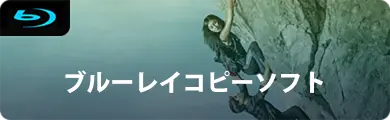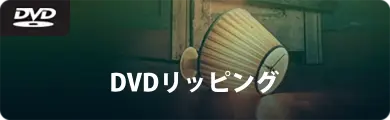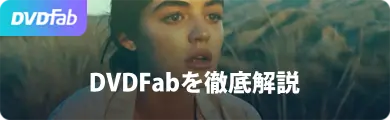StreamFab 動画 ダウンローダー
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次>
始皇帝暗殺(1998)
| 監督 | チェン・カイコー |
| 評価 | 3.61 |
解説
『さらば、わが愛/覇王別姫』のチェン・カイコー監督がメガホンを執り、日本、中国、フランス、アメリカの4カ国共同製作で作り上げた歴史大作。中国最初の皇帝、始皇帝の暗殺にまつわるエピソードを、ふたりの男とひとりの女の愛憎劇を絡めながら描いてゆく。物語の壮大さもさる事ながら、当時の衣装や宮殿を再現した美術も特筆もの。紀元前3世紀の戦国時代。秦の始皇帝は、先祖代々の宿願であった中国統一に執念を燃やし、他国との戦争を繰り返していた。始皇帝を愛する趙姫は、彼の野望を遂げさせようと、孤高の暗殺者・荊 に会いにゆくが...。
パラサイト 半地下の家族(2019)
| 監督 | ポン・ジュノ |
| 評価 | 4.04 |
解説
『母なる証明』などのポン・ジュノが監督を務め、第72回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した人間ドラマ。裕福な家族と貧しい家族の出会いから始まる物語を描く。ポン・ジュノ監督作『グエムル -漢江の怪物-』などのソン・ガンホをはじめ、『新感染 ファイナル・エクスプレス』などのチェ・ウシク、『最後まで行く』などのイ・ソンギュンらが出演。
あらすじ
半地下住宅に住むキム一家は全員失業中で、日々の暮らしに困窮していた。ある日、たまたま長男のギウ(チェ・ウシク)が家庭教師の面接のため、IT企業のCEOを務めるパク氏の豪邸を訪ね、兄に続いて妹のギジョン(パク・ソダム)もその家に足を踏み入れる。
映画レポート
世界共通の社会問題である“貧富の格差”は、映画界においても多くの著名監督たちがそれぞれの切り口で追求しているテーマだ。カンヌ国際映画祭パルムドールに輝き、全米賞レースでも猛烈な勢いで外国語映画賞を総なめにしている「パラサイト 半地下の家族」は、おそらく映画史上最も鮮烈に“格差”の視覚化に成功した作品だろう。
全員失業中のキム一家は、日当たりが悪く不衛生で、WiFiの電波もろくに届かない半地下住宅で暮らしている。一方、高台の豪邸に住んでいるIT社長のパク一家は、勝ち組を絵に描いたような大富豪。キム家の息子が身分を詐称してパク家の娘の家庭教師になったことをきっかけに、ふたつの家族の人生が交錯していくという物語だ。両家の途方もない格差を象徴する“家”のデザインにこだわったポン・ジュノ監督は、思うがままのカメラワークを駆使した空間演出のタクトをふるうべく、このふたつの主要舞台の大規模なオープンセットを建造して撮影を行った。
悪意なき貧乏人であるキム一家には、パク一家への恨みなど一切ない。手荒い手段で財産を奪う“侵略”ではなく、密かにまとわりついて幸せという名の養分を吸い取る“寄生”が彼らの狙いだ。「パラサイト」とは、何とうまく的を射たタイトルだろう。ユーモアとサスペンスを変幻自在に操るポン監督は、中盤の意外なほど早いタイミングで達成されるパク一家のパラサイト計画のプロセスを、痛快なブラック・コメディに仕立ててみせた。
壮大などんでん返しが待ち受けるその後の展開はジャンルもトーンも一変し、クライマックスに向かって怒濤のスペクタクルが炸裂する。ポン監督のさらなる格差の視覚化を成す重要なエッセンスは“雨”と“階段”だ。もしも災害レベルの豪雨が降ったら、半地下住宅と高台の豪邸のどちらが甚大な被害を被るかは一目瞭然。そして極めて映画的な装置である階段は、本作に隠されたもうひとつの階層の存在をあぶり出すシークエンスで絶大な威力を発揮する。その暗黒の異界への扉が開かれた瞬間、寄生する者とされる者の構図は激しくねじ曲がり、パラサイト計画の行く末は予測不能のカオスと化していく。
そのほか“桃”や“体臭”などポン監督の尋常ならざるディテール描写が冴えるモチーフはいくつもあるが、娯楽性満点の本作のエンディングは決して爽快ではない。格差というものの恐ろしい断絶の視覚化までも試みたこの映画は、ほの暗い複雑な余韻となって、鑑賞後も私たち観客の心にパラサイトしてくるのだ。(高橋諭治)
万引き家族(2018)
| 監督 | 是枝裕和 |
| 評価 | 4.08 |
解説
『誰も知らない』『そして父になる』などの是枝裕和監督による人間ドラマ。親の年金を不正に受給していた家族が逮捕された事件に着想を得たという物語が展開する。キャストには是枝監督と何度も組んできたリリー・フランキー、樹木希林をはじめ、『百円の恋』などの安藤サクラ、『勝手にふるえてろ』などの松岡茉優、オーディションで選出された子役の城桧吏、佐々木みゆらが名を連ねる。
あらすじ
治(リリー・フランキー)と息子の祥太(城桧吏)は万引きを終えた帰り道で、寒さに震えるじゅり(佐々木みゆ)を見掛け家に連れて帰る。見ず知らずの子供と帰ってきた夫に困惑する信代(安藤サクラ)は、傷だらけの彼女を見て世話をすることにする。信代の妹の亜紀(松岡茉優)を含めた一家は、初枝(樹木希林)の年金を頼りに生活していたが……。
映画レポート
子どもは生まれてくるとき環境を選べない。でも、もし選択の自由があったら? 虐待する親と、愛情かけて万引きをやらせる親。あなたはどちらと一緒に暮らすだろう?
劇中、治(リリー・フランキー)が不憫に思って家に連れ帰る5歳の少女は、虐待する実親の元へ戻らず、治たち家族の一員になる道を選ぶ。一方、治の息子の祥太(城桧吏)は、治に指南された万引きの正当性に疑問を持ち始めたことから、「この家族と同じ価値観を共有していけるだろうか?」と迷うようになる。
大人の不正と、自身の心に芽生えた正義感の間で揺れる祥太の葛藤は、ダルデンヌ兄弟監督の「イゴールの約束」で、違法外国人労働者の売人をする父を手伝う少年イゴールが体験するものに似ている。イゴールも祥太も、汚れ仕事以外に生きる術を知らない大人の保護下で、自分はどう生きるべきかを自問する。これは、そんな少年の成長と選択を描く超一級の思春期映画だ。
おそらく是枝裕和監督作品の中では、「誰も知らない」の遺伝子をいちばん多く受け継いでいるだろう。しかし、児童虐待から独居老人まで、いまどき日本の社会問題を6人の登場人物に背負わせた群像劇でもあるこの映画には、さらなる是枝的要素が混ざり合っている。子どもたちを愛し、愛される親になろうと奮闘する治と信代(安藤サクラ)の物語は、「そして父になる」の続編だ。また、法律的な善人が犯す悪(少女の親による虐待)と、法律的な悪人が成す善(治による虐待児の保護)を対比させた点は、「三度目の殺人」の流れを汲んでいる。まさしく集大成だ。
この映画の創作を思い立ったとき、「犯罪でしかつながれなかった」というキャッチコピーを最初に思い浮かべたという是枝監督は、「この家族が何でつながっているか?」という問いを見る側にも投げかける。私に見えた答えは「不安」だ。6人はそれぞれの不安を埋め合うように肩寄せ合って暮らし、同時に秘密が露見することに対する不安を共有している。そして、最も幸せな瞬間にもそれは消えることがない。その心象風景を、寒色で表現した映像が素晴らしい。(矢崎由紀子)
イングロリアス・バスターズ(2009)
| 監督 | クエンティン・タランティーノ |
| 評価 | 3.66 |
解説
クエンティン・タランティーノ監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ最強のアクション大作。ナチス占領下のフランスを舞台に、それぞれに事情を抱えたクセのある登場人物たちの暴走をユーモアたっぷりに描く。メラニー・ロランやクリストフ・ヴァルツ、ダイアン・クルーガーなど各国を代表する俳優たちがこれまでにない役柄を喜々として演じている。歴史的事実を基に作り上げられた、奇想天外なストーリー展開は拍手喝采(かっさい)の快作!
あらすじ
1941年、ナチス占領下のフランスの田舎町で、家族を虐殺されたユダヤ人のショシャナ(メラニー・ロラン)はランダ大佐(クリストフ・ヴァルツ)の追跡を逃れる。一方、“イングロリアス・バスターズ”と呼ばれるレイン中尉(ブラッド・ピット)率いる連合軍の極秘部隊は、次々とナチス兵を血祭りにあげていた。やがて彼らはパリでの作戦を実行に移す。
映画レポート
タランティーノが広がっている。手馴れた安全地帯をみずから抜け出し、リスクを承知で新天地での勝負に挑んでいる。
「イングロリアス・バスターズ」を見て、私は思った。だが、見てすぐにそう感じたわけではない。時間が経ち、映画に仕込まれた語りや技のコクを反芻しているうち、その思いが強くなってきたのだ。
映画の鋳型はマカロニ・ウェスタンである。冒頭のシーンを見れば、だれしもセルジオ・レオーネのタッチを連想するだろう。ナチスに家族を殺された娘の復讐譚が話の軸になっていくところも、レオーネ・ファンにはお馴染みの流れではないか。
だが、映画はとんでもない方向に舵を切る。逸脱に逸脱を重ね、悪夢と笑いを何枚も重ね焼きして「見たことのない戦争映画」へにじり寄っていく。となると、謳い文句が「痛快戦争アクション」だったことなど、遠い昔の笑い話のように思えてくる。「特攻大作戦」や「地獄のバスターズ」が原型にあるかのような装いがタランティーノの陽動作戦だったことも、すぐさまはっきりする。なにしろここでは、「映画中映画」を除いて、最前線の戦闘シーンなどまったく出てこないのだ。
代わりにタランティーノは、不思議な形でヨーロッパ映画の粘着性を輸血した。クリストフ・ワルツやメラニー・ロランといったわれわれに馴染みの薄い俳優に複数の言語を喋らせ、土地や人の湿り気や粘り気を画面に定着させただけではない。彼らがうごめく場面では、かならずといってよいほど、言葉の銃撃戦を思わせる「テンションの積み重ね」が用意される。その楽しさ! そのスリル! これは、なんともわくわくする悪夢の試みだ。おそらくタランティーノは、自身が何十本となく見てきた戦争映画にも、もっと面白い夢を見させてやりたかったのだろう。
ライフ・イズ・ビューティフル(1998)
| 監督 | ロベルト・ベニーニ |
| 評価 | 4.35 |
解説
カンヌ映画祭で審査員グランプリに輝いた、ロベルト・ベニーニ監督・脚本・主演の感動作。ナチの強制収容所に収監されたある一家の物語を、ユーモラスかつ温かな視点で描く。“イタリアのチャップリン”と称される、ベニーニのユーモアと哀しみを交錯させた演出が秀逸。1939年、ユダヤ系イタリア人のグイドは、小学校の教師ドーラに恋をする。彼の純粋さに惹かれた彼女は結婚を承諾。やがて可愛い息子も生まれ、3人は幸せな日々を送っていた。そんなある時、彼らに突然強制収容所への収監命令が下る。
誰も知らない(2004)
| 監督 | 是枝裕和 |
| 評価 | 3.96 |
解説
主演の柳楽優弥が史上最年少の14歳という若さで、2004年度カンヌ国際映画祭主演男優賞に輝いた話題作。『ディスタンス』の是枝裕和監督が実際に起きた、母親が父親の違う子供4人を置き去りにするという衝撃的な事件を元に構想から15年、満を持して映像となった。女優初挑戦の、YOU扮する奔放な母親と子役達の自然な演技も秀逸。母の失踪後一人で弟妹達の面倒をみる長男の姿は、家族や社会のあり方を問いかける。
あらすじ
けい子(YOU)は引っ越しの際、子供は12歳の長男の明(柳楽優弥)だけだと嘘をつく。実際子供は4人いて、彼らは全員学校に通ったこともなく、アパートの部屋で母親の帰りを待って暮らしていたが……。
わたしは、ダニエル・ブレイク(2016)
| 監督 | ケン・ローチ |
| 評価 | 4.08 |
解説
『麦の穂をゆらす風』などのパルムドールの常連ケン・ローチ監督がメガホンを取り、社会の片隅で必死に生きようとする男の奮闘に迫る人間ドラマ。病気で働けなくなった主人公が煩雑な制度に振り回されながらも、人との結び付きを通して前進しようとする姿を描く。コメディアンとして活動しているデイヴ・ジョーンズらが出演。ローチ監督にパルムドールをもたらした力強い物語に震える。
あらすじ
59歳のダニエル(デイヴ・ジョーンズ)は、イギリス・ニューカッスルで大工の仕事に就いていたが、心臓の病でドクターストップがかかる。失職した彼は国の援助の手続きを進めようとするが、あまりにもややこしい制度を前に途方に暮れる。そんな中、ダニエルは二人の子供を持つシングルマザーのケイティと出会う。
映画レポート
ケン・ローチが初めてメガホンを握ってからほぼ50年。これほど一貫した姿勢と映画作りのスタイルを保っている監督も珍しい。それだけにともすればマンネリになりがちなところを、ほぼ毎回ストライク・ゾーンに決める力量たるや、驚くべきものがある。昨年のカンヌ国際映画祭で、キャリア二度目となるパルムドールをさらった本作は、とりわけみごとな直球玉だ。
英国北部の工業都市ニューカッスルを舞台にした、心臓の発作に見舞われ大工の仕事を続けられなくなったダニエルと、彼がたまたま知り合ったふたりの子供のシングルマザー、ケイトの物語。それぞれ国の援助を必要としているにも拘らず、お役所的な複雑なシステムや理不尽な対応がそれを阻む。日々切迫していく彼らの姿を通してローチは、実直な人間が生きられない社会とは、いったい何なのかということを問いかける。あくまでリアリスティックで抑えたトーンの奥には、彼の煮えたぎるような怒りが潜んでいる。
ローチの錬金術はしかし、それを声高なメッセージとして訴えるのではなく、日常のありがちなシチュエーションやディテールの積み重ねによって観る者の共感を誘い、このささやかなドラマに引き込む点にある。たとえばコンピューターなど使ったこともないダニエルが、必要に迫られ初めてマウスの使い方を学ぶシーンや、思いあまって壁に落書きをする場面などは、思わず笑ってしまいながらも胸を突かれるに違いない。観ているうちに我々は、彼らに感情移入するとともに、この物語がだんだん他人事と思えなくなってくるのではないか。ある日病で倒れたら、失業したら、子供をひとりで育てなければならなくなったら? 実際に多くのリサーチをしたというポール・ラヴァティの脚本は、突っ込みどころのない説得力に満ちている。
プロ、素人に拘らず、これ以上はないという適材をキャスティングするのもローチの慧眼だ。本作の切り札と言えるのが、ダニエル役のデイヴ・ジョーンズ。どこにでもいそうな労働者の佇まいでありながら、チャーミングで人間味に溢れどこまでも誠実な、人としての正しさを滲ませる。
英国の良心を代表するローチの揺るぎない信念が、観る者の心にずしりと響く作品だ。
オールド・ボーイ(2003)
| 監督 | パク・チャヌク |
| 評価 | 3.70 |
解説
カルト的人気を誇る日本の同名漫画を原作に、『JSA』のパク・チャヌク監督が映画化したアクション・サスペンス。2004年カンヌ国際映画祭グランプリを受賞し、韓国映画のパワーを見せつけた話題作。15年の理由なき監禁生活を強いられ、突如解放された男の復讐劇を描く。『シュリ』のチェ・ミンシクを主演に、『春の日は過ぎゆく』のユ・ジテ、『バタフライ』のカン・ヘジョンが共演。完成度の高さに注目したハリウッドメジャーによるリメイクも決定している。
あらすじ
ごく平凡な人生を送っていたオ・デス(チェ・ミンシク)はある日突然拉致され、気がつくと小さな監禁部屋にいた。理由も分からぬまま15年監禁され続け、突如解放される。復讐を誓うデスの元に現れた謎の男(ユ・ジテ)は、5日間で監禁の理由を解き明かせと命じるが……。
ニュー・シネマ・パラダイス(1989)
| 監督 | ジュゼッペ・トルナトーレ |
| 評価 | 4.36 |
解説
イタリアの名匠ジュゼッペ・トルナトーレによる、映画史に残る至高の名作。イタリアのシチリアを舞台に、少年と映写技師が映画を通して心を通わせていく様を、感動的な音楽と繊細な人物描写で描き出す。映画に魅了された少年トト役を、サルヴァトーレ・カシオが愛くるしい演技で演じきった。年齢を超えた友情や少年時代の夢など、世代や時代を超えた人々に愛される物語に、“映画の魔法”という名の感動が存分につまっている。
あらすじ
映画監督のサルヴァトーレ(ジャック・ペラン)は、映写技師のアルフレード(フィリップ・ノワレ)という老人が死んだという知らせを受け、故郷のシチリアに帰郷する。
映画レポート
もはや説明不要なほどに知られた、不朽の名作である。ジュゼッペ・トルナトーレが全編を通して紡ぐ映画への愛はどこまでも尊く、長きにわたり世界中の映画ファンへの問答無用のラブレターであった。1989年の第42回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で、審査員特別グランプリを受賞してから30余年。その間、世界中で様々な出来事が起きたが、映画を愛する人々にとって、そして映画を生業とする人々にとっても、今ほどこの作品を必要とする時代はないのではないだろうか。
新型コロナウイルスの感染拡大により、何もかもが変わってしまった。これまでの何気ない日常が、どれほどかけがえのないものであったかを誰もが痛感させられているはず。世界中の映画館が休業を余儀なくされている。いったい誰が、映画館のない日常を想像することが出来ただろう。
「ニュー・シネマ・パラダイス」に登場する小さな映画館「パラダイス座」は、シチリア島の小さな村の中心に位置する広場にあり、教会を兼ねている。第二次世界大戦終結直後で誰もが貧しく、楽しみといえば映画だけだった。本編には、「駅馬車」「チャップリンの拳闘」「ジキル博士とハイド氏」「風と共に去りぬ」「街の灯」「カサブランカ」「素晴らしき哉、人生!」「夏の嵐」「ならず者」「ローマの休日」など、数え切れないほどの名作が登場する。映写技師として働くアルフレードと、「トト」と呼ばれていた映画に魅了された少年サルヴァトーレの心の交流は、この場所から始まる。
今作には、大きく二分すると劇場公開版とオリジナル版が存在する。前者はパラダイス座が物語の中心として鎮座するのに対し、後者はトトの人生に主眼が置かれている。まるで趣が異なるが、その是非を論じるのは野暮というもの。トトとアルフレードの触れ合いは実に温もりにあふれ、人はひとりでは生きていけず、行動しなければ何も始まらないということを、見る者に静かに提示してくる。
火災によって失明したアルフレードが、突き放すようにトトに告げるセリフが強く胸を打つ。「今のおまえは私より盲目だ。人生はおまえが見てきた映画とは違う。人生はもっと困難なものだ。行くんだ! おまえは若い。もう、おまえとは話したくない。おまえの噂が聞きたい」。
鑑賞機会を重ねれば重ねるほど、シーンひとつひとつの持つ意味合いが染み入ってくる。少年時代のトトが映写室の小窓から覗き込んだ世界には、銀幕を食い入るように見つめる好奇心に満ちた眼差しがあった。戦後の日本が迎えた、空前の映画ブームも然り。笑いも涙も、客席に座る誰もが等しく共有できた。この光景を、失くしてはならない。冒頭で今作を「映画ファンへの問答無用のラブレター」と記述したが、いまはトトとアルフレードが鎮魂歌(レクイエム)を奏でているようにも感じられる。そう遠くない将来、人々が本当の意味で日常を取り戻すまで、そして世界中の映画館に人々が戻ってくるまで、何度だって2人が激励してくれるはずだ。
タクシードライバー(1976)
| 監督 | マーティン・スコセッシ |
| 評価 | 3.95 |
解説
ニューヨークの夜を走るひとりのタクシードライバーを主人公に、現代都市に潜む狂気と混乱を描き出した傑作。ベトナム帰りの青年トラヴィス・ビックルは夜の街をタクシーで流しながら、世界の不浄さに苛立ちを感じていた。大統領候補の選挙事務所に勤めるベッツィと親しくなるトラヴィスだったが、彼女をポルノ映画館に誘ったことで絶交されてしまう。やがて、闇ルートから銃を手に入れたトラヴィスは自己鍛錬を始めるが、そんな彼の胸中にひとつの計画が沸き上がる……。
映画レポート
地下から噴き上げる水蒸気を切り裂く1台のタクシー。ハンドルを握る運転手は、麻薬、性、暴力が溢れかえり、毒々しいネオンに照らされたニューヨークを見つめている。1976年、スクリーンに姿を現したトラヴィス・ビックル。その内面を覗き見るのは、何度目のことだろう。安易に共感を抱いてはいけない――今回もまた、画面越しに警告が発せられている。
マーティン・スコセッシ監督、ロバート・デ・ニーロによる2度目のタッグ作。タクシー運転手のトラヴィスが、自らの存在を世間に認めさせるべく“行動”を起こすまでの過程を描く。ベトナム戦争帰りの元海兵隊員、重度の不眠症、余暇はポルノ映画鑑賞、不満と愚痴を書き殴る日記――鬱屈とした日々に付きまとう逃げ場のない寂しさに、胸が締め付けられる。しかし、物語が進むにつれ、そんな同情はいとも簡単に突き返されてしまう。
トラヴィスが欲しているのは“同情”ではなく“承認”だ。しかし、タクシー運転手という職において、彼自身の存在価値を求める者はいない。客が求めているものは、トラヴィス個人ではなく、目的地へと運んでくれる従順なトランスポーターだ。同僚たちとの距離も縮まらず、愛を捧げた女性には無知と矛盾を見抜かれ、彼を必要とする者は誰もいなくなる。
だからこそ、鏡像に対する名セリフ「You talkin' to me?」(俺に用か?)が印象的に響く。自分を最も理解している男“トラヴィス”からの問いかけ――デ・ニーロが体現してみせた狂気の芝居は、何度見ても飽き足らない。トラヴィスのDNAは、40年以上の時を経て「ジョーカー」へと受け継がれている。オマージュは勿論のこと、デ・ニーロがキャストとして両作を繋ぎ、それぞれが“狂気へのプロセス”を重視している点も見逃せない。
内へ溜め込まれた負の感情が、周囲への脅威として反転する――トラヴィスが向かう先は、悪の誕生へと結実する「ジョーカー」とは、異なるものになっていく。その様は、道を踏み外した“バットマン”のようでもある。是非セットでの視聴をおすすめしたい。また「一杯の紅茶を飲むためなら、世界が滅びてもかまわない」という一文が登場し、自意識過剰の魂が炸裂する小説「地下室の手記」(著:ドストエフスキー)の熟読を添えれば、よりベストな鑑賞体験になるはずだ。
Girl/ガール(2018)
| 監督 | ルーカス・ドン |
| 評価 | 3.81 |
解説
第71回カンヌ国際映画祭でカメラドールなどを受賞した人間ドラマ。トランスジェンダーの主人公が葛藤しながら、バレリーナを目指して奮闘する。メガホンを取るのは、ベルギーのルーカス・ドン。自身もバレエスクールに通うダンサーで、映画初出演となるヴィクトール・ポルスターが主演を務め、『マリア・スクウォドフスカ=キュリー』などのアリエ・ワルトアルテらが共演した。
あらすじ
15歳のトランスジェンダー、ララ(ヴィクトール・ポルスター)は娘の夢を応援する父(アリエ・ワルトアルテ)に支えられ、バレリーナを目指して難関のバレエ学校への編入を果たす。それと同時にララが待ち望んでいたホルモン療法も始まるが、効果はなかなか現れなかった。それでも夢のためにバレエに没頭し、そのかいもあって先生の目も少しずつララに向けられるようになる。
映画レポート
2009年にベルギーの新聞に衝撃的な記事が掲載される。それは、トランスジェンダーの少女がバレリーナになるための葛藤を記したものだった。その記事に触発された当時18歳のルーカス・ドン監督が実に9年間を費やし、完成させた映画は、バレリーナ独特の薄皮のような皮膚の内側で起こる性同一性障害の現実を生々しく描いて、時に目を背けたくなる衝動にすら駆られる。
ベルギー国内有数のバレエ学校に人より遅れて入学してきた主人公のララは、家族の理解の下、定期的に通院して男性としての二次成長を抑制する投薬量法を受けている。ホルモン療法によりさらなる女性化を目指すララだが、自然の摂理として生まれ持った性がそれを拒もうとする。レッスンでは、パッドでバストを強調し、股間にテーピングを施して逆に突起を隠し、華麗にピルエットを舞うララだが、彼女の才能に嫉妬したクラスメイトたちから残酷な嫌がらせを受けることもある。肉体の性と性同一性の不一致は、かくも日常レベルで過酷なものなのか。
やがて、ララに訪れる決断の時。それは、かつて映画が新たな概念の1つとして描いてきたトランスジェンダーへの一般的認識を、一気にアップデートするもの。人によっては理解の範疇外にあった世界を、同じ肉体を持つ人間として共感できるレベルにまで押し上げてくれる。
だから、ララを瑞々しく好演するアントワープのバレエ・スクールに通うトップダンサー、ビクトール・ポルスターが、役柄の設定とは違いシスジェンダー(肉体の性と性同一性が一致している人)であることを問題視する論調は、決して的を射ていない。誰が演じるかではない。人が本来の自分として生き抜くための努力と、挫折と、そして、葛藤の果てに訪れる自由こそが、作品のテーマなのだから。
それにしても、ララの家族や医療関係者の、何とフラットなことか!? 黙々と冷静に的確な治療を提案するドクターは勿論だが、娘の幸福のためならすべてを投げ打つ覚悟のシングルファーザーの父親が、どんな時も愛に溢れていて涙が出る。これは、ベルギーという国の成熟を痛感させる映画でもある。(清藤秀人)
キャロル(2015)
| 監督 | トッド・ヘインズ |
| 評価 | 3.60 |
解説
「太陽がいっぱい」「殺意の迷宮」などで知られる作家パトリシア・ハイスミスの小説を基にしたラブロマンス。同性ながらも強く惹(ひ)かれ合う女性たちに待ち受ける運命を追い掛ける。メガホンを取るのは、『エデンより彼方に』『アイム・ノット・ゼア』などのトッド・ヘインズ。『ブルージャスミン』などのケイト・ブランシェット、『ドラゴン・タトゥーの女』などのルーニー・マーラが共演。彼女らの熱演はもとより、舞台となる1950年代初頭のニューヨークを再現した美術にも注目。
あらすじ
1952年のニューヨーク。デパートでアルバイトをするテレーズ(ルーニー・マーラ)は、娘へのプレゼントを探すキャロル(ケイト・ブランシェット)に応対する。優雅で気品に満ちた美しさを誇るも、謎めいたムードもある彼女に魅了されたテレーズ。彼女にクリスマスカードを送ったのを契機に、二人は会っては話をする仲になる。娘の親権をめぐって離婚訴訟中の夫と争うキャロルと恋人からの求婚に思い悩むテレーズ。そんな中、彼女たちは旅行に出掛けるが……。
映画レポート
トッド・ヘインズの作品はしばしば、外観と中身のギャップというか、上辺からは想像もつかない、その奥で静かに進行しているドラマを描いている。平凡な郊外の主婦が薬に溺れ神経を病んでいく「SAFE」(1995)、華やかなロック・ミュージシャンの屈折と孤独を描いた「ベルベット・ゴールドマイン」(1998)、50年代のブルジョワの主婦が夫の秘密を知ったことで、黒人の庭師と禁じられた恋愛に踏み込む「エデンより彼方に」(2002)。彼(彼女)らは、社会やコミュニティの足枷のなかで感情を押し殺し、内側から徐々に崩壊していく。パトリシア・ハイスミスが50年代を舞台に書いた原作をもとにした「キャロル」も例外ではない。ケイト・ブランシェットとルーニー・マーラという二大演技派を起用し、当時はタブーだった女性同士の恋愛を語る。
デパートのおもちゃ売り場に勤めるテレーズ(ルーニー・マーラ)の前に、クリスマスのギフトを探すキャロル(ケイト・ブランシェット)が現れる。あでやかな金髪、すらりとした体躯にゴージャスな毛皮を纏った彼女に、テレーズはたちまち目を奪われる。だがその奥にわき起こった気持ちが何なのか、すぐにはわからない。ただこの人に再び会いたい、と彼女はキャロルの後ろ姿を見つめて思う。キャロルが忘れていった手袋を自宅に返送したことで、テレーズはキャロルから昼食に誘われる。
こうしてふたりの逢瀬が始まる。キャロルは夫と離婚調停中なのを語り、その謎めいた視線でじっとテレーズを見つめる。その興奮はテレーズにとって、結婚を迫るボーイフレンドからは得られないものだった。だが同性同士の付き合いはもちろんおおっぴらにできず、特に上流社会に身を置くキャロルにとってそれは、娘の親権を剥奪されかねない危険なことだ。だからすべては内に秘めたまま、その思いの丈が眼差しや控えめな身のこなしによって伝えられる。こうした繊細な感情を捕らえることにおいて、トッド・ヘインズほど相応しい監督もいないかもしれない。たとえばキャロルがテレーズの肩にそっと手を置く、それだけのことがなんと熱っぽく、エモーションを喚起することか。
もっとも、「エデンより彼方に」がダグラス・サーク的総天然色の世界だったのに引き換え、今回の50年代はもう少しくすんだ、緑がかった色調がベースになっている(撮影監督はヘインズの盟友エド・ラックマン)。それはソフトフォーカスを多用したショットと相まって、詩情に富み、まるでおとぎの国に迷い込んだアリスさながら、異世界に足を踏み入れたテレーズの夢心地を表現するかのようだ。
カメラマンを目指すテレーズはキャロルと出会ったことで初めて、人間を被写体として撮りたいという欲求が生まれる。つまりこれはテレーズが愛を知り、人間としてもアーティストとしても成熟する物語でもあるのだ。
「心に従って生きなければ人生は無意味よ」と、キャロルは言う。それを実践することがいかに困難を伴うか。だが、だからこそ得難い境地に至るのだということを、時代を超えてこの映画は訴えかけてくる。
ダンサー・イン・ザ・ダーク(2000)
| 監督 | ラース・フォン・トリアー |
| 評価 | 3.40 |
解説
60年代のアメリカ。セルマは女手ひとつで息子のジーンを育てながら工場で働いている。彼女に対して理解と愛情を持つ人々に囲まれ満ち足りた生活を送っていた。ただ一つを除いて。彼女は遺伝性の病のため視力が失われつつあり、ジーンも手術を受けない限り同じ運命を辿ってしまうのだった。そのために、内職もしてジーンの手術費用を貯えていた。が、ある日工場を解雇されてしまい、貯めていたお金まで盗まれていた……。歌手ビョーク主演のドラマ。カンヌでパルムドールと女優賞を受賞。
存在のない子供たち(2018)
| 監督 | ナディーン・ラバキー |
| 評価 | 4.32 |
解説
『キャラメル』などのナディーン・ラバキー監督が、中東の社会問題に切り込んだドラマ。主人公の少年が、さまざまな困難に向き合う姿を描く。ラバキー監督も出演するほか、ゼイン・アル・ラフィーア、ヨルダノス・シフェラウ、ボルワティフ・トレジャー・バンコレらが出演。第71回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞したほか、第91回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた。
あらすじ
12歳のゼインは、中東のスラムで両親とたくさんの兄弟姉妹と住んでいるが、親が彼の出生届を出さなかったため身分証明書を持っていなかった。彼は11歳の妹と仲が良かったが、知人の年上の男性と無理やり結婚させられてしまう。怒ったゼインは、家を飛び出して職を探そうとするが、身分証明書がないため仕事ができなかった。
映画レポート
この映画には、二種類の「存在のない子供たち」が登場する。12歳の少年ゼインの場合は、両親が出生届を出さなかったから。赤ん坊のヨナスは、母親のラヒルが不法移民だから。どちらも法的に存在していない。そんな二人が肩を寄せ合って生きる。家出してラヒルに拾われたゼインがヨナスの子守りをしていたとき、ラヒルが警察に拘束され、帰れなくなったからだ。氷と砂糖をミルク代わりに与え、懸命にヨナスの面倒を見るゼイン。12歳の弱者が、より幼く弱い者をかばいながらサバイバルする姿に、胸が痛まない人はいないだろう。
しかし、この映画の根底に流れるのは、そうした状況から醸し出される感傷ではなく、そうした状況を生み出す大人たちに向けられた怒りだ。その怒りの矛先は、まず子供を労働力としかみなさず、愛も教育も与えないゼインの両親に向けられる。そして、親たち(彼らもかつては存在のない子供たちだったのだろう)を、そんな大人にさせた社会に対しても。ゼインが両親に向けて放つ「世話できないなら産むな」という告発は、世話されない子供たちを放置している社会に向けられた言葉でもある。弱者の視点から社会問題をえぐる。そこに、この映画の芯の強さがあり、共感の源泉がある。
実際、劇中で扱われている社会問題は、少女の強制結婚、子供の人身売買、不法移民など、日本にはなじみの薄いものが多い。それにも関わらず「他人事」に思えないのは、育児放棄や虐待のニュースが後を絶たない日本の現実と呼応するドラマでもあるからだ。ゼインは、「生まれてこなければよかった」という理不尽な思いにかられながら生きている世界中の子供たちの代弁者だ。彼の告発のまなざしは、「生まれてきてよかった」と言える社会を実現する責任があるすべての大人に向けられている。
ゼイン役のゼイン・アル=ハッジは、レバノンに逃れて来たシリア難民。過酷な日常をたくましく生き抜きながらも、自身の非力さと限界に突き当たり、涙する場面が切なさをかきたてる。彼を筆頭に、ほとんどの出演者は役柄と似た背景を負っているという。これほどのリアルな存在感に圧倒されたのは、実在のストリート・チルドレンを起用した「サラーム・ボンベイ!」以来かもしれない。
ピアニスト(2001)
| 監督 | ミヒャエル・ハネケ |
| 評価 | 3.69 |
解説
ウィーン。小さい頃から母親に厳しく育てられたエリカ。40歳を過ぎてウィーン国立音楽院のピアノ教授となった今でも母と二人暮らし。ある日、エリカは私的な演奏会の席で青年ワルターに出会う。彼のピアノの才能に特別な感情を抱くエリカだったが、それ以上にワルターのエリカに対する思いは強かった。彼女に執拗につきまとい、ついには音楽院の試験に合格し彼女の生徒となってしまう。ワルターはある日、思いあまってトイレにいたエリカに強引にキスを迫る。ワルターの思いが通じたかと思われた瞬間、エリカがひた隠しにしていた秘密があらわになる……。
ベニスに死す(1971)
| 監督 | ルキノ・ヴィスコンティ |
| 評価 | 3.76 |
解説
イタリア映画界の巨匠、ルキノ・ヴィスコンティが、美少年への思いを募らせた老作曲家の苦悩を格調高く描いた文芸ドラマ。作曲家グスタフ・マーラーをモデルに描かれたトーマス・マンの原作を基に映画化。少年へ恋焦がれるあまりに破滅へと向かう作曲家を演じるのは、『召使』『ダーリング』などのダーク・ボガード。美少年を演じたスウェーデン出身のビョルン・アンドレセンの美ぼうも話題になった。マーラーの音楽と共に描き出される芸術的で退廃的な世界観を堪能したい。
あらすじ
1911年、イタリアのベニス。静養に訪れた作曲家のアシェンバッハ(ダーク・ボガード)は、宿泊先のホテルで見掛けた少年タジオ(ビョルン・アンドレセン)に一目で心を奪われる。タジオへの思いが抑えられないアシェンバッハだったが、折しもベニスではコレラがまん延し始め……。
パリ、テキサス(1984)
| 監督 | ヴィム・ヴェンダース |
| 評価 | 4.07 |
解説
W・ヴェンダースが、S・シェパードのシナリオを得て描いたロード・ムービー。テキサス州の町パリをめざす男。彼は失踪した妻を探し求めていた。男は、4年間置き去りにしていた幼い息子との間にも親子の情を取り戻す。そして、やがて巡り会った妻に、彼は愛するがゆえの苦悩を打ち明ける……。
アデル、ブルーは熱い色(2013)
| 監督 | アブデラティフ・ケシシュ |
| 評価 | 3.67 |
解説
第66回カンヌ国際映画祭で史上初、パルムドールが主演女優2人にも贈られ話題を集めたラブストーリー。ジュリー・マロによるフランスの人気コミックを原作に、運命的に出会った女性同士の真っすぐな愛の行方を大胆なラブシーンを交えて繊細に描き出す。監督はこれまで数々の映画賞に輝いてきた俊英、アブデラティフ・ケシシュ。『マリー・アントワネットに別れをつげて』などのレア・セドゥと、『カレ・ブラン』のアデル・エグザルコプロスの体当たり演技が光る。
あらすじ
教師を夢見る高校生アデル(アデル・エグザルコプロス)は、運命的に出会った青い髪の画家エマ(レア・セドゥ)の知性や独特の雰囲気に魅了され、二人は情熱的に愛し合うようになる。数年後、念願の教師になったアデルは自らをモデルに絵を描くエマと一緒に住み、幸せに満ちあふれた毎日を過ごしていた。しかしエマの作品披露パーティーをきっかけに、二人の気持ちは徐々に擦れ違っていき……。
映画レポート
ボブ・マーリーとサルトルが同列に語られる。そのまさかの接続。預言者と哲学者は同じだと主人公は言う。そんな発言を聞けば、微妙に納得はできるものの、ジャマイカのレゲエの聖者であり闘士でもある歌い手と、西欧の近代思想の核となる哲学者とをこうやって繋げることの出来る女子高生とは一体何者か? それがフランスであると言ってしまえばそれまでなのだが、いずれにしてもこの映画が常に示すのは、こういった不意の出会い、あらぬ方向へと繋がる接続である。
通学バスに乗り遅れそうになった主人公が焦って走るシーンから始まるこの映画は、いつもどこか息せき切っているように見える。焦っているというより、もしかすると今ここで起こるかもしれない不意の出会いを逃すまいとする研ぎすまされた時間感覚と言った方がいいだろう。自分の身体の周囲に延びて行く触毛のような神経細胞が感じる時間とも言える。「私」という個人がはっきりと確立する前の高校生の物語、という設定も、そんなことを思わせるのかもしれない。また、主人公の性的な立場の不安定さもその一因かもしれない。
とにかくそこに生まれる輪郭の微妙な揺れを、カメラがとらえる。画面に映る風景の中に流れる空気の動きが、自然に身体に伝わる。気がつくとその空気に乗って、街角から見知らぬ音楽が聞こえてくる。そしてその一瞬、時間の流れが緩やかになり、主人公は交差点で運命の人とすれ違うのだった。不意の出会いの訪れとはこのようなものなのだと、全身でこの映画を肯定したくなる。その積み重ね。だからすべてが不安定で、もしかするとあったかもしれない別の人生が、そこからふと顔をのぞかせる。その可能性を身体中に染み込ませ、私たちも主人公も大人になるのだ。そんなことを思わせる3時間。もちろん最後に再びあの音楽が……。こうやって映画も人生も、あったかもしれない別の人生もまた、果てしなく広がり続ける。だからこそ私たちは、いつまでも映画を観続けるのだろう。
アンチクライスト(2009)
| 監督 | ラース・フォン・トリアー |
| 評価 | 3.00 |
解説
息子を事故で失った夫婦が深い悲しみと自責の念にさいなまれ、森の中の山小屋に救いを求めて迷走する姿を描くチック・スリラー作品。『ダンサー・イン・ザ・ダーク』の鬼才ラース・フォン・トリアーが、主演にシャルロット・ゲンズブールとウィレム・デフォーを迎え、絶望のふちに追い込まれた夫婦の苦悩とてん末を過激で大胆な描写を交えて描く。第62回カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞したシャルロットの熱演に圧倒される。
あらすじ
愛し合っている最中に息子を事故で失った妻(シャルロット・ゲンズブール)は罪悪感から精神を病んでしまい、セラピストの夫(ウィレム・デフォー)は妻を何とかしようと森の中にあるエデンと呼ぶ山小屋に連れて行って治療を試みるが、事態はますます悪化していき……。
映画レポート
忘却の彼方の感もあるドグマ95の誓い。提唱された自律のルールはいっそ不自由という自縛の術の獲得法ともみえて、そんな自虐的束縛を創造の原点とするラース・フォン・トリアーの映画作りの神髄を示唆してはいなかったか。自虐の要素を除去することが最も苛酷な自身の痛めつけ方(最大の快楽の取得法)と心得た監督の新作「アンチクライスト」の、ドグマお構いなしの(黒白、スローモーション、ヘンデルの調べ……)プロローグ! 迷いなくそれを差し出して映画は鏡張りの球の中の自我宇宙へと観客を導く。
「ドッグヴィル」「マンダレイ」に続く一作が頓挫し陥った鬱状態を脱するためのセラピー映画。そう告白して改めて自縛装置を完備する監督は心療セッションそのままの問答で台詞を紡ぐ。子供(=新作)の死と対峙するセラピスト/夫(=トリアー)と患者/妻(=同)。ふたりでひとりの“私”を恐怖のピラミッドの頂点と認めるまでに通過する頭の中の景色。自問自答が画面の内(物語)と外(セラピー)とで微かにずれつつ響く。男と女、理性と直観、文明と自然の壮絶な格闘。心理劇、ホラー、寓話。ベルイマン「鏡の中にある如く」→聖書コリント人への第一の手紙13章→愛と信仰と希望→本作の悲嘆、苦痛、絶望。と、幾通りにも解釈可能の世界。だがトリアー界に在るのはトリアーだけ。ヒロイン(“私”のひとり)を葬っても顔のない無数の私(ヒロインたち)がまた湧き出でて地獄絵を完遂するだけだ。そこに創造源たる無間を確認し閉幕する自己チュー分析エンターテインメント。それは苦しさを喜々と楽しむ監督/神/悪魔の手の内をさらりと開示し、そのあっけなさでこそ興味深い怪作となっている。
ドライブ・マイ・カー(2021)
| 監督 | 濱口竜介 |
| 評価 | 4.02 |
解説
村上春樹の短編小説を原作に描くヒューマンドラマ。妻を失い喪失感を抱えながら生きる主人公が、ある女性との出会いをきっかけに新たな一歩を踏み出す。『寝ても覚めても』などの濱口竜介が監督と脚本を手掛け、『きのう何食べた?』シリーズなどの西島秀俊が主人公、歌手で『21世紀の女の子』などで女優としても活動する三浦透子がヒロインを演じ、『運命じゃない人』などの霧島れいかや、『さんかく窓の外側は夜』などの岡田将生らが共演する。
あらすじ
脚本家である妻の音(霧島れいか)と幸せな日々を過ごしていた舞台俳優兼演出家の家福悠介(西島秀俊)だが、妻はある秘密を残したまま突然この世から消える。2年後、悠介はある演劇祭で演出を担当することになり、愛車のサーブで広島に向かう。口数の少ない専属ドライバーの渡利みさき(三浦透子)と時間を共有するうちに悠介は、それまで目を向けようとしなかったあることに気づかされる。
コメント
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です。
関連記事
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】ivfree.asiaは安全?視聴方法や代わりサイトまで一気にご紹介!
- Aoi / 2024-01-18【2024年最新】カリビアンコムのダウンロード廃止?今なら使えるカリビアンコム動画のダウンロード方法!
- Aoi / 2023-12-26【高品質かつ安全】Supjavからアダルト動画をダウンロードする方法
- Aoi / 2023-12-21【23年最新】Avgle ダウンロードの裏技を公開!簡単に高画質動画を入手~Android・iPhone/iPad・PC全環境対応
- Aoi / 2023-11-30av4.usが閉鎖!?代わりの無料アダルト動画サイトをまとめ
- Aoi / 2023-11-29【無料】TokyoMotionダウンロードする方法、その操作手順まで詳しくご紹介!(PC&スマホ)
最新記事 人気記事
Kira / 2024-09-24
【無料】ディズニー動画ダウンロード方法おすすめ|ディズニー+から映画を保存してオフラインで視聴しよう
Kira / 2024-09-24
SwitchでHuluは見れません!その理由と今後の動向を予想して裏技まで紹介します
Melody / 2024-09-24
【2023年】Huluを録画する方法!裏ワザ?真っ黒にならないソフトを紹介します
Kira / 2024-09-24
AbemaTVをダウンロード&録画できるツール7選!DRM解除できるものだけを厳選
HANA / 2024-09-24
【ABEMA ダウンロード】ABEMA(旧AbemaTV)動画をダウンロードする方法、ダウンロードできない原因と対策
youjinkin / 2024-09-24
U-NEXTで鑑賞できるおすすめアニメ作品TOP 20
Kira / 2024-09-24
U-NEXTがダウンロードできるツールトップ7!録画ソフトも
Melody / 2024-09-24
【完全保存版】U-NEXTのダウンロード方法!できない時の原因と解決法も
Tetsuko / 2024-09-24
StreamFab myFansダウンローダーの機能や使い方、評判をレビューして徹底解説!
Tetsuko / 2024-05-09
Missavの無料エロ動画をダウンロードするツール5選
展開 ∨ 折りたたみ ∧
ホットトピックス

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次

StreamFab 動画 ダウンローダー
>
1000+のサイトから映画やアニメを無制限にダウンロードでき、最新コンテンツの1080pでのダウンロードをサポートする唯一のツールかもしれません!
目次
Copyright © 2024 entametalk.jp All Rights Reserved.
年齢認証

あなたは18歳以上ですか?
エンタメTALKはアダルトコンテンツを含みますので、18歳未満の方の閲覧を固くお断りいたします。
いいえ はい